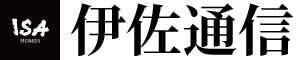- HOME
- エフエム世田谷 「わたし歳時記」
エフエム世田谷 「わたし歳時記」
世田谷区をはじめ、杉並区、中野区、渋谷区、目黒区、狛江市などで聞くことができるコミュニティ放送局「エフエム世田谷」。
伊佐ホームズは、ここに「わたし歳時記」という15分の番組を提供していました。これは毎月お一方にご登場願い、生き方・暮らし方をお聞きするというもの。分野は各界に及びますが、いずれも自分の世界を築かれている素敵な方々です。
〈番組は終了しました〉
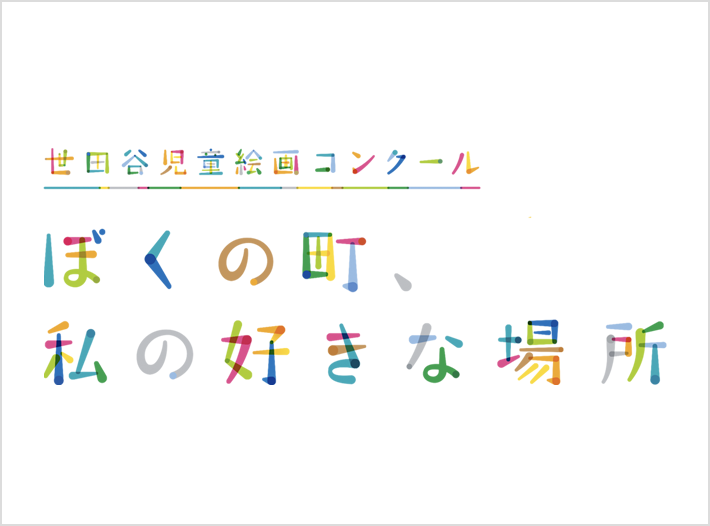
大林宏也さん

司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、東京農業大学 教授 大林宏也さんです。どうぞよろしくお願い致します。
大林:お願いします。
司会:大林さん、1965年神奈川県のご出身です。木材工学を専門として、現在、東京農業大学地域環境科学部 森林総合科学科で研究なさっています。
先週は、日本の森林問題についてもお聞かせいただきました。その問題につきましては、研究者だけではなくて、木を扱う企業も真摯に取り組んでいる会社もあります。実はこちらの伊佐ホームズさんも、かねてからさまざまな取り組みをされていますので、今日は、伊佐ホームズからこの方にもご一緒いただこうと思います。設計部の小柳雄平さんです。小柳さん、設計部の所属ですが、木材・森林関連も担当されていらっしゃるのですよね?
小柳:はい、こちらはですね、伊佐ホームズが数年前から取り組んでいる動きなのですけれども。今、木材の価格が、すごく安くしか原木を買えないような状況が続いているのですけれども、そちらを工務店として、材料を、木材を使っている会社として、何かそれは出来ないかということで。改革したいなという思いから動き始めたのですけれども。今、山元に直接工務店が原木を購入する形を我々とっているのですが、その価格がそのまま、山元がこれから木材をさらに生産して、山づくりに貢献できる・還元できる費用で、直接工務店が山元から購入し。で、その山元の方々はもちろん生産するのですが、生態系だとかも重視したような形でやってもらうというような取り組みをやっております。
司会:で、会社を作られたのですよね?
小柳:そうですね。主にはQRコードを原木1本1本につけて、それが最終的に、お客様に物件をお引渡しした際には、今までの山元の山主の情報だとか、丸太の大きさの情報だとか、製材された情報、強度とかも全部履歴に残っているような形で、今QRコードを通して、お客様にも見せられるので。そのような付加価値を木1本1本に与えて、実際に運営できるシステムを作れたのですけれども。これを伊佐ホームズ一社でやっていても、なかなか山に還元するかというと、日本全国で見ると本当に微々たるものなので。これはちゃんと工務店として、全国の工務店と力を合わせてやっていきたいということで、これを会社化させまして。「森林パートナーズ」という会社を2年前に別会社として作って、で、これを全国的に展開していって、地域・地域ごとで、それぞれの地域の事情に合わせたシステム作りを作っていってもらうのですが、それのノウハウを我々は提供していって。お客様・消費者も含めて、山元と一体になってやっていきたいというような会社をつくりました。
司会:関わる人が良く見える状態というか、明るい状態にしているというような気がするのですが、これを作るにあたって、大林さんと関わったということですか?
小柳:作るときにはまだ、実はお会いはしていませんで。先生と会えたきっかけはですね、我々も工務店の立場で山元に入って、いろいろな山の問題・取り組みをやっている中で、土木側からですけど、同じように山と取り組みをやるというような意識を持った方と出会うことが出来まして。その方が東京農大出身で、大林先生のゼミの学生だったということで、先生をご紹介いただいた次第です。
司会:大林さんはその取り組みを聞かれた時にどんなふうに感じられましたか?
大林:そうですね。家を建てる側が山へ行って、この木が自分の柱になりますとかって、そういうようなやり方もあって、今までも聞いたことがあったので、「へぇ、そういうのがあるのか」と思ったのですが、実はそうとはちょっと違ってですね。もっと大きな流れで、使う木材を山のある地域から、必要な量の情報が出てということで、ただ一本、一本、この木だよ、この木だよってことではなくて、必要な量の情報というのが行き来して、その樹木、林木というのですかね。山の木から自分のところで使う木材になって、「帰ってくる」というのですかね、「行ってしまう」というのですか。移動していくという流れがあるので、なかなかこれはおもしろいじゃないかな、と。さらに目黒・世田谷、そういった都会の地域から、例えば、秩父であるとか、奥多摩であるとか、そういう山、生産しているところまでの、どちらかといえば近距離の関係があるので、もしかすると、これをうまくやっていくといいんじゃないかな。それからもうひとつ、先ほどあったように、各地域でそれを展開するとなると、別に一か所で縛っているわけじゃないので、それを工務店と山の関係が出来る場所が、日本中にはいっぱいあると思うので、それを広げていけるのではないかなというふうに思いました。
司会:あの、いろいろな分野で力を合わせるというのは、かなり広がりが出てくるというか、これは日本の森林を守るというところにも繋がっていくのかなと思うのですけれど。
大林:そうですね。どちらかというと、「使う」という方ですかね。使っていかないと困るので。今までだと、使ってはいたのですけど、もうちょっと…よく川上とか、川下、川中とか、山と消費者とをつなぐ言葉があるのですが、山の方、川上のほうは川上のほうで、自分たちの都合で木を作って伐採して。川下と呼んで使う方は、自分たちが欲しいのは、こんなのが欲しい欲しいと言っているだけだったのが、合えば、その情報が出会えば、もしかすると日本の山の木をどんどん使えるような状況になるんじゃないかなとは思います。
司会:有効にということですね。そのへんについては、小柳さんはどんなふうに考えていらっしゃいますか?
小柳:はい。有効にももちろんそうだと思うのですけど、今までは寸断されていて、なかなか需要情報が山に行かないということ。ただ、今までの時代が、消費側が一時期すごく盛り上がっていたときがあるので、山はもう出せば売れるというような感覚で、木を出していた時からの体制が今残ってしまっているというのが、一つ問題はあると思うのですけれども。これから人がどんどん少なくなっていってしまう時代の中で、出せば売れる時代でもないので、これからはもちろん消費者の情報をちゃんと山に投げて、それに伴った伐採をしてもらって。我々も一応金額を取り決め価格でやっているので、山元としてもこれだけ出せばこの位のお金が入ってくるというのも、ある程度見込んだうえでの経営が出来るので、長期的な経営を、山はそれこそ川下と川上とで連携しながらやっていくという情報交換はもちろん大事だというふうに思います。
司会:今ちょうどそれがうまい具合に形になっているところだと思うのですが、これからはどういうふうな展開をお考えでいらっしゃいますか?
小柳:ますますなんですけれども、今我々が出来たのが、一つの情報のプラットホームを作って、そこに皆が参画してもらっている。山元から製材所、プレカット工場、工務店と、あとお客様も含めてですが。そこに情報が集約されて、そこからみんな情報を貰えるという、みんなフラットな今関係で取組みが出来ていて。なので、このような「見える化」されているようなプラットホームを持つというこの流通を、ますます広げていければということで全国展開していきたいというふうに思うのですけれども。やっぱり我々の工務店とか、山元、そこの流通だけじゃなくて、一番大きいのはどうしてもお客様になりますので、お客様が共感して、その価値を共感してもらえるようなシステム作りをして、それを地域ごとに構築していってもらうというところが大事なので。私が先生と実はこれからやっていきたいというのはですね、木の価値というものを、民間として出しているところにですね、大学の先生としての意見を入れていきながら、連携したような形での価値として作り上げて、お客様により訴求していきたいというふうに思っています。
司会:大林先生はいかがですか?
大林:そうですね。ビジネスとしてそうやって木材を使うにあたって、自分のところはこの山のこの木を使っているのですよ、この地域の木を使っているのですよ、というのが一つですが、その木は、ちゃんとした強度を持っていますよとか、表面の模様がいいというのを表現するのは難しいのですが、問題がないですよとか。いろいろ木材そのものの情報というのもあると思うのですね。そういうものが、もしかすると、家を作る人、建てる人にとって、必要なことかもしれないので、そういった情報が、どういう情報が欲しいのだろうか、あとはそれを、例えば工務店で説明できるのだろうか。いや、そのために、例えば大学の人が説明した方がいいのだろうかというような違いもあると思うので、そういう違った目線で協力していきたいなとは思っています。
司会:これからますます楽しみな取り組みだと思いますが、また何か動きがあったらぜひ お聞かせいただきたいというような気分がしております。今月は「わたし歳時記」、東京農業大学 教授 大林宏也さんにいろいろと森林の問題など含めてお話いただきました。ありがとうございました。そして今週は伊佐ホームズ設計部の 小柳雄平さんにその取り組みについて伺わせていただきました。お二方ありがとうございました。
大林・小柳:ありがとうございました。
岩本康さん
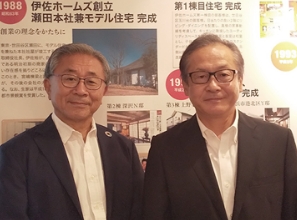
司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、(株)世田谷サービス公社 社長 岩本康さんです。よろしくお願い致します。
岩本:よろしくお願いします。
司会:社長、4週にわたって、岩本さんのお話をお聞きいただいたと思うのですが。ゆっくりお話されるのは今日が初めてというふうに聞いていますが、いかがでしたか?
伊佐:まず、あのお生まれになって、少年時代が私は田んぼ派だったと。私も田んぼというのは、どうしようもなく胸が、こう、キュンとくるという風景でしてね。そして、どっちかというと、動くよりは田んぼをよく眺めたという、思索されるお姿というかな、少年。それが徐々に、世田谷区役所時代でも、いろいろな仕事をされながら、まんべんなくものを見つめられる少年の姿がですね、これだけ立派なお仕事をされてこられた区役所時代のお仕事の姿に重なってくるのですよ。それと高校時代は、山岳部で、飯豊連峰、蔵王連峰、年間60日いらっしゃったという。そういう点で、ずっと沈黙の中に物事のエネルギーをためていかれる方かなというふうに勝手に想像しているわけですけれども。 私も大学ほとんど授業に出ず、大変な成績で卒業させてもらったので、ここもまた 共感を大変致して(笑)もう嬉しいのですよ。
岩本:ありがとうございます(笑)
伊佐:私は今、サービス公社の4週にわたるお話を聞いてですね。従業員さんが約1000名弱ですよね。そしていろいろな方がいらっしゃる。時代の典型の組織ですよね、今の。障害者の方、女性、高齢者の雇用含めてですね。これはまさに、時代が今後これはどう展開するかということをみんなが注目する、典型的な組織ですよね。当社は小さいですが、やはり病気休暇中が2人いるのですよ。こういう人間たちを守りながら、残った人間がやっていくという。それは社会資本、人間の資本を活かしあっていくというか。当社、環境との取組みをやっているのですよ。森を育てる家づくりということで、森の環境を守るための工務店としてのやり方を、日本で最初にやっていましてね。我々が直接山にお金を払って、職人が出来る価格で買って、お金を直接渡すのですよ。そうしないと、流通で取引先に渡していきますと、結果的にそれが山に戻っていないのですよ。私は確固としてそういうことをやってきましてですね、そういう点で、環境と今社会的な問題を、人間の問題を解決していくというのが私の会社の経営。本当に公社さんは出来て35年。その頃よくこういう公社を作られましたよね。その頃の区長さんは、岩本さんが入られる前のお話?入られた頃ですか?
岩本:入った直後くらいでした。確かに、先進的都市・世田谷だとは思います。株式会社を行政の出資で作るという。そういう意味では、3セク(第3セクター)というのがそんなにまだ手法としては少なかった頃だと思います。
伊佐:そうでしょうね。3セクの失敗例というのは、よく全国的に話題になりましたよね。ここまで定着されて、拡大されて、大きな役割を果たされてくるわけですよね。重要な役割ですよね、これ。岩本さん、就任4カ月ですよ?(笑)
岩本:そうですね。まぁ、世田谷方式というのでしょうか。結局区民がご利用になる集会施設とかを、安定した品質というのでしょうか。あとは、地域のさまざまな町会の方々とか、商店街の方々がいますけれども、それのネットワークを活かしながら、管理させていただくというのが、まさに第3セクターならではの仕事だと思っていますので、そこをねらって設立したという35年前ですね。凄いなと思いましたね。
伊佐:凄いですね。それじゃあ、官と民がうまくつなぎ役として、うまくいっている例のひとつですよね。
岩本:と、思います。
伊佐:また、民の、我々の商店街の会長さんとか、皆さんも、非常に公社に対する愛着をもっていますよね。
岩本:本当にそれが宝だと思っていますね。
伊佐:やっぱり区民としても 出会う機会が多いですよね。施設が60…?
岩本:62施設くらいですかね。
伊佐:我々はいつもお世話になっているわけですね。
司会:本当に密着した会社ということになりますよね。
岩本:そうですね。地域とのつながりというのが、施設スタッフそれぞれみんな持っていわるわけですけども、それが宝だと思いますね。
伊佐:じゃあ職員の方も誇りを持っておられますよね?
岩本:はい、そうですね。その誇りを大切にしてですね、頑張ってほしいなと思っていますね。
伊佐:現役の区役所時代のみなさんの誇りとまた違った意味の誇りというのは、どのへんが違いになりますか?まだまだね、短いでしょうから…。
岩本:そうですね。行政そのものじゃないものですから。で、特に、自分で考えなくちゃいけないというとおかしいですが、ただ責任を取りながら、舵取りをしていくというのはちょっと今までと違うものですから。そこはちょっとキリッとしなくちゃいけないなと思っています。
伊佐:ちょうど私は会社を作って今32年目になるのですね。その前に大きな会社に一応14年いて。そこは約8000名の会社でしたので。私は、やはり愉快な会社を作りたいなって。仕事の途中が愉快、出来たものは最高。で、会社の経営も安定するという。愉快ということが大事かなと思って。当社創業以来、忘年会をやったりですね、これは大変な演芸大会になるのですよ。あるいは、会社で、研修旅行で、日本のいい建築を見る旅をしたりですね。やっぱりプロセス、プロセスが愉快であって、いいものが出来る。で、近頃、私は社会の問題と取り組むことが多くなりましてね。先ほど申し上げた林業の問題。結果的に、これが地方創生のひとつのお役に立ちそうなことが、いろいろありました。今年から世田谷区のほうでSDGs、持続可能社会の実現目標ということで、子供たちに自然環境での教育が始まりまして。少しこれを私もお手伝いしてですね、山側として。そんなことも始まったりしてですね。そういう架け橋をつくる仕事が増えました。また、今秩父とか川越の古い建物を活かした美しい旅館を作ろうというプロジェクトを進めていましてね。これも地域の財産を活用するという。もうひとつは、お寺の檀家さんが減っていくのでですね。どう地域と繋がるかということを、構想から一緒に入りましてね、ご住職と。それを設計に落とし込んで、現場に落とし込んで。そうやって檀家が増えていって、そして地域の方が安心できるような場所に変えていこうという、新しいお寺像というか。私は工務店という、究極は建築の仕事なのですが、社名は伊佐ホームズという、「ズ」なんですね。複数(形)。そこに周辺の仕事があると思っていたのです。近頃はそういう社会の取組みが自分の仕事になってきたところがありまして。そういう点では、私、公社さんというのは、公社さんという聞いたところの縛りについて、心配することもあるのですよね。限定されているのかなと思って。逆に民間と競うようなレベルをされること自体が、機能が増していくかなという気もしたり。で、先般のジャルダンの活用の話。結婚式。あれは、東京一の結婚式場にできませんかね~?
岩本:ありがとうございます。
伊佐:そしたら、少子化の問題も解消される一つの提案になると思います。ここまで大きな組織ですからね。そんなことをやっていただく公社になっていただきたいなというのが、私は新社長に期待。…なんか今日は私が新社長へのインタビュアーという感じですな(笑)
岩本:ありがとうございます(笑)
司会:どうでしょう、岩本社長?今のお話で。
岩本:そうですね。こじんまりせず、ですね、夢を持った仕事をしたいと思いますね。伊佐社長のご本、著作を読ませていただいて。「信じたことひとつだけ」という、信念のかたまりみたいなふうに私は受け取ったのですけれども。それを実現されていく。本物の家という、まぁ単純な言葉ですけれども、凄い思いが、社長の頭と心の中には、もうその具体的な本物の家という像があって。私はそこまでいけないですけれど。そういう具体的なイメージというのですかね、夢を持ってやらないと、社員に伝わらないのだなという気はしますので、頑張っていきたいと思います。
司会:あの、おふたりとも共通のご趣味がおありなのですが…。
伊佐:今、私は月2回、山に行っていますね。
司会:岩本さんは、奥様も一緒に山登りを楽しんでいらっしゃると?
岩本:40過ぎてからまた再開したのですけど。その時の再開のきっかけは、妻が自分で登りだしたと。ただ一人じゃ高い山には行けないので、付き合うようになって復活したというきっかけですね。
司会:でも、そんなふうにいろいろ気分転換をしながら、伊佐社長も岩本社長も、お仕事のほうもますます意欲的に頑張られているところではないかなと思うのですが、今後ますますいろいろな意味で、お互い刺激が深まりそうな気がいたしましたが。あの…
伊佐:時間ですか?
司会:そうなのです。もっともっとお聞きしたいことはあったのですが、今月5週に渡って、世田谷サービス公社の社長 岩本康さんにお話をいただきました。ありがとうございました。そして今週は伊佐社長も加わっていただきました。ありがとうございました。
岩本 ・ 伊佐:ありがとうございました。
西山敏樹さん
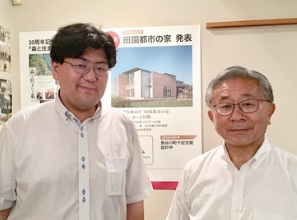
司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、東京都市大学 准教授 西山敏樹さんです。どうぞよろしくお願い致します。
西山:どうぞよろしくお願いします。
司会:西山さん、1976年東京都のご出身。交通移動手段におけるユニバーサルデザインとエコデザインの融合をテーマに、大学だけでなく、シンクタンクの両方で、研究者としてご活躍でいらっしゃいます。さて、今月4週目の今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただこうと思います。社長、よろしくお願い致します。
伊佐:はい、お願いします。
司会:3週、お話を聞いていただいたかと思うのですけれども、社長、お聞きになっていかがでしたか?
伊佐:まず、私はね、赤羽の電車の話が大変感銘を受けました。あれ、小学校の高学年くらいですか?
西山:高学年…、それより下ですね。ずっともう、10歳、12歳くらいまで、ずっと電車を見て育ってましたね。
伊佐:あの頃の風景がかなり人生を支配することが…
西山:ありますね。
伊佐:そして先生はその後、いろいろなお年寄りのお困りになっていることに対する思いやりから、どんどん学問が進んでいって。
西山:まぁ、そうですね
伊佐:僕は、ユニバーサルデザインって、結構「冷たくてかっこよくて」っていうふうにとっていたのですが、全く違うという。人間学から来たことだということを、3回のお話を聞きましてね。
西山:よくね、そこを誤解されるところがありまして。なかなかデザインの分野でも、何か一ついいものを作ればいいのだろうとかね、結構誤解が多くて。そこで苦労をしておりますが。
伊佐:まぁ、私は住宅をやってきて、家庭の中の心のユニバーサルはあるかもしれませんが、そういう普遍的な価値観とはかなり違うのが我々住宅で。まぁ、違うから住宅かなって。家庭、全部違うわけですから。そう思いながら、先生の学問の領域がどんどん広がっていかれていますよね。東急田園都市線の沿線の交通手段の問題。これ、まさに社会の問題ですよね。
西山:本当そうですね。今、エイジングシティという言葉がありまして。人も年取って、インフラも年取る。サービスも年取るというところで、いろいろなものが老化しちゃっているのですね。そこらへんを住宅とか住環境の問題を含めて考えていかなきゃいけないということですね。
伊佐:だから便利になっても、一杯の不便、困った社会問題が溢れていますよね。これをつなぎ合わせて、総合的に、体系的に、道を開いていくような研究・学問が必要だと思いますし。まさに先生はそれをやっておられるなと思って。
西山:いやいや。あの、人間をやっぱり中心にデザインするということが忘れられてきちゃっているので、そこをやっぱりもう一回取り戻して、やっていきたいと思いますね。
伊佐:よく、科学技術の発展というのは、文明の進化だと思うのですが、それは本来手段であって、文化ですよね。心の充足、ということですよね。その関係は、我々は忘れてはいけないなと思いますし。
西山:文化というのもひとつ大事で、その土地その土地の培ってきたものってあるのですよね。それを壊してやるものじゃないですよね、ユニバーサルデザインって。
伊佐:そうでしょうね。
西山:私たちが心がけているのは、「制作のコピーは絶対にしない」ということなのです。だから例えば、三鷹でやっていても吉祥寺のコピーは絶対しないということ。そういうことをやらなければいけない、心がけなければいけないということですね。
司会:その土地、その土地に合わせた。ということは、先生がおっしゃっていた最初の調査とかも物凄く大変になりますね。
西山:それは、その土地を対象にやりますから、どこかの土地の仕事があっても、それは絶対に使わないですね。
伊佐:それは凄いご決意ですよね。結構切り売りのコピーが多いことありますよね。
西山:それで失敗する事例というのは、実はたくさんありましてね。視察とかいって、あちこち行くじゃないですか。そうすると、そこの土地に影響を受けちゃいますよね。それがないように我々も心がけなければいけないっていう。そこは肝に銘じています。
伊佐:一回一回が真剣勝負ですよね。
西山:真剣勝負でやりますね。そういうことです。
伊佐:相手になりきって考えるという。尊いですよね。今、私は林業と取り組んでいまして。森林環境を守る工務店として、そういういい住宅を作っていきたいと思って。まぁ、森林環境を守るという、今の社会問題に取り組んでいましてね。先月、キノコの学者さんを秩父の森に連れて行きましたらね。この方は、500の菌を持っている学者。そして、場合によってはですよ、秩父は石灰岩が多いから、トリュフができるかもしれない。私は森林のその資源をね、多面的に活用したいと思っているのですよね。
西山:そうですよね。だから足し算じゃないのですけどね、ここからどういう付加価値が生まれていくのかみたいなことを、地域で考えて、経済を回すみたいにしていかないとダメですね。
伊佐:それが出来ますとね、下草刈りというのは、木材のための下草刈りってかなりキツイと思うのですがね。草を刈ってですよ、今度キノコの生産がもし出来るならば、素晴らしい前向きなことですよね。
西山:で、そういうのを、街の特性とか、ブランディングとか、文化としてやっていくということが非常に大事になるのですよね。
伊佐:だから私は都市と地方といいますか、山、あるいは森林と、それを繋ぎたいというのが私の思いでしてね。そういう点で先生の学問の領域の広がり方というか、あるいは足し算するという、そして何かを生み出すということについては、大変私も感銘を受けましてね こういった形で我々も仕事を開きたいなと思いましたね。
西山:イノベーションとか、よく言うじゃないですか。それで新しいことをやったというと、割とホッとしちゃう人が多いのですよね。それがやっぱりいけなくて。今ね、イノベーションを繋ぐとか、イノベーション融合という言葉が出て来て、イノベーションが起きたら、さらに何かと足していかないと、常に新陳代謝しないとダメだというふうに、我々の世界もなってきているのですよね。
伊佐:そういうことですよね。
西山:なんかねスパイラルアップというか、らせん状にどんどん発展していくみたいなことを目指さないと…
伊佐:インフレスパイラルというか、らせんですよね。
西山:そう、らせんなんです。その感覚を忘れるとダメになっちゃうのですよね。
伊佐:おっしゃるとおりですよね。
西山:それで、住宅というのは、皆一生に一回の大事な買い物だと思うのですけど、その一方で周りはシェアリングとかね、サブスクリプションといって期間ごとに使うとか、「持たない社会」になってきちゃっている中で、住宅はやっぱり欲しいと思うのですよ、それは。
伊佐:先生ね、当社特許をとった住宅があるのですよ。それは住まい方が半日で変革できるというか。これはある面じゃユニバーサルな…
西山:ユニバーサルですね。状況に応じてね、出来ますから。
伊佐:若いときは夫婦だけ。その後子供さんが増えて家族が多くなる。その後また少なくなる。それに対応が出来るということ。これは戸建った住宅であっても、だれでも住みやすくなる。その掛け算であろうと思っていましてね。そういう点では、ユニバーサルが少しあったかもしれませんね。
西山:住む人も年齢が変わりましてね、子どもも大きくなりますし。やっぱりね、可変式って結構大事ですね。可変式っていうので、状況を変えて、そこで使っていくということで、未来永劫使えるとか、サステナビリティを維持するとか、そういうことにもなっていくと思いますね。
伊佐:これは貸家として貸す場合にも、いろいろな家族に対応できるわけですからね。そういう点では大変いいかなと思いますね。
西山:いいと思いますね。やっぱりシーンに応じて変えられるというのは、一つ大事なもので。やっぱり固定していると大変ですよね、住宅というのはね。
伊佐:固定しすぎたために、価値が限定される。
西山:っていうのがあって、それで価値を上げていくというのは大事ですよね。
伊佐:中古住宅になった場合でも、汎用性が高いという。
西山:…ということが、いろいろなシーンに使えることが大事だと思いますね。
司会:それは、お家だけじゃなくなく街にも言える話ですよね。
西山:双方に言えますね。だからもうひとつ大事なのが、AIが入ってきたりだとか、人が少なくなってきて、AIに任せられる部分もあるのだけど、任せられない部分もやっぱりあって。いわゆる士業というのは、任せられないと思うのです。我々もそうなのですけど、教師とかね、看護師とか、保育士とか…。
司会:あ、「士」とつく…、
西山:「士」というのは、「師匠」でもいいですし、「武士」の「士」でもいいのでしょうけど、士業は人間の機微があるので、やっぱりそういうふうに峻別していくということも我々大事で、そういう機能をどうしても、この家の中にも入ってくる。エネルギーのマネジメントとかもそうでしょうし。
伊佐:そうですね。
西山:だからそれで、本当にどういう状態が一番いいのかっていうのを、建築とかでも見ていかなければいけないと思いますね。
伊佐:おっしゃるとおりですね。ソフトとハードと、他分野との掛け合わせですよね。
司会:私たちには、それを選別する重要な課題がまた出てくるような気がしますね。
西山:ありますね。今大学でその人材を育成している段階です。目利きになってもらわないとね、ダメなのです。
司会:そうですよね。
伊佐:そういう点で、先生、学生さんは育てていますか?
西山:今育ってきていますので、そこに期待していただけると有難いなと思いますけどね。
司会:お二人、お話尽きないところでございますが、慶應義塾大学の先輩後輩という…
西山:本当に大先輩で!
司会:社長からご覧になったら、頼もしい後輩が育っているなと感じが…?
伊佐:頼もしいどころじゃないですよ。鞄持ちをしたいなと思います。
西山:そんな…恐縮です!
司会:また、お二人の関係の中で、きっとたくさんの足し算が出来るのではないかなと、お話聞きながら期待が膨らみました。あっという間に、すみません、お時間になってしまいました。
伊佐:もう終わりですか?
西山:もう終わっちゃう。
司会:今月の「わたし歳時記」のゲスト、4週に渡りまして、東京都市大学 准教授 西山敏樹さんにお話を伺いました。また、今日は伊佐ホームズの伊佐裕社長にもお話をお聞きしました。お二人、ありがとうございました。
西山・伊佐:ありがとうございました。
伊庭保さん

司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、SONYで日本企業初のCFOに就任していらっしゃいました伊庭保さんです。どうぞよろしくお願い致します。
伊庭:よろしく。
司会:伊庭さんは1935年世田谷区下北沢で生まれ、育ちました。東京大学法学部卒業後、1959年にSONYに入社。そして1995年に初のCFO・最高財務責任者に就任し、SONYの一時代を率いていらっしゃいました。そして5週目の今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきます。どうぞよろしくお願い致します。
伊佐:よろしくお願いします。
司会:まずはお二人の出会いからお聞きしてもよろしいですか?
伊佐:じゃあ私のほうから。ちょうど私の友人で、SONYにいた人間がいましてね。その田中君という友人からですね、伊庭さんのご自宅の件のご相談いただきまして。喜んで私どもで仕事をさせていただいて、今お住まいになっているということで。当初、私、これだけの事業をやってこられた企業人でおられたのですね、本当に仰ぎ見る思いでお近づきになったのですがね。今回の放送でも、わかりますように、お人柄がこのように春風のごとく接していただいて、大変お近づきにならして頂いたなと思って。また4回分の放送を聞いておりまして、初めの入社の動機は、ある面じゃ受け身でおられた。そしていろいろなSONYの成長に応じて、伊庭さんが場所を作られて。大事な役割を、後ろ側から攻めの体制を作ってこられたなというのをまざまざと知りましてですね。なんとお幸せな人生・企業人でおられたかなと思いますし。それとSONYという会社の凄みをですね、まざまざと今回4回分お聞きしてですね。私先般、上高地に行きましてね、山を見ていたのですよ。穂高の連峰があるわけですよ。奥穂高とか、前穂高とか、西穂高とか。やっぱり山岳というのはいろいろな峰々が、こう頂上と重なり合って、美しい風景を作っているのですよ。そういう点で、井深さん、盛田さん、そしてそのもとに伊庭さんのような方がいらっしゃる。あと何人かまたそういう方がいらっしゃると思うのですけど。企業というのはですね、人の力の結集。その前に志でしょうかね。それを本当まさに4回、感じさせていただいてですね。家づくりを通して、こういうお話をお聞きできるというのは、幸せこの上ないですよ。
司会:伊庭さん今の(お話)は(どう感じられますか)…?
伊庭:どうもありがとうございます
伊佐:私はですね、ここのギャラリーは、出光商会から土地を買ったのですよ。で、私は、出身が福岡ですから、出光佐三さんの人生には大変敬服しておって。国家観であるとか、経営観とか、美意識とか。私も奇しくもそういう場所で、こうやって事業をやっていますのでですね、そしてこうやって今伊庭さんとお会いして。私も創業以来32年、私の場合は本当に低山でございますけど、低いながらですね、美しい形の山として企業をやっていきたいなというふうに思います。
伊庭:伊佐さんに仕事をお願いするようになったのも、まったく人のつながりの偶然。偶然のあれで。名前が出た、田中じゅんというのは、SONYで一時私の部下なんかもやっていて。今はもう辞めて、奥様の実家が不動産屋をやっているので、不動産屋の社長をやると。で、伊佐さんと慶應の山岳部とかね、そういう繋がりで。よく、今でも山にはよく登っているし。なかなか優雅だと思うのは、山の上でお茶をたてたりとか。
伊佐:そうですね、また絵も描きますよね、彼は。山の絵を描きますね。
伊庭:えぇ。そうですね。水彩なんか、なかなかいい絵を描きますね。
司会:共通点で山というのも出てまいりしたね、今ね。
伊庭:そうなのですよね。会社に入ってから、山行くのは本当に少なくなっちゃったのですけれども。元気な頃というか、90年代の頃は、全然計画なしにね、毎週土曜か日曜はね、高尾山へ気が向いたら行って。高尾山の頂上でおにぎりを食べて帰ってくるという。毎週のようにやっていたし。会社は五反田にあったのですけど、自転車で会社に行ってみたりとかね。で、その頃はね、体を動かすことが好きで。今は足を痛めちゃったからあんまり出来なくなっちゃたんですけど。やっぱり山を愛する男というのは、なんか共通するものがあって。付き合っても気持ちがいい。
伊佐:あとはお酒ですか?
伊庭:お酒ね(笑)
伊佐:山好きはお酒が好きですね、だいたい。だいたいセットされていますね、それは。
司会:あとは、おふたりともご本がお好きでいらっしゃいますよね。
伊佐:どんな本が多いのですか、伊庭さんが読まれているのは?
伊庭:雑学ですね。あの…
伊佐:歴史ものとか?
伊庭:えぇ、歴史ものも読みますし。最近の読み方は、もう本屋行って探すのが面倒くさくなったので、書評を見てね。で、面白そうなのを。最近読んで面白かったのは「ファクトフルネス」ね。あのー、世の中に溢れている情報というのはね、よく用心してみないと偽情報が混じっているって。書いたのはアメリカ人かな、なんかの女性も加わっていて。彼女がこの前日本に来て、講演会なんかもやっていましたけどね。だからアメリカは、トランプ大統領をめぐるフェイクニュースの話があるのですけども、本当に、事実というのはこんなにSNSが発達しちゃって、情報が過多になってくると、何が本当だかわからなくなっちゃうので、読む人が判断しなきゃならないけど、それも大変なことだし。こういうSNSの世界が発展すると、一体どうなっちゃうのだろうかっていうね。
伊佐:なるほどね。
司会:そういうふうに時代をしっかりとつかまえていらっしゃるというか。時代に沿っていろいろ目を光らせていらっしゃるのですねぇ。
伊庭:というか、まぁそれも好奇心ですね。
司会:あぁ、なるほど。
伊佐:じゃああらゆるジャンルに目がいかれていますよね。
伊庭:だから、高校生の頃読んで、感銘を受けたのは、中勘助の「銀の匙」とかね、それは先生に薦められて。それから、青春時代は「若きウェルテルの悩み」とかね、そういうあたりから始まって、司馬遼太郎も大好きだし。それから、吉村…。
伊佐:昭?
伊庭:昭!吉村昭の本もいいし。
伊佐:いいですね~。史実だけを追求していってドラマが出来るというのは、吉村昭というのは凄いなと思いますよね。装飾がないですよね。事実だけで大きな装飾が出来るというか、物語が出来る。
伊庭:吉村昭の息子がSONYに勤めているのですよ。で、文才は、親父さんの引き継いでいるまではないけれど、片鱗はありますね。
伊佐:そうですか。
伊庭さん、私、本ですとね、近頃、露伴、幸田露伴の渋さというか、味深さというのに非常に惹かれましてね。さっきおっしゃった真実の問題。何が真実かという、こう、両極といいますかね。努力論という文章が好きでしてね…。
司会:なんかご本の話になると、お二人どうも話が尽きないような気がいたしまして。もしかしたら今夜あたり、どこかでお二人が語り合っている姿をどなたかご覧になるかも…(笑)
伊佐:そうですね、盃を交わして、本のお話をまたお聞きしたいですよね。
司会:すみません、放送のほうはもうあっという間にお時間になってしまいまして。まだまだお聞きしたいところなのですが…。
伊佐:是非、どこかでまたお願いしたいですね、それは。
司会:是非。お願いしたいと思います。「わたし歳時記」今月のゲストSONYで日本企業初のCFOに就任していらっしゃいました伊庭保さん。そして、今週は伊佐ホームズの伊佐裕社長にもお話していただきました。お二方、どうもありがとうございました。
伊庭・伊佐:ありがとうございました。
瀧良三さん

司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、慶應義塾大学・登高会 会長 瀧良三さんです。よろしくお願い致します。
瀧良:よろしくお願いします。
司会:慶應義塾大学山岳部のOB会・登高会の会長を、瀧さん3年前からお務めでいらっしゃいます。今月、登山の魅力、たくさんお聞かせいただいておりますが、4週目の今日は、やはり山登りも楽しんでいらっしゃる、伊佐ホームズの佐裕社長にも加わっていただきます。どうぞよろしくお願い致します。
伊佐:はい、お願いします。
司会:社長と瀧さんはかなり関係が深い…?
伊佐:はい。じゃあ私から。私、前の会社、丸紅というところなのですが、今から44年前に、瀧さんとその独身寮で一緒だったのですね。瀧さんは私の3年上で、政務部にいらっしゃった。私は都市開発にいまして。まぁ、寮での出会いがなかったら、いくら同じ会社でも(出会いが)なかったと思うのですが。また寮の中でも、大変瀧さんは人徳があって、皆に慕われるお人柄でしたよ。いつも悠々とされていましてね。で、寮は予定がない人間たちはね、土曜日曜はゴロゴロとしているのですよ。行くところがないのでね。瀧さんもね、大変かっこいい美青年でしたよ。しかし、土日いるのですよ、寮に。で、そういう人間たちがラグビーをやっていたのですよ。で、ちょうどその頃、瀧さんはラグビー部のキャプテンでですね。私も運動が好きですから、ラグビー、まだ浅かったのですが、瀧さんと一緒にラグビーさせてもらって。まぁ、ひどいものでしてね、ガラクタチームは。その日になってもメンバーが揃わないのですよ。それで寮のアナウンスをしましてね、私が、皆に。今日試合があるのだと。ぜひ出てくれということで、名前を指名しましてね。何時までにロビーに降りてくれということで。それで、水泳部とかですね、野球部の人間とかね、集めましてね。試合、瀧さんを中心にいくわけですよ。
司会:かなりキャプテンの瀧さんはご苦労がおありでしたでしょうね。
瀧良:いやー、まずメンバーをそろえるのが大変でしたね。(笑)
伊佐:終わったら餃子がつくとかですね、ビールがつくとかですね、そんなことで。楽しい独身時代でしたね。
瀧良:そうですね。
伊佐:で、その頃から瀧さんが、なんでしょう、山というのは聞いていたのですがね。私その後丸紅を去って、もう31年になりますがね。だんだん瀧さんという人物に対する関心が高まるというか。その後も何度かお会いするうちにですね、やはり山岳部って。私は山が今好きなのですが、とても瀧さんの山とはケタが違いますけどね。あれだけの慶應の山岳部というのは歴史があるし、そういうところの長を務めて。大変な忍耐の時間を4年間過ごされた方。そのあと、丸紅でのお姿を見ても、非常に恬淡としたお仕事ぶりなのですね。私から見たら、そういう山岳家の人生とですね、その社会人の人生の、どういう兼ね合いがあるのかなという気が、仁もこの年になりますとありましてね。今回、山の魅力とともに瀧さんの人生を知りたいなというのが私の狙いだったのですよ。
司会:その伊佐社長が思っていたイメージというのは、瀧さんはどんなふうにお感じになりますか?
瀧良:いやー面映くって、むずむずしているのですけど(笑)とてもとてもそんな人間ではありません。伊佐社長は、非常に豪快といいますかね。山はお互い好きだということもあるのですが、共通点は他にもあって。特に日本酒、居酒屋が好きだということで。しかも自由が丘にある居酒屋がですね、お互い、実は共通のおなじみの店だということがわかりまして、そこで時々は一緒に呑んでいますが。非常に、なかなか豪快ないい人間だなというふうに思っています。
司会:じゃあ、社長は今回3週聞いて新たな魅力を…?
伊佐:あぁ、魅力、もちろんです。瀧さんね、私は絵を描いていましたので、大学時代も北アルプスをふもとから描いていたのですね。月に1回写生に行ってましたので、だいたい行けば1週間山を描いているというか。安曇野から見る北アルプスとかですね、白馬だとかですね、妙高とか。で、だんだん私そのあと、山岳家のいろいろなエッセイが好きになったのですね。山岳家って非常に名文家が多いのですよ。それに惹かれてまた山のほうに浸るような思いがありました、人生の中で。その後、私は建築の会社を興したのはご存知ですけれども。そのあとやはり森の問題とか、林業の問題とかに取り組みだして、余計また山に入ってきて。で、自然界というのは不自然なものがひとつもないのですよね。どれみても不自然なものがないのですよ。我々は建築をやっていましてね、不自然な線が無いようにしたいなという。美しいものには不自然さがないのですよ。そういう点では目を鍛えるには、私自然を見るというのは非常にいいなと思うのですよ。非常に熱心な人間たちは現代建築の作品をよく見ているようですが、私それ以上に自然の景観に触れるというのは、目を鍛えると思うのですね。どこにひとつたりとも同じものはないわけですから、自然界というのは。さまざまな林の中でも、山の地形でも、沢でも、高原でも、見事に点在していますよね。渓谷でも。そうして山に行って帰ってくると、非常に自分の心の自然さと目がまた洗われてくるというか。そうしたら仕事に行っても、なんとなくね、設計図に違いが見えるというかな。私、山の効用がそんなところでもありましてね。それとやはり、豊かな森は大変素晴らしいし、我々の生命の根源に還るようなところがあるというような学者さんも言っているようですけれども。森というのはそういうことのようなのですよね。瀧さんは非常に山岳として、山を極めてこられた。私は見ながら絵を描いたりして、だんだんに仕事柄山に近づいてきたという…。そんなことでさ、こういう話しながらまた酒を飲めるといいですよね、居酒屋で(笑)
司会:今のお話はやっぱり瀧さんも同じようなことを感じられることおありですか?
瀧良:そうですね。日本ほど、これだけ緑が多くて、山も川も本当にすぐ近くにあるような国は珍しいと思うのですね。その自然を十分に楽しんでいけるのは幸せだなというふうに思っています。
伊佐:そうですね。日本は島国だから、非常に植生が豊かだそうですね。世界的にも珍しいようですね、生物の生態系の抱負さには。いや~一度、瀧さん御供させて下さい、山に。
司会:じゃあどうでしょう?瀧さん、社長と一緒だったらどのへんに、って今お考え浮かびますか?
瀧良:さぁ~、どこでしょう?むしろ伊佐さんのほうが最近はよくご存じだから、伊佐さんの後ろにくっついていこうかな(笑)
伊佐:いや、とんでもないですよ。でも私は、平坦地をずっと歩くのも好きなのですよね。昔の道を、街道を歩くというかな。やっぱり歩くとだんだんだんだん、自分がなくなっていきながら、自分があるというか。瀧さんそういうとこでしょう?自分がなくなるのだけど、自分があるという感じありませんか?
瀧良:うん、うん、うん、うん。難しいこと言うね~。(笑)なんとなくわかるような気がする。
司会:自然の中に溶け込むというか、一体感ですか?
伊佐:そうですね。邪魔な自分がなくなっていくというか、だんだん大事なとこだけ残ってくるというかな。そんな作用があるような気がしますよね。去年のね、連休に、八ヶ岳の白樺の池に行ったのですよ。ちょうど雪が降って来ましてね、連休で。これはちょっと装備がないのでね、そこからもう山をあきらめて下ったのですよ。その時は、小海線の八千穂の駅まで歩いたのですよ。これが、水平距離で26キロ。標高差が2000弱から800ですか、八千穂が。だから1000メートルちょっとくらいの標高差を下って、水平距離26キロ行きますとね、もう様子が全部違うのですよ。上は雪が降っている、下がまた芽が吹いていない白樺がある、次にちょっと芽が出た、その下が今度もう新緑、その下が、桜が咲いているというかな…。それがまた頂上に行けなかった、また山の楽しみというかな。楽しいですね。いろいろなところで楽しみが見つけられるというか。
司会:瀧さんご自身にも、頂上目指して行けなかったというようなご経験はおありですか?
瀧良:あります。特に冬の穂高なんかは途中であきらめて帰ってきたことがありますし。
司会:今の社長のお話は、同じように感じたことはおありですか?
瀧良:特にね、春の山は頂上のほうは冬と同じで、雪が凄い積もっているのですけど、下山してくるにつれて、ジャンパーを脱いで、セーターを脱いで、だんだん緑が増えて来て。下につくと、もう本当に春の…
伊佐:ひばりが鳴いていたりしてね。
瀧良:この季節の移り変わりをほんの数時間で体験できるというのは素晴らしい!大好きですね。
伊佐:小川の水の水量が多いですよね。雪解けの水が。水がはしっているというかな、あれがわかりますよね。
司会:日本の美しさを実感できるという時ですね。
瀧良:そうですね。
司会:なんかすごい羨ましくなって、私も高尾くらいに登ろうかな…(笑)
伊佐:やりますか?やりましょうか、ご一緒に。
司会:ここは経験者と一緒に行かなくても大丈夫ですか?
瀧良:大丈夫です。
司会:なんかたぶんリスナーの方の中にも「ちょっと登ってみようかな」という思いが、今増えてきている方がいらっしゃるのではないかなと思います。ひとことだけ、なにかお二人からメッセージ的なことがあったらいただいてもいいですか?
瀧良:いっぱいいろんな山がありますから、前にも申し上げましたけど、経験豊かな方と一緒に行って是非山の楽しみを体験していただくといいかなというふうに思います。
伊佐:あの当社では、森との取組みやっていましてね、植林をやっております。そういう点で、是非都会の方が、森の楽しさを知ってですね、植林の喜びを持っていただくとありがたいなと思います。
司会:ありがとうございました。「わたし歳時記」今月のゲスト慶應義塾大学・登高会 会長 瀧良三さん、そして、今週は伊佐ホームズの伊佐裕社長にもご一緒していただきました。ありがとうございました。
瀧良・伊佐:ありがとうございました。
西野文貴さん

司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、森づくりアドバイザー・西野文貴さんです。どうぞよろしくお願い致します。
西野:よろしくお願いします。
司会:西野さんは、1987年大分県のご出身。東京農業大学で植物社会学と植生景観について学び、現在も大学院の博士課程後期課程に在籍でいらっしゃいます。そして日本の森づくりのために精力的に活動していらっしゃいます。また今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただいてお話を進めたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
伊佐:お願い致します。
司会:実はお二人、九州男児という共通点がおありなのですよね。
西野 ・ 伊佐:そうみたいですね
司会:で、4月のゲストの瀬田玉川神社の高橋禰宜のご紹介で知り合われたということなのですが、ゆっくりお話されるのは今日が初めて…?
伊佐:いやいや、私はね、その前に西野さんが書かれた「皇居の自然は日本人の心」という文章にいたく惹かれましてね。お会いしたいなと思っていたのですよ。皇居の中の植生調査ですか。調査の結果、711種の植物、2737種の動物、合わせて3448種が確認されたと、いう驚愕するような数字を知りましてね。ああいう都会の中に、これが、こういう生態系が存続しているということが、まさに日本の宝物の象徴かなというふうに思ったのですよ。私はね、お会いしたいと思っていたら、こんな思いが出来たのでね。
西野:わぁ、嬉しいですね~。
伊佐:私も3回お話を聞きましてね、勉強の醍醐味というか、まさにね、学ぶことが喜びというか。私も勉強しなかったのでね~、そういう気持ちで勉強すればよかったなと思ってね。
西野:いやいやいやいやいや!
伊佐:僕はペーパーでね、紙の上でそういうことを学んだのでね。現場に来ながら、こう発見する喜び、それを分類していく、そしてその歴史を知っていくというのを。これがまさに教育の醍醐味かなと思って。もう感心して聞いておりました。
西野:いやいや、ありがとうございます。
伊佐:あの、私はですね、18歳の時にお寺で3カ月生活したのですよ。標高700メートルの、熊本の山の中でしたよ、お寺。これ、電気もガスも水道もなくて、水も山水なのですよ。で、日の出とともに起きて、日が暮れてからろうそくの灯で食事をして、9時に就寝と。で、トイレに行くのもろうそくを持っていくような。で、そういう3カ月をしますとね、人間にとって、情報が何かとか。何が大事か、人間が生きてゆくのに。情報というのは、私はもう要らないなと。えぇ、本当に。で、私は何かあったらこの山に帰ってこようと思っていたのです。都会に出て降りて、何かあったらこの山に帰ってこようと。ここに変えれば必ず復元できる、自分を、って。僕はなんか、18の時にね、確信がありましてね。少し自然への目覚めがここであったのですよ。
あとは、それと私は昆虫少年だったのでね。
西野:あぁ~。はい、以前の話をちょっとお伺いしていると。ラジオを聞いていると、そうですよね。
伊佐:あの櫟の樹液のところに集まる、あの昆虫の宇宙はね、もう震えましたね。
西野:以前のラジオの内容で、昆虫を集める量がですね、凄いなって。
伊佐:まぁ、量だけでね(笑)
西野:いやいや、凄いなぁと思いましたね。1日で100匹とか集めていたというお話をお聞きしてたのですけど。
伊佐:まぁ、そんなことの経験の中で、今住宅づくりをやっているわけですがね。やっぱり新建材と天然の無垢材の存在感が違うのでね。私は高級とかじゃなくて、やっぱり本物に触れていく力。自然と同じように。自然の中の産物が木材であり、そして生活空間があるという、そういうことを作って表現したいなというのが今の仕事なのですよ。その中に日本人の美しいと思う衣装といいますかな、日本のデザインを入れていきたいと思ったりして。そうしているうちに、木の根源である森、林業が大変な状態だということで、近頃はすごく森とのつながりが深くなってきて。そしてそれを回復するために、今植樹をやっていくと。そういうことに目覚めたからこそ、西野さんの文章に私は出会ったと思うのです。
西野:いやー、ありがとうございます。
伊佐:もしね、目覚めてなかったらこの文章を素通りしていると思うのですよ。たぶんお会いする機会もなかったと思います。人間って、意外と意識がないと、それを見る必要がないですからね。そのおかげでお会いできて。まぁ3回(番組を)お聞きしてですね、これからもぜひご一緒にね、ご指導を頂いて、森とのつながりの、我々建築をやっていきたいと思いますのでね。
西野:いや~、僕のほうこそお願いするところですね。
伊佐:頼もしい、本当に。若き先生がいらっしゃるなっていう。
西野:是非、よろしくお願いします。
司会:西野さんは、今の社長のお話聞いてどんなふうに感じられました?
西野:そうですね。あの~、3カ月実際にお寺で過ごされたというところで、感覚が研ぎすまされたというお話はですね、それたぶんやっぱり原点、生き物として原点に返ったということですよね。ただ単純に情報だけ、ごちゃごちゃ入っている、その人間社会で生きていくためではなくて、いったん生物社会の中の一員として、その3か月間は自分を見つめなおす時期だったのかな、と。そこで研ぎ澄まされたセンスとか感覚が、たぶん今行われているものに、すべてにたぶん反映しているのだろうな という。だからその辺に関しては、もう学ぶことが今日たくさんあったなというか、思っていますね。
伊佐:今のお寺の住職、こういいますよね。非常に心身疲れた人間が、お寺で雑巾がけをすると回復すると言われているのですね。これは、人間が立ちあがって頭を使いすぎると。重力にこう背いて立っている…
司会:逆らって立っていると。なるほど。
伊佐:だからもう一回、爬虫類を回復するというのが掃除だと言われていますよね。禅の中では。禅に限らず、お寺さんではそうだと。爬虫類のというか、もっと根源の生命力というか。今おっしゃったことは、少しそういうことにも繋がるかもしれませんね。
西野:いや~、それで今秩父で行われている森づくり、いわゆる植樹もですね、あれも木を植えた瞬間というのは、植える瞬間というのは、僕いつも思うのですけど、性別とか国境とか全部超えちゃうのですよね。やっぱ人間の中で、次の命を植えて、っていうその循環的な行動をすると、なんかいつも気持ちが最後みんな笑顔になって帰っていくのですけど。
伊佐:確かにそうね。山に行くとそうなんですよね。本当にそう!
西野:それをなんか今日共感できるなという部分を凄い感じていますね。
伊佐:それと私は、1年間に30回山登りしているのでですね。
西野:おぉ!素晴らしい。
伊佐:いろいろな森を見るわけで。やっぱり健在な森だとかは美しいし、清々しいですよね。
西野:そうですね。まさしく。
伊佐:出来れば、針葉樹林よりは広葉樹林とか、非常にやっぱり豊かだなと思って
西野:いや、本当、これから先、少子高齢とかいろいろな問題がたぶん出てくると思うのですけども、それをうまくいろいろな産業を形にだんだんしていってですね、(それが)出来るような気が、なんか今日は凄い、そういう感じがしていますね。まさしく今おっしゃられた広葉樹の使い方というのも、これからたぶんもっと出てくると思うのですよ。
伊佐:そしたら是非お願いしたいのですよ。我々は針葉樹を切った後、楓を植えているのですよ。混交樹林にしていこうということで。そして楓からメイプルの生産もうちでやっているわけなのですがね。それに限らず、いろいろな自然の資源を我々が大事にして活用するという。そして山が生活を維持できるということを我々支えたいと思っていますね。
西野:まさしくそうですね。今日そういう意味もあってですね、この黒文字、大葉黒文字をですね、実は持ってきて。さきほどちょっと匂いを(収録の)間に嗅いでいただいたのですけども、芳香・匂い、いい匂いしますし。やっぱりこれも今精油として、芳香剤としても採られているくらいなので、そういう意味では、これから先、針葉樹だけでない、混交林で副産物が何か新たに取れて、なにかひとつの経済が回ることが出来れば…。
伊佐:それは期待したいですね。
西野:そういうふうな世の中にしたいというふうには思いますね。
司会:今お聞きしていると、お二人の協力で もっともっと広い世界になりそうなという…
伊佐:本当にそう、お願いしたいですね。
西野:それがやっぱり、今までなかった化学反応だと思うのですね。普通はなかなか出会わないものが、いろいろな、今回は本、「明日への選択」という本の、雑誌の媒体であったりだとか。それがもしくは、形が違っていればフェイスブックで繋がっていたかもしれないですし。でも、何かしらたぶんですね、僕は伊佐社長とはご縁があってどこかで繋がると。で、今日は出会うべく時に出会ったのかなと、いうふうに今日は感慨深いですね。
司会:私、素敵な瞬間に立ち会えたなというか。
西野:その通りだと思います。僕も今日感動を凄い味わっていますね。
司会:それぞれの世界が広がりそうですね。お互いに。
伊佐:そうですね。我々は目の前のことをやっているのだけれど、西野さんは体系的に世界を見てらっしゃるのでね、繋がるようにやっていきたいなと思いますよね。
西野:今日の午前中に瀬田の住宅を見させていただいたのですけども。たぶんもっと使える在来種、広葉樹、いわゆるシンボルツリーでもなんでもですね、たぶんこれからもっと出てきそうだなと。で、それを発見する、その研ぎ澄まされたセンスをお持ちの伊佐社長さんは、たぶんこれからそういうのを見つけて、「これ、新しいあれだ」とかやってきそうな、そんな予感もちょっと感じるような内容しましたね。
伊佐:うちは雑木で、特に櫟とか楢が多いのですけどね。冬時期は、葉をつけて冬を越すやつがありますよね。雪が積もってもね、雨が降っても、冷たい雨が降っても、葉がついている。そして新芽が出て来て落ちるという。必要なくなると落葉するわけですよね。だから我々人間の生も、もしかしたらそういうことで、終われば、お務めが終われば、終わると。いうことは、終わりじゃないというふうにも考えたいと思いますしね。
西野:で、一番これから先のキーワードになるのが「循環」かなと思いますね。いわゆる、その落ちた葉っぱがただのゴミじゃなくて、一つの土の資源になったりとか。いろいろなもの、次の命が次の命に繋がるというようなことがだんだんまた、これから先、令和の時代に入って見直されていければいいなというふうに思いますね。
司会:お二人のお話、本当に尽きないところではあるのですが、あっという間にもうお時間になってしまいました。
西野:もう終わり、早いですね。
司会:私もまだまだ聞いていたいところなのですけども、また改めてお話聞きたいなとも思っております。
西野:是非。
司会:今月4週に渡って、森づくりアドバイザーの西野文貴さんにお話いただきました。楽しいお話ありがとうございました。
西野:ありがとうございました。
司会:そして、今日は伊佐ホームズ・伊佐裕社長にもご一緒いただきました。ありがとうございました。
西野・伊佐:ありがとうございました。
東浦亮典さん
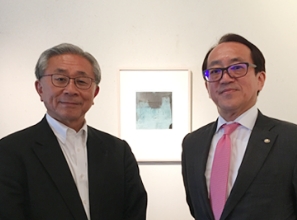
司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、東京急行電鉄執行役員・東浦亮典さんです。よろしくお願い致します。
東浦:よろしくお願いします。
司会:そして、今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきます。よろしくお願い致します。
伊佐:はい、よろしくお願いします。
司会:伊佐社長、先週まで3週、東浦さんのお話お聞きになって、どんなふうに感じられましたか?
伊佐:もう3回お聞きしましてね。鷺沼の少年時代に、きっとその頃デベロッパーの風景が見えたのかなと。やっぱりね、地形がまずあのへんは斜面。それが変わっていく、形状が。あるいはブルドーザーの動きだとか。で、その頃就職にあたって、あまり意識がなかったとおっしゃっていたのですがね。僕は1回目を聴きましてね、やっぱり少年の頃に鮮やかな映像があったなというふうに思いました。それから私もそうですが、私もね、東浦さん。まさに東浦さんがやってこられたような仕事を丸紅で10年間やっておりましたよ。ただ商社なのでね、やっぱり金融がベースなので、専門業界じゃないので、儲ければいいという思想が強いのですよ。だから街づくりのスパンが短い。そういう点で私は、そのころから東急さんの事業性、事業への広大なる、先を読んだお仕事ぶりは、凄いなというふうに思っていましたし。それと街だけでなく、サービス業とか、さまざまなことの視野、立体産業。その中で鉄道が走っているという。その海を東浦さんがどんどん拓いて、今まさに東急の精神を具現化されてきたなというのが、南町田の問題、(二子玉川)ライズのこの変容。で、渋谷がどんなに成長するかというのはねぇ。3回目でおっしゃったように、世界の主要都市を意識されていると。我々どうしても、東京の中のマーケットをみるのだけど、先を見ている。それはやっぱり私は、オーナー企業の、特に二代目の五島昇さんのビジョン、があっただろうなと思って。それが非常に遺伝子として残っておられる。それが、私から見ると、東浦さん偉い方なのだけど、鷺沼の少年に種が落ちて、それが東急のこのまた幹になって。これはまさに東急の幹が東浦さんですよ。まぁ広い、範囲が!
司会:今の伊佐社長の感想っていうのは、東浦さんどんなふうにお聞きになりましたか?
東浦:いや、過分なご評価で…。
伊佐:とんでもない!とんでもない!とんでもない!
東浦:そうですね、今おっしゃったように五島昇というお話があったのですけど。五島昇という大変偉大な経営者はですね、平成の元年に亡くなっているのですね。で、私は昭和60年入社でしたので、五島昇という方にお会いしたのは、入社前の面接の時、それから入社式の時、それから亡くなる直前でかなり体が弱られた時の3回しかお会いしていないのですね。だから、直接薫陶を受けたわけでもないのですが。その後ご存知のように、バブルが崩壊しまして、東急グループも非常に経営が厳しかった時代が長く続いたわけですね。その時に今伊佐社長のおっしゃっていただいたような精神を、一時忘れかけたんじゃないかという時代があったように思うのですね。私は、東急が他の企業グループと違うのは、長期的な視座とですね、沿線というところを支える責任とかですね。それから生活文化を作っていくというですね、こういったところを忘れたら、たぶんうちの存在意義ってもうないだろうなと思っていて。ちょっと一時期、儲けだ、儲けだということでですね。その精神が忘れられていたときがあったのですが。昨年、実は五島昇さんより源流になるのが、渋沢栄一さん。今一万円札で話題になっていますけれども。あの渋沢栄一さんが、やっぱり東京にも、日本にもですね、そういう計画的な衛星都市が必要だというので作った会社が源流なのでね。
伊佐:田園都市株式会社ですよね?
東浦:そこから100周年がちょうど昨年だったのですね。そういうことに鑑みるとですね、もう一回原点に戻ろうよという時代に今なっていると思うのですね。
司会:そして、新しい令和という年を迎えているので、凄い流れを感じますね。
伊佐:私もずっと学生時代から東急沿線に住んでいましてね。本当に気持ちがいいのですよ。たぶんね、すべてはね、どんな人が住んでいるか。どんな感情で生きているか、その街で。それが大きいかなと思って。不快な思いがないですよね。
東浦:やはり、先人たちが長期的にいい街づくりをしてきていただいたことによってですね、いいお客様が住んで頂いた。そのいいお客様から、また新たな生活文化とか、経済とかがまわって、また沿線が活性化する。こういうサイクルがもう出来てきているのじゃないかと思いますね。
伊佐:私も鷺沼に住んでいましたし、今は奥沢なのですがね。まさにどこに行っても気持ちがいい街で。これはね、気持ちがいいというのが一番の価値かなと思いますね。
司会:そうですね。もともとの基本のところには、イギリスの都市計画があったということですよね?
東浦:あのエベネザー・ハワードという方がですね、ロンドンが産業革命で、中心街が非常に非衛生で猥雑な状況になったときにですね。ここでは人の住むところではない ということでですね、ロンドンから北に55kmいったところ、レッチワースというところに、理想のガーデンシティを作ろうと。これが世界的に当時受けまして。日本では主に私鉄各社が移入したのですね。阪急の小林一三さんとか、渋沢栄一さんがこれを日本に作ろうということで出来たのが、我々の会社の源流ですので。
伊佐:日本株式会社の元祖が渋沢栄一さんですから。街づくりも同じように、長い視野で仕事が出来てきたと。そこに東浦さんがこうやって入られて、成し遂げられたと。 これからまたされていくということが本当に楽しみですな。
司会:伊佐ホームズさんでもおそらく東急沿線では、家づくりたくさん手がけていらっしゃるんじゃないかと思うのですが。
伊佐:当社のお客様の53%が世田谷区のお客様になっています。思い返しますとね、私、昭和63年の4月に二子玉川の駅に降りて、今の会社を作る準備を始めたのですよ。その頃は田舎の駅なのですよ。駅を降りたらね、人もいないのですよ。あの頃ね、駅のロータリーに氷屋さんがありましたね。玉川製氷という氷屋さん。これが思い出が深いですね。で、人が通ってなくてね、お店も焼鳥屋さんが一軒あったかなぁ。酒屋さんのお店があったりして。まさに昼は閑散とした街でしてね。
東浦:ちょっと田舎の駅みたいでしたよね。
伊佐:田舎の駅でした。
司会:今の、では二子玉川は想像できないですよね。
東浦:あぁ、まったく想像できないと思いますね。
伊佐:本当にそういうところで私も仕事を始めた幸せを感じますよ。
司会:これから家づくりということで、また関係が深まっているのではないかと思うのですが、共通の思いみたいなもの、もしお聞かせいただけたらと思うのですけれど。
伊佐:そうですね。私は、森を育てる家づくりということをこの5年やっていましてね。やはり環境があって、我々の生命があるわけですから。そういう点で、ただ儲かるのではなくて、そういう森林の自然資本と、社会的資本と合流させてですね、事業を成立させるというのが私の理念でしてね。我々住宅会社が、山と直接取り組むと。そして山に植林をしたり、生態系を守る活動を今やっていましてね。
東浦:素晴らしいですね。
伊佐:えぇ。これは大変今林野庁からも期待されたり、国からも期待されていましてね。東急さんの沿線でも、池上線はかなり木を使った駅舎になっておられて、素晴らしいなと思っていますね。それと東急さんはBunkamuraだったり、木造化の問題とかですね、非常に時代を感じられるお仕事をされていくなと思いますよね。渋谷が目立ちますけれども、さまざまなところに、時代を切り拓いていく会社だなと思いますね。
司会:伊佐ホームズさんの取組みというようなことは、東急にとっても、とても大きな力になると思うのですが、東浦さんいかがですか?
東浦:そうですね。やはり今社長がおっしゃったように、家という、見えている、目の前に見えているものじゃなくて、その奥にあるものとか、全部つなげて考えられている発想って素晴らしいなと思ったのですけど。私ももうちょっと若い頃はですね、前週までにお話したのですけれども、街づくりをするのだ。それは、最初若いころ見ていたのは、フィジカルなもの、目に見えるもの、物理的なものを変えていくのだということを仕事だと思っていたのですが。最近50も超えてくるとですね、ちょっと偉そうな言い方をすると、社会システムを変えていくことを仕事にしていきたいと思いまして。
伊佐:私も全く同感ですな。
東浦:やはり、今日本はいろいろな課題を抱えていて。高齢化の問題とか、あと都市が縮退してきて、今小さくなっているのですけども。こういった中で、高度経済成長、右肩上がりの時のやり方ではない社会システムに変えていかなければいけないのですが、そこにまだ日本は追いつていないなと思っていまして。まぁ、偉そうな言い方をするのですけど、私はハードな街づくりだけでなくて、社会のシステム、人の生活のパターンとか、そういうものを変えていく仕事をしていきたいなと。
伊佐:そうですね。
司会:あぁ、同じ思いだなというような…
伊佐:全く同感ですね。新しいビジネスが、新しい形が生まれていく。
東浦:そうですね。
伊佐:そのためには技術革新があったりしていくと思いますので。
司会:今後ますますお二人の関わりが深まっていくような感じがいたしました。
伊佐:いやぁ、いいお話ですね、最後に。
司会:「わたし歳時記」今月のゲスト、東京急行電鉄執行役員・東浦亮典さん、そして、伊佐ホームズの伊佐裕社長にもお話いただきました。ありがとうございました。
東浦・伊佐:ありがとうございました。
高橋知明さん
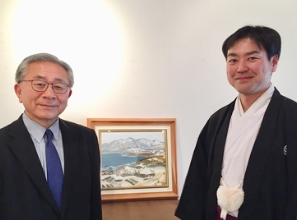
司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、瀬田玉川神社禰宜・高橋知明さんです。よろしくお願いいたします。
高橋:よろしくお願いいたします。
司会:そして、今週は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
伊佐:はい、よろしくお願いします。
司会:伊佐ホームズの本社、瀬田にあります。 同じ街どうしということで、おふたりはかねてからお付き合いがおありだったようですね?
伊佐:はい、親しくなりましたのはこの10年近くなのですが、以前より瀬田玉川神社さんは、私どもの氏神様なので随分お世話になっています。約31年間ということですから、お付き合いは。
司会:あの、お二人知り合われてからはどんなふうに関わられているのですか?
伊佐:共通の友人がいましてね。私はその友人を大変尊敬しておりました。その友人がこの髙橋さん、高橋禰宜さんと大変また親しくて。それだけで急速に近づきましたね。 なんでしょうね、人間というのは回数を重ねるのではなくて、親しくなる時は一気に親しくなるというかな。まさにその通りのご人物でしてね。今毎月私が拝読しています雑誌への寄稿もされておりましてね。まさに見事な文章。外国人から見た日本の姿を毎月連載されていまして。そういう勉強もされている禰宜さんですよ。そしてまた森の活動が凄いですよね。
高橋:あぁ、そうですね。
司会:森の活動、というのは、この前もちょっと先週お話しいただきましたけれども、具体的にはどんなことをなさっているのですか?
高橋:はい。東日本大震災から8年ということですけれども、私の実家が陸前高田ということもあったのですが。当時は神社本庁にいたのですけれども、その翌年から被災地に津波除けのための森の防潮堤を作ろうというプロジェクトが始まりまして。これは、細川護熙元首相が理事長で、それから、その森づくりのコンセプトについては、宮脇昭先生という、横浜国立大学の名誉教授がいるのですが、その方が提唱したやり方で、森の防潮堤を作ったらどうかということで。実際に津波があったところに、たくさんの神社もあったのですが、その神社の鎮守の森があったところは、津波被害がすごく低減されたとかですね。森の後背の部分の家々が守られるとか。あるいは、塩を被った木々でも、鎮守の森を構成する木々というのは、枯れずにその姿のままにあるということで、いわゆる自然は、そういう災害を何回も体験してきているわけですから、折りこみ済みなわけですよね、災害というものを。そういったものを沿岸に、グリーンベルトとして作っていったら、津波を全く防ぐことはできなくても、減災をする効果があるだろうということで、私は5年間くらい、今は「鎮守の森のプロジェクト」という公益財団になっているのですが、そこの事務局を5年間やって。当時でだいたい40万本くらいの苗木を、たくさんのボランティアの人たちと植樹をしたということがあります。
伊佐:高橋さん、私もこの会社を作って30年を超えたわけで。元来、日本の美しい木質文化を作りたいということでやってまいって。この10年近く、いかに林業とか森林の状態が悪いかということを知りましてね。今、山と工務店の付き合い方の新しいスタイルを作りましてね、それは大変林野庁も期待してくれているのです。我々工務店ほど、森の資源を直接的に使っている業種はないと思うのですよ。製紙会社もどんどん木をとりながら、砕いていくわけですけれど。我々は木そのものの命、構造を生かしていくわけですから。そういう点で我々の仕事も森あってと思いますのでね。まして、私、神社さんにしろ、森があるからこそ神々しさが出てくるし、一体化しているなというふうに思いますよね。やはり我々は、森を考え、また地方の林業を考えて、現代社会の中で諸問題を解いていくということが大事かなと思うのでですね。我々の仕事上の問題と高橋さんがやっておられる、鎮守の森プロジェクトがつながるといいなと思いますね。
高橋:そうですね。鎮守の森のプロジェクト、私は今ちょっと携わっていないのですけれども。森は、明治神宮の森が約100年で今のような立派な森になっていると。ああいう森を作っていく植樹活動なのですね。で、今の科学では、その植樹の科学では、30年くらいであの森を作って行けるというぐらいまで進化をしているわけなのですが。昔、山の中には、奥山という区域があって、山の保水力とか、水源ですよね。それから鳥獣を守るような区域であって。しばしば奥山と里山の境には、神社とか祠があって、そこから先は進んではいけませんよ、というような場所であったのですけれども。戦後の国策によって、全体が里山化していくというか、植林活動になったわけですね。今、花粉症がひどい人もたくさんいらっしゃると思うのですが、我々の仕事は、ひとつはその奥山を作るようなことも、これからの山の中にはそういった場所も必要なのではないかということがひとつあります。
それからちょっと余談になってしまいますが、社長、去年ですね、私伊勢の神宮の宮域林を、視察をしたのですね。で、伊勢の神宮は、宮域林はですね、100年ちょっと前まで一旦御用材を切るために、ご遷宮のためのですね、禿山のような状態になって。その後おはらい町、あの赤福という有名なお店がありますが。あのあたりおかげ横丁ともいうのですけども、何度も何度も洪水の被害に遭うというような歴史があったそうです。それで、禿山になってしまった山に、もちろん、目的としては御用材にするための桧を植えるのですが、そこの神宮の宮域林の技師はですね、桧だけを植えるのではなくて、混交林の中で桧を植えたということなのですね。で、次の次ぐらいの、40年後くらいのご遷宮には使える木材がだいたい出てきますよという状態になっているのですが、そういう混交林の中で、目的林でもあって、そしてその後、洪水被害がそれからはないのだそうですね。そして川を見ると、いわゆる生物多様性の川になっているというか。森のミネラルが五十鈴川という川に流れ込んで、さまざま絶滅危惧種と呼ばれているような小動物、魚も豊かに、植物もそうなのですけど。そういったものが還ってきているということも聞いておりますので、これからの一つの提案として、ですね。神宮の宮域林のようなものも、形もひとつありなんじゃないかなと。まぁ、折衷案というか、いいアイディアかなと思って見ていました。
伊佐:そうですね。確かに当社が取り組んでいます、埼玉県秩父の山には、三峯神社さんがある。ここへの寄進の苗木はですね、多くが海の方々からの寄進ですね。築地あたりの市場の関係の組合の方からの寄進で。桧何万本とかですね、苗木なのですね。それを海の方が非常に目立ちますね。だから海と山が繋がっているというのは、もうおのずとご存知だったということだろうと思いますしね。
司会:そういう意味では、日本全国でそういう見直しをしなければいけないところがたくさんあるような気がいたしますね。
伊佐:そうですね。あと、さきほどの防潮林、やっぱり現代社会のコンクリートと、自然で対処する問題を両立できるような文化が出来たらいいですね。
高橋:そうですね。ハイブリッド型の防潮堤というのも、一部施工した場所もあるのですけども。後背部分、海側のほうはコンクリートだけれども、陸側のほうは土でもって、そこに植樹をしたらどうか。そんなモニタリング植樹みたいなことも鎮守の森プロジェクトの時にはしたりもしております。けっこう生育がよくてですね、これが。
司会:あぁ、そうですか。
伊佐:で、街の方への景観が違ってきますよね。樹木がありますとね。なによりも人の心の問題が大きいですよね。
高橋:はい、おっしゃる通りだと思います。
伊佐:外側では、ハードで防いで。内側で、景観とまた第二次的な予備としての、予防としての防潮林があるという形になればいいですよね。
高橋:はい。まぁ多重防災という考え方だと思うのですが、今回は復興予算で、防潮堤を、コンクリートの防潮堤を作ることが出来たのですが。ではこれを例えば50年後、100年後、メンテナンスをするのは、同じ国の予算で出来るのですかというと、少子高齢化の時代でもありますし、それだけ予算があるのかどうかとか。それは地方財源でやって下さいなんていう話になったら、もう作った意味がなくなってしまうものになる。けれども、多重防災で、森のほうも同時進行でやっていれば、コンクリートが、いずれというとあれですけどね、朽ちてしまうようなことがあっても 森のほうは100年、200年、あるいは千年、二千年と続くような、街を守るようなグリーンベルトになっていくのではないか。そんな思いでたくさんのボランティアの方々と活動してきたということです。
司会:自然の驚異に対して自然で守る。というか、本来の私たち人間のあるべき姿というようなものを考えさせられますね。
伊佐:そうですね。
司会:今月の「わたし歳時記」のゲスト、瀬田玉川神社禰宜・高橋知明さん、そして、今週は伊佐ホームズの伊佐裕社長にもご一緒していただきました。お二方ありがとうございました。
高橋・伊佐:ありがとうございました。
酒井智章さん
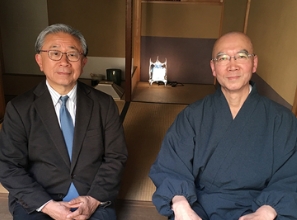
司会:「わたし歳時記」今月、3月のゲストは、日蓮宗 池上實相寺住職、酒井智章さんです。今週もよろしくお願い致します。池上實相寺、1550年に開創されたお寺で、酒井さんは平成3年から住職をお務めでいらっしゃいます。そして、今週は、この方にもご一緒いただきます。伊佐ホームズ、伊佐裕社長です。よろしくお願い致します。
伊佐:はい、よろしくお願いします。
司会:社長と住職の出会いはいつ頃になりますか?
伊佐:はい。もう10年超えたと思いますが、奥様が私どもの会社の文化イベントにお見えになったことが縁で、お寺さんのリニューアルの相談を頂きまして。それ以来深い深いお付き合いをさせていただいてですね。お寺さんの在り方を常に問いておられる。我々も建築会社としてどう生きて行くかということをいつも考えるわけで。
和尚、私もですね、私は高校を出まして、山寺に3か月間にいたことがありまして。そのとき標高700メートルの山なので、電気がない、水道がない、ガスがない。そういう暮らしの中で、NHKラジオだけが入るところだったのですね。雨が降れば、山に霧かかって、非常に森厳な感じがして。そこにいますとね、すべてのことが整っていくというかな。朝5時頃ですね、私本堂の横の方丈に、初めは寝ていましたので、障子越しに朝の光が差しだす頃に、竹林の影が映りましてね、野鳥の鳴き声とか、大変清々しい3カ月でした。それから、東京の予備校に出てきてですね。私はそういう点でお寺さんへのご縁を感じたのは、そこからありますし。あと私は、祖母が大変信心深かったので、朝夕、般若心経が鳴っている中におりました。
それとちょっと私先に申しますが、私が会社を作ってちょうど今、今年31年で。ちょうど今、こういうお彼岸の中にありまして。私が何故こういう住宅会社を作ったかといいますと、自分の住宅への思いというのは、物質じゃなくてですね、自分の精神を鍛えてくれた場所。家というのは、人を教育する場所というのがありまして。物質論じゃなくて精神論がありました。で、今の時代というのは、工場で家が出来るものですから、住む人もなんとなく物質として住んでしまう。わたしやはりそこに精神が宿るような仕事をしたいということが、私の創業の思いでした。そういう点では、ご住職が1回目、2回目と、實相寺に飽きない、あるいは毎朝の掃除のこと、おっしゃっていました中で、私もそういうことを取り込むような経営であり、家を作っていきたい。じゃあ数を作るのではなくて、一棟一棟が飽きないものを作るというか。そこに魂を込めていきたいなということで、そういう点で、私もお寺さんのこうやってお仕事をさせていただいて、ご縁頂戴して、1回、2回と放送に聞き惚れておりました。
司会:ご住職、今の社長のお話でいかがですか。
酒井:そうですね。お寺というのは、そういう意味では、すばらしく計算されて作られた建物だというふうに思います。例えば、本堂でお経をあげておりますと、非常にお経の声がよく通っていく。天井の高さですとか、そこで例えば雅楽を演奏するにしても、非常に綺麗に聞こえる。ですから、洋楽のコンサートをやっても、皆さんが喜んでくださるのは、やっぱりそういうような影響もあるのではないだろうかというふうに思います。やはり心が落ち着く、それから音が非常によく綺麗に聞こえる、そういったような建物である。それは、やはりお寺の作り、それは伝統的にそういう技術者が技術を重ねてきた結果だというふうには思います。
司会:あの、伊佐ホームズさんが改修も手掛けていて、そういったことも皆さん計算されてなさるのでしょうか?
伊佐:あとで我々は、教えて頂くようなところありますけれども。先ほどご住職おっしゃった、その人が持っている声、音質がもっとよくなるという。あるいは我々の持っている心が、もっとそこで気づかされて、心が深まったり広がったりする。別のものを借りてよくなるのではなくて、自分自らのものがよくなっていく場というのは、やはり歴史的な建物の、宗教の力かなというふうに感じますよね。また家も違うのですが、そういう場であったらいいなというふうにつくづく思いますね。
司会:家の、もっと大きな総合的な器として、お寺さんがあるというような感じも致しますね。
伊佐:心のよりどころとしての、ですね。
酒井:お寺というのは、男女とか、年齢とか、社会的な身分とか、そういうものをまったく超えて、大勢の方たちが集えるところなのですね。だから、そういうような特色というものは、考えて作っていたのではないかなというふうに思いますね。その昔は貴族だけのための祈りの場所だったかもしれませんけれども、それが鎌倉時代の祖師たちが、そういうものから解き放って、誰もが来られるところなのだよ、もともと仏教とはそういうものなのだよということを、どんどん教えていきました。それが現代に宗教が生きている、一番の根本になっていくと思いますけれども。やはり、もう一度ですね、私たち坊さんたちは、そのことをもう一度考え直してですね、大勢の方たちが集えるところなのだ、大勢の方たちが祈れるところなのだ、大勢の方たちが仏さまの教えを聞いてくださるところなのだというところを、もう一度考え直して、お寺を活用していかなければならないだろうと。それが坊さんの仕事だなというふうには思っています。
司会:今のご住職のお話で、聞いてくださるというような捉え方をされているのですね。
伊佐:あと私ですね、お寺の方々の生活を見ていましたら、公と私の区別がないですよね。日常茶飯事、人が出入りするわけですから。あの中で心がお育ちになるというか、現代社会はあまりにも私というのを大事にしすぎているというところがあるので。建築的にも、そういう鍵がかからない、「心の鍵がかからない建築」といいますかな、ということを大変感じますよね。
司会:凄い!いい言葉ですね。心の鍵が、それがまさにお寺の在り方と合いますものね。
酒井:そうですね。坊さんが家庭を持つということは、明治以降に公になったようなことでございます。ただ家庭を持ったことによって、どこでもそうでしょうけれども、奥さんがイニシアチブをとっていくのです(笑)それはやはり家庭の運営というのは、全部そうなのですね。だからお檀家の方たちも、住職と話をするよりも、まず奥さんと話をしたほうがいろいろなことが相談しやすいとかですね、そういう意味では、寺におきまして、寺族の中で、奥さんの存在というのは絶大なものがあることは間違いございません。これはどの坊さんに聞いても同じだと思いますけれども(笑)ですから、そういう形でもお寺の在り方というのは、変わってくるのではないだろうかというふうに思いますね。もっとやはりね、奥さんを大切にしなきゃいけないなと、今さらながらにですね、寺の住職としては思う次第でございまして。跡取りもまもなく結婚しますけれども、そういうことは大切にして、お寺を守っていってもらいたいなというふうに思っております。
司会:この前ちょっとだけお話を聞きましたら、イベントなどの企画も奥様がものすごくアイディアをお持ちなのですって。
伊佐:凄いですよね。また、料理もお上手なのですよ。見事な料理!
司会:社長はお召し上がりになったことは?
伊佐:はい。
司会:あぁ、羨ましい!
酒井:イベントの後ですね、スタッフの慰労を兼ねて、うちの家内が料理を作って振る舞うということをよくやっておりまして。相撲の部屋の女将さんみたいに、大鍋でおでんを作るとかですね。30人分とか全然苦にしないでやってくれますので。
伊佐:背中がね、料理のお姿を見るとかいがいしいなぁっていう感じ。喜びが背中にあるというような。
酒井:まぁ、それは得手不得手がございますから(笑)どの奥さんもそれをやれと言っても なかなか出来ないかもしれません。たまたま、そういうことが出来るというのであるならば、そういうことをつかってやってくれたらいいなというふうに思いますね。
伊佐:私も、お寺さんから嫁を取るといいなというふうに勝手に思うのですよね、子どもたちのね。そのくらい一番のいい教育がなされている、家庭教育としてはなるのでないかなと思いますね。
司会:気働きのできるお嫁さんが迎えることが出来るということですよね。 ありがとうございます。社長とご住職のお話はこのへんがお時間になってしまいまして。来週もう1週ございますので、お寺の今後のことについてもご住職にはお話を伺いたいと思っております。
酒井:はい、承知しました。
伊佐:今日は楽しゅうございました。
司会:今月のゲスト、池上實相寺住職、酒井智章さん、そして、今週は伊佐ホームズの伊佐裕社長にもご一緒いただきました。お二方ありがとうございました。
酒井・伊佐:ありがとうございました。
風間茂彦さん
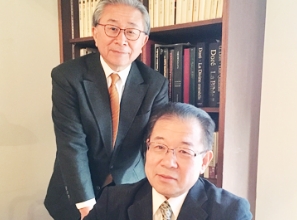
司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、慶応義塾 塾監局参与の風間茂彦さんです。今週もよろしくお願い致します。風間さん、1953年、東京都のご出身。去年まで母校・慶應義塾大学のメディアセンターの事務長を務めていらっしゃいました。そして、今月最終週の今日は、この方にもご一緒いただきます。伊佐ホームズ、伊佐裕社長です。よろしくお願い致します。
伊佐:はい、よろしくお願いします。
司会:風間さん、東京都ご出身とご紹介致しましたが、世田谷にも関わりがおありなのですよね?
風間:えぇとですね。最初は私、渋谷で生まれたのですけれども。小学校4年の時ですね…あ、5年ですな。5年の時に瀬田に引っ越してまいりました。
司会:そうですか。
風間:いろんなことをやっておりましたけれども、一番印象に残っていることといいますと、私の父親がなにか教養を身につけなければいけないということで、いろいろな試みをやってくれたのですけど。まず、最初に講談社の「世界文学全集」というのを買ってくれまして。それでこいつは本を読むかなということだったと思うのですが、一切それには興味を示さず、ですね。で、親父は困りまして、次に、しばらく間を置いて、今度はリーダーズダイジェストという会社があったのですけれども、そこが出しておりました「家庭音楽全集」というクラシックの小曲を集めた30cm・LP12枚組、これを買い与えたのですね。そうしましたら私はそれに夢中になりまして。小さな電蓄にそのレコードをかけて、暇があると聞いていたという。そういうような少年時代だったかなというふうに思い出しますね。
司会:伊佐社長、どうでしょうか?その辺に共感するところは?
伊佐:いやいや、ほとんど同世代なのですがね、風間さんと。全く私は違うなと思いましてね(笑)私の家は商家でしたのでね、父親が帰って来て、母との夜の会話とか、仕事の話なのですよね。「こういう仕事がうまくいった」とか、あるいは、「こういう社員が辞めるから、おまえ今度行って説得してくれ」とか、ですね。あるいは、おふくろが夜遅くにお客様のところに、何か届け物をするときに私もついて行ったり、ですね。そういう点では、風間さんは東京で、私は九州の福岡。全く違う時代を過ごしたのだなということを痛感しますよ(笑)
また前回までの、風間さんのいろいろな大学を終えられての、慶應義塾の中での。最後は、社会的情報の特性が大事だという図書情報学の、図書と情報というのが結びついて、どうやってそれが役に立つかということが問題だということをおっしゃっていたように。この私は、私的には結構本を読むのですが、どちらかというと人物の伝記が好きでして。父親が事業をやっていたということとかで、実感する生き方というかな。だからあまり情報を広くというよりは、なんだか偏った情報で生きてきたなというふうに思いますが。風間さんは学問としての、そういう入り口が違ったのだなと思った次第ですけど、いかがですか?
風間:そうですね。ですから、そもそも最初に申し上げたのは、この図書館の世界に入ったのは本を好きだったわけじゃないので(笑)そうしますと 内容よりもその扱いをどうするかというところにだんだん興味がわいてきたと。というのは、究極的には、それは自分が読むというよりも、図書館の利用者の方・本を読む方に、いかにいい情報を提供するかと。そして、よかったよ、ありがとうと言われることが楽しいと。そういうところに喜びを見出したということかもしれませんね。
伊佐:なるほど。当社はですね、毎朝1冊の本をみんなで味わっていましてね。約10年続いておりまして、大変いい習慣だと思っておりまして。そういう点で本の力というのを、先ほどの学問的な図書館学といいますか、それとは違うのですが、我々が自分たちの道、会社経営を1冊の本を頼りに来たなという実感はありますね。
風間:そうですね。本の扱いなんかに興味があるといいましたけれども、それはやっぱり内容にアクセスするためでありまして。本の実態というか、一番大事なところはその内容ですよね。そこにいかに、いろいろな知識だったり経験だったりが盛り込まれていて、それを自分のものにすることができるかということなので。今、伊佐社長のやってらっしゃる1冊の本を読むという、その取り組みというのは非常に大事なことかなというふうに思いますね。
伊佐:ありがとうございます。やはり情報がどうやって血肉化していって、自分のものになっていくかと。言葉を味わうというか、自分のものにするということを社員と一緒に共有してですね。そういう点で大事にしてきたなというふうに思います。ただ非常に広範囲な本の海の中をどうされていくかという、尊いお仕事を風間さんはされてきたのだなと思いまして。まぁ、当社が昨年の5月、家づくりの完成を終えまして。大変喜んでお住まい頂いているようなのですが、そのような方とお会いして、人生の出会いを嬉しく思います。
司会:風間さん、どうでしょうか?伊佐ホームズさんが手がけられた家は、今快適にお住まいでいらっしゃいますか?
伊佐:あまり無理強いしてはいけません(笑)
風間:これは無理に申し上げるわけではないのですけれども(笑)本当に満足しております。もとはといえば、私どもの敷地と伊佐ホームズさんの本社というのが、声をかければ通じる距離にあるわけですね。毎日、私の家の前を社長は通って通勤なさっているくらい、そんなご近所づきあいというところからこういう話が出てきたわけでありますけれども。非常に私どもの考え方というか、家に対する考え方、あるいは人生に対する考え方とか、それを理解していただいたうえで、設計者の方をご紹介いただきまして。非常にいい関係で1つの家を作っていただくことが出来たなと思っております。ありがとうございます。
伊佐:去年の年末に、風間さんの奥様の手料理で大変なごちそうを頂きましたね。やっぱり仕事を終えて、改めてそういう食事を共にさせていただいて、もてなし頂いて。なんとこの家づくりというのは、有難い仕事かなというのを格別な思いで昨年の年末はお世話になりました。
風間:ありがとうございます。やっぱりですね、美味しいお料理をつくるためにはいい、その作れる空間がなければといけないということかなと思いまして。新しい家になりましてから、料理がうまくなったかなという気がしております(笑)
司会:それは嬉しいですね。
伊佐:器の見立ても美しいですしね、本当にすべて最高でしたね。お願いがあるのですがね。
風間:あ、なんでしょう。
伊佐:私ども、寺院の客殿をお手伝いすることが多くてですね。今、お寺さん等も檀家さんが少なくなっていくので、地域の方々としっかりとした支える場所でありたいと、 いろいろ相談を受けましてね。私は、あるご住職には、いろいろな蔵書を、本を、お受けになって、そういう本があるような喫茶コーナーとかをお寺のなかに作られたら、大変地域とのつながりにいいのではないかということを思っていましてね。我々家作る前に、よく、先生の蔵書をもらってくれないかとか相談を受けるのですよ。今後私は、受けた場合、私どもではなくて、いろいろな方を繋いで有効活用したいなと思いましてね。その時にはぜひ風間さん、バックアップをお願いしたいと思いますね。
風間:そうですね。何ができますか、わかりませんけれども。私もこのお話の中で申し上げましたけども、最近は電子の本が多くなったということがありますけれども、実は電子の本というのは非常にそっけないものでありまして。そうしますと、やはりですね、いかに電子本が栄えても、もともとの紙で作った、この魅力というのは他に代えがたいものがあります。ですから、そういうものが1回利用されて捨てられるのではなくて、再利用されて、また手にしたい方のところで利用していただけるということがあれば、それは本当にいいことかなというふうに思いますね。
伊佐:そうですね。
司会:また伊佐社長との共同事業も出来てくるのかなというような気も致しますけれども。あの、風間さんは3月で慶應義塾大学定年退職ということなのですが、これからやってみたいことって何かおありでしょうか?
風間:そうですね。同じように辞めていく人間の中でも、また同じような仕事をどこかで見つけてやるという者もたくさんいますけれども、私自身は、いわゆる同じ仕事は、もうこれで一区切りつけようかなと思っています。と申しますのも、今まで仕事がありましたもので、やり残していることが随分あるわけで。例えば、読みたい本もたくさんあるけれども、読まずにあったり。聞きたい音楽もたくさんある。しかしながら単にメディアを買うだけで、溜めてあってですね、いろいろあるわけですね。まずは、そういうものをきちんと読むなり聴くなりしてみようと、いうことから始めようかなと思っています。一つ最近思いますのは、仕事を辞めましてから、急に感受性が豊かになったかなと思います。これはですね、不思議なことで、本来、年を取ってきますと、そういったものが衰えるじゃないかと思っていたのですけれど、なにか本を読みましても心にさっと入ってきますね。音楽を聴きましても、難しくて、七面倒くさくて嫌だったものがですね、なんだか理解が及ぶようになってきたと。これは何なのだろうと思って。きっと他に仕事のことを考えていた部分というのがなくなって、コンピュータでいいますと、容量が増えたと。そこでいろいろな仕事が出来るようになったのかなと思っております。ですから、そこを活用して、今までやり残したことをやっていきたいなと。その中にもちろん、伊佐社長がおっしゃるような、一緒の仕事もあれば、やっていきたいなと思っています。
司会:ありがとうございます。「わたし歳時記」今月のゲスト、慶應義塾 塾監局参与の風間茂彦さん、そして、お話大変盛り上がりました、伊佐ホームズ・伊佐裕社長ともお話していただきました。ありがとうございました。
風間・伊佐:ありがとうございました。
久喜邦康さん

司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、秩父市長の久喜邦康さんです。よろしくお願い致します。久喜さん、1954年生まれ、秩父市のご出身です。2009年から秩父市長をお務めでいらっしゃいます。そして、5週目、今月最後になりますけれども、この方にもご一緒いただきます。伊佐ホームズの伊佐裕社長です。よろしくお願い致します。
伊佐:よろしくお願いします。
司会:これまでの回でも、何回か社長のお名前、市長から出てきましたけれども、これまでの番組をお聞きになって、何か感じられたことおありですか?
伊佐:私はですね、林業の問題で市長とお会いしたり、観光の問題だったり、それぞれ今まで約4年近くお付き合いさせていただいているのですが。総合的にお話を聞いたのはこの番組が初めてでしてね。特に私は水道と電気の問題については大変感銘を受けましたし、これが全国のモデルになっていけばいいなというふうに思いました。
司会:そうですね。秩父といいますと、伊佐ホームズでは大きなプロジェクトを進めていらっしゃいますけれど…。
伊佐:そうですね。市長、私はお付き合いをお願いして4年近くになりますがね、私も昭和63年に会社を興して、ちょうど今32年目になります。ちょうど、お話を聞きましたら市長が開業された年と同じだったなと思いましてね。私は創業の時に家族を連れまして、秩父の札所巡り、三十四番までを歩いてやったのです。その折に触れた言葉がですね、「枝葉が枯れないのは根が深いから」という言葉に出会いましてね、このことが、創業時の逸る心にとっては大変大きな言葉をいただいて。(これが)私の出発点でして。またそれ以来、ちょうど今から6年前になりますが、家内が他界して追悼の意味で、またそのあとに秩父の札所をまわった時に、林業家の皆さんと出会った、と。この林業家が日本の中でも新しい林業をやっておられて、3Dスキャナーという機械で、山の立っている木の情報を計測して林業を行う。大変先進的な方々でして。これはすごいと思いましてね。我々工務店が、そういう山の木を、立派な木を、必要な木を買うシステムを作ってですね。これ、プラットホームという、産業基盤というか、そういう情報基盤というのを作りましてね。全国に先駆けてプラットホームという会社を作ったと。以来、いろいろなことで市長とお会いしてですね、私も秩父市の事業推進アドバイザーをやってですね、秩父が持っておられるいろいろな資源を生かしていこうということで、今お手伝いして。特に昨年は旅館を作ろうというプロジェクトもご提案していましてね。秩父には、いろいろな養蚕農家の素晴らしい民家が残っています。ある外国人はですね、デザイナーなのですが、カール・ベンクスさんという方、去年の新聞で言っていますが 「古民家は宝石の原石」と言っているのですよね。やっぱり、地域・地域の、残っている祭であるとか、古くからの教えだとか、形態とか、約束事というのは、その街を支える根幹だと思うのですね。我々新しいものに取り組むのですが、その根幹を守り育てるために新しいものに取り組むという。そのことがないと、新しいものに取り組んでも、それはただ、ただ、経済的なことだけであってですね。そういう点で、秩父は札所にしろ、さまざまなお祭りにしろ、珍しいくらい残っている。私はこれから地方創生の時代で、前回までの、エネルギーとかという生活の問題と文化の問題こそ、地方創生の大変な宝物だと思いましてね、今年も頑張ってまいります。
久喜:はい、よろしくお願いします。
司会:こういった外からの力について、市長はどんなふうに感じていらっしゃいますか?
久喜:いやー、伊佐社長さんのお話聞きながらですね、素晴らしい方だなというふうに、秩父の本当の応援をしてくれる方々、私こういう方々にお会い出来て嬉しく思いますし、本当に頼りにしたいと思っています。
伊佐:秩父の一番奥の三峰神社はですね、行っただけでなんだか厳かな場所でしてね。あれは、日本武尊が創建したと伝えられる、関東平野で一番古いといわれていますよね。日本書紀にも書かれていますけれども、あそこを聖地として据えた景観の美しさというのはあると思いますね。我々、林業と取り組む人間にとっても、秩父は地質の問題で大変質が高い木材なのですね。そして北斜面が多いので、非常に成長が厳しいので、その分良質材が多いという。私は林業を木材から始まって建築をやっていますが、さまざまな秩父周辺の魅力に取りつかれている人間であります。
司会:外の方がここまで魅力を熱く語るという…、
久喜:ありがたいですね。本当にありがたいというふうに思います。
司会:こういった力を借りて、さて秩父市はという、なにか意欲的なところ、市長おありじゃないかと思うのですが。
久喜:そうですね。秩父の木材を、資格というか基準を取らせていただいて。で、川下の方々に使っていただく、そういうようなブランド的なものを強めていければなと思いますし。あとは、大滝に市有林、秩父市有林がございます、市で持っている、市の。 市有林のところの樹木は美林ということで、大変貴重にされています。特に我々自慢なのは、秩父市民会館のことなのですが、そこの木は大滝のその市有林から作られているのですね。自分のところの建物は自分の木で作っているという。建築屋さんが、建てた会社が、「こういうのは初めてだ」というふうに皆さん驚かれていましたけどね。
司会:水も電気も、そして木材も全部賄えるということですよね。
伊佐:ね。あと秩父は養蚕業が残っているのですね。今養蚕農家が10軒あると聞きましたが…。
久喜:そのとおりですね。
伊佐:私も知りませんでしたけど、群馬県、長野県もかつて養蚕がさかんだったのですがね、やはりリンゴ畑とかで農薬を散布するので、もう蚕がダメらしいですね。まぁ蚕がダメというか、桑の葉がダメなのでしょうね。秩父はあるのですよ。これ、繭からなんと1200メートルの糸が取れるのですよね。特に秩父の場合強いので、糸をよって、糸にする場合3本で立派な糸になるそうなので、だから江戸時代から大変養蚕業がさかんだったという歴史があるところで。そういう点で、いっぱいの宝物が秩父市にはありますよね。
久喜:そうですね、養蚕のほうは10軒になりましたけれども、皆さんよく頑張っていただいて。で、その繭の恵みに感謝するお祭りが、まさに「秩父夜祭」なんですね。で、秩父神社のほうに、お祭りの時にはその繭を感謝のしるしとして贈呈している、そういうことで秩父夜祭はスタートしているとも聞いています。
司会:秩父銘仙という織物は、ではその繭からというか…。
久喜:その通りですね。
伊佐:そのファッションショーですよ、最終的にはお祭りは。
司会:あのプロジェクトに関してなのですけれど、順調に進んでいる、あるいはご苦労は?
伊佐:はい、いろいろ苦労もありますがね。昨年は内閣府に呼ばれて、当社グループの取り組みが大変な評価をいただいて。林野庁もこれをもっと進めていくということもありましたし。また昨年秋は、世田谷区の子供さんたちを植樹に連れていきましてね。子供さん、こういいましたね。「モノ作りは自然から生まれるのですね。」という言葉がありました。いわゆる都市にいますと、パーツ・部品なのですね。モノなのですね。しかし自然に触れますと、原理原則が見えてくるというか。これ、私は尊いなと。その中の一部だと認識をするということは、大きな人間の成長になると思います。
司会:そういえば、社長。絵画展に入賞されたお子さんが、来年は秩父の絵を描きたい、森を描きたいとおっしゃっていましたよね。
伊佐:そうでしたね。
司会:せっかくですから、描いた絵はまた秩父でもご覧いただくというようなことも、広がりも出てくる。そういった子供からのつながりも大きいですよね。
伊佐:あぁ、いいですね。大きいですよね。
司会:こんな風に感じると、世田谷区民の皆さんに聞いていただいているこの番組ですが、 世田谷の皆さんもいろいろな意味で、自然のこととか感じることが多いじゃないかなと思うのですが。
伊佐:そうですね。是非一度おいでください、秩父のほうに。
司会:では、その秩父の魅力。社長にはさっきから熱くいろいろ言っていただいているのですが、お二人にもう一度、一言ずつお話していただきたいのですが。
伊佐:では、私のほうから。やはり、懐かしい日本が残っている。そして地形がいいですね。ほとんど四方山に囲まれているので、人間にとっての安心感があるというか、それが大きいと思います。歴史と自然ですね。
司会:市長、いかがでしょうか?
久喜:ひとことでいえば、ですね、私は癒しの里だというふうに思います。様々な方々がいろいろな思いをもって生活されているわけですけど、ちょっとリラックスしたいなとか、まぁそういうときに、ふと自然の中に身を置くというのは、私は非常に大切なところであり、それが秩父でできると。しかも80分で簡単に来られるということですね。そこで食べたり飲んだりしてひと時を過ごして、またリフレッシュできると。そういうような区民の方の癒しの場として、秩父が提供できればなというふうに思います。
司会:私も新年の抱負、「早く秩父に行こう」と決めました(笑)
伊佐:いらっしゃってください。
久喜・伊佐:お待ちしております。
司会:もう社長は秩父の人になっていますね(笑)
司会:どうぞ皆さんもぜひ魅力あふれる秩父に足を運んでみて下さい。今月のゲスト、秩父市長の久喜邦康さん、そして、今週は伊佐ホームズ・伊佐裕社長にもご一緒いただきました。ありがとうございました。
久喜・伊佐:ありがとうございました。
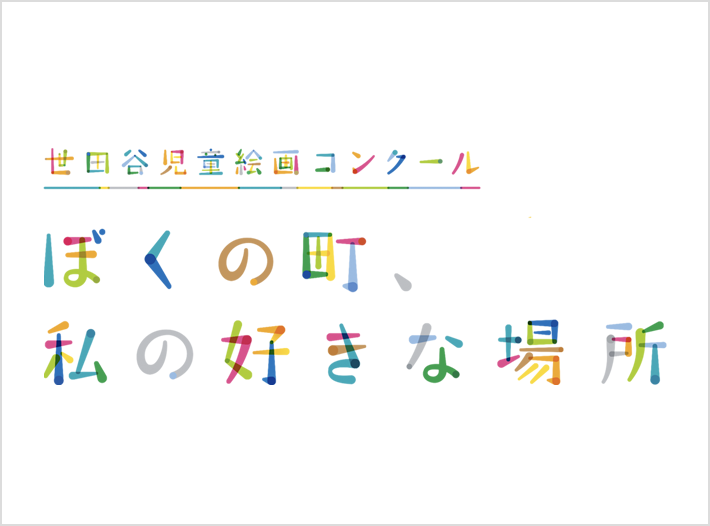
武見敬三さん
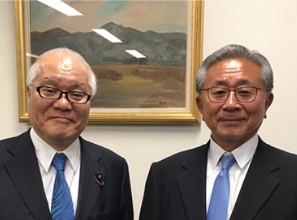
司会:わたし歳時記」今月のゲストは、参議院議員の武見敬三さんです。よろしくお願い致します。武見敬三さん、1951年生まれ。慶應義塾大学法学部卒業、同大学院政治学専攻修士課程を修了されました。そして1995年に参議院議員に初当選。国政に日々尽力していらっしゃいますが、さて、今週なのですけど、この方にもご一緒いただこうと思います。伊佐ホームズの伊佐裕社長です。よろしくお願い致します。
伊佐:はい、よろしくお願いします。
司会:今月最終週になってしまいました。社長、いろいろ今月お話聞いている中で、感じられることたくさんおありだと思うのですが、まずお二人の関係についてちょっとお聞かせいただいてもよろしいですか?
伊佐:我々は昭和45年に慶応大学法学部に入りました。同じ学科だったのですよ。
司会:あぁ、同期。
武見:政治学科。
伊佐:まぁ、武見先生、武見はですね、すばらしいラガーマンでした。非常に精悍な顔つきでプレイをしていましてね、フランカーだったのですよ。
武見:いまでも精悍だと思っています(笑)
伊佐:はい(笑)今ね、ちょっといろいろね、ありますがね(笑)前回まで健康寿命ということで、私も感慨深くお聞きしとったのですけどね。本当に精悍でしたよ。で、フランカーというのは、フォワードとバックスのつなぎ役で行動範囲が広いのですよ。たぶんね、私、この4回の今までのインタビューを聞いていましてね。まさに、こう身体、ラグビーの感覚が今の武見のサーキットの広さかなというふうに感じますね。ここだけじゃないというところがある。ここだけもすごいのですよ。しかしそれを中心にした非常に広い、広い範囲を見ている。医療と防衛問題、安全保障問題とかですね、今非常に国の困難な問題を多々聞いてですね、本当に私も危機感感じながら聞いとったのですが。ただ武見の話を聞いて、今後の日本がリーダーシップの取り方があるという、非常に悪いことが先導モデルになるという可能性があるという。大変それは私も興味があって。本当に素晴らしい仕事をしてくれているなと思ってですね。素晴らしいよ、本当。
武見:いや、だけどね。伊佐というのはね、とんでもない蛮カラ学生でね。
伊佐:今日バラすの?それ(笑)
武見:福岡のね、修猷館とか何とかいうね、学校からやってきてね。それで1年中、詰襟の黒服来ているわけ。
伊佐:その下ね、下着だったりするのよ。洋服なくて。
武見:それで、なんかこの人…綺麗なのかなって思うような、そういう蛮カラの学生で。で、下駄とかサンダル履いて来るのですよ、学校。そんな人いませんよ、当時だってね。そしたら同じ政治学科だったものだから、授業だとか試験だとか一緒に受けるわけですよ。そのうちにだんだんだんだん、なんとなくね、メンタリティーが似ているらしくてね、仲良くなって。
伊佐:(笑)本当ね。
司会:じゃあ特に何か大きなきっかけがあるわけでなくて、自然に…。
伊佐:共通のね、ラグビーの…。
武見:ラグビーとか、またそういうの、よく見に来てくれたわけ。
司会:伊佐社長、プレイは?
伊佐:私は社会人になって、やりました。
司会:そうなのですね~。
伊佐:で、我々、私が出た高校はですね、非常に「質朴のふうを鍛えず」という飾らないことが大事だったのです。
武見:(笑)
司会:笑っていらっしゃいます
伊佐:なにそれ?(笑)
武見:だって、質朴とか飾らないとか言ったってね、そりゃ程度ってものがあるじゃないですか、やっぱり。当時の学生時代の伊佐というのはね、そういう程度をはるかに超えていましたよ。もう純朴や、いわゆる蛮カラってやつ。本当の蛮カラ!
伊佐:私はもう大学行ってね、「違うんだ!自分には、違う大学に来たな」という思いが、初めありました。だから学校嫌いだった。あんまり学校に行かなかった。
司会:本当ですか?そういう中でどんどんどんどん結びつきが強くなったというのは、何かおありだったのでしょうか?
武見:いや、彼がやっぱり今の伊佐ホームズを始めて、それで仕事を頑張るようになったときに、私はまさに世田谷の住人なのですよ。で、私なんかはね、女房が世田谷の駒沢1丁目に住んでいたわけ。女房が、というとおかしいかもしれないけれど、要は女房の実家に私は間借りして住んだわけ、結婚して。それで、サザエさんのマスオさんになって。そしたら今度、結果として、そこに私が家を建てて、そこに完全に住み込む状態になったわけですよ。そういう中で常にお家を改築したりするときに、伊佐ホームズのご厄介になっているわけ。
司会:そうですか~。
武見:だけど、ありがたいのはね、ひとつ違うの、他と。なにかひとつがいいのよ。これはね、例えば増改築の話だけじゃない、庭もそう。植えてもらえる木、一本一本がね、良く育つし。しかも、その枝ぶりがいい木がちゃんと育つような木、ちゃんと持ってきてくれる。
伊佐:そういわれると嬉しいですなぁ。まぁ、私が会社をつくってもう31年目になのですがね、やっぱり家というのは文明という道具じゃなくて、文化だと思いましてね。やっぱり人の心を育てるものですから。文明と文化というのは大変違うと思うのですよ。文明というのは目的のための手段です。そのあとに文化があるわけで。あまりにも、私住宅産業が文明の産物になって。だから住宅産業という言葉は本来おかしいかなって。やっぱり心が、こう伝わるような家を作る。その奥には性能とかそういう材料とかがあると思いますが、そういう気持ちの持ち方によって、やはり家というのは違ってくると思いますよね。
武見:あと私はね、伊佐ってね、その蛮カラの本質の中にね、日本の和の精神があるのだよね。だから、その和の精神みたいなものが彼のビジネスの根幹にあるわけ。だからね、洋風の家みたいに見えていて、実は和の精神がその中にしっかり入り込んでいるというね、そういう特色を伊佐ホームズって持っていますよね。私ゃ、なにもここでね、広告までする必要はないのだけども(笑)だけど実際に、私は常にそれを感ずるわけ。だからね、それはやっぱり伊佐の生き方そのものなのかな。
司会:じゃあ、居心地のいいお住まいでいらっしゃいますね。
武見:そりゃもう居心地いいですよ。そういう、今の時代が逆にそれ求めているような気がする。
伊佐:そうね。
司会:それから先週までのお話の中で、「在宅」ということも出てきましたが、それも今のお家の話と繋がっていきますよね。
武見:もろ、結びつきますよ。やっぱりバリアフリーで、いわゆるおトイレとか、それからお風呂なんかはね、水回りなんかはとくにそうだけれども、ご高齢の方が滑って転んだりしないように、かつ使いやすいようにしなきゃいけないでしょ。そういう配慮ってこれからますます住宅の中で求められてきますから。それはもう、伊佐のところがやっていることを徹底的に広めてもらいたいですね。
伊佐:私はね、空き家の問題って大きいなと思って。それとやっぱり福祉とか医療の問題に、社会の問題点を解決することがやはり喜ばれて、それがまたビジネスかなと思いますのでね。やっぱり空き家をいい形で活用していきたい。
武見:世田谷区はね、一部、区民センターみたいなね、寄り合い所みたいな機能のものをしているけれども、あれだけじゃなくて、高齢者支援の拠点を作ったりね、やり方これからたくさんあるだろうと思うし。またその所有権を持っている方なんかにも協力していただいて、税制だとか補助金も含めて、いろいろな形でそういうことをやりやすくするということは、これから世田谷区の中でますます必要になるでしょう。
司会:そうですね。武見先生には、もちろん国のために動いていただかなければいけないのですが、おふたりで世田谷区のためにいろいろなことを、力を貸していただけるような気が致しますね。
伊佐:そうですね。困ったことを解決して、モデルを作りたいですね。
武見:本当!私はね、在宅でも医療や介護がね、相当きちんと受けられて、それを「ホスピタル・アットホーム」というのですよ。もう家に病院があるのと同じだと。そういうところまで世田谷区でね、その仕組みを作っていって。で、世田谷に住んでいる方々がね、人生最後まで楽しく有意義に過ごせるようにするというのが私の一番のやりたいことだね。
司会:とてもいい言葉ですね。「ホスピタル・アットホーム」。温かいですね。さぁ、おふたりにとっては、来年はとても楽しみ年ではないかと思いまして。ラグビー。
武見:そう、ラグビーワールドカップです!これ招致するために、私ねシドニーまで森喜朗さんと一緒に行ってね、それで招致活動をやっていたのですよ。ついに念願かなって、来年いよいよラグビーワールドカップがアジアで初めての開催です。
司会:またそこで活力をぐんとアップしていただいて、どうぞ、世田谷区のため、国のために、これからもご活躍いただければと思います。武見さんには以前も「私歳時記」に出てきて頂いているのですけれども、また是非登場していただければと思います。今月の「私歳時記」のゲスト参議院議員の武見敬三さん、そして伊佐社長にもお話を伺いました。ありがとうございました。
武見・伊佐:ありがとうございました。
清水英碩さん
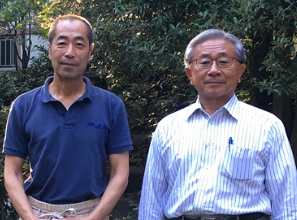
司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、九品仏浄真寺住職、清水英碩さんです。今週もどうぞよろしくお願い致します。九品仏浄真寺、世田谷区奥沢にある浄土宗のお寺です。清水さん、こちらの17代目の住職でいらっしゃいます。
そして、今週はこの方にもご一緒いただきます。伊佐ホームズの伊佐裕社長です。どうぞよろしくお願い致します。
まずは伊佐社長、実はご自宅がこのすぐ近くということで…
伊佐: はい。お寺さんの土地をお借りしまして、家を作って25年経ちますね。
司会:そうですか。もうその間、足しげくこちらのほうには通って?
伊佐: そうですね、私にとっての日常の大事な部分ですよね。実は私、住職、福岡が故郷なのですがね。ここに来るまではいつも故郷に帰るという気持ちが強かったのですが、ここに家をもって、このお寺さんを背景に拠り所があって生活していますとね、なんかこちらの方がね、故郷なのですよ。だから福岡から帰ってきて、九品仏さんの門を見ますとね、帰ってきたなと。特に桜のころは、行くときはこうだったけど、帰ったらもうこうだったよなというのが気になりましてね。そういう点では、故郷というのは、今生まれたところよりは心地いい場所が故郷になっていくなという気がしておりますね。
司会:社長のように思っている方、このへんにはもうたくさんいらっしゃるでしょうね。そんなお二人が初めてお話を交わされたというか、出会いというのは何かきっかけがおありだったのでしょうか?
伊佐: はい、これはもう大事な時でしてね。もちろんお顔は存じ上げているし、ただそれ以上の親しさは頂いていなかったのですがね。5年前に家内が他界しまして、来月11月の14日が命日になりますが。私は、宗派も違うのですが、もう2年半の闘病生活でしたので、いよいよその時が近づいてきたときに、娘たち、子供たち5人おるのですが、相談しましてね。何かのときには浄真寺さんにお願いするつもりだということで。もういよいよという時に、4、5日前でしたでしょうかね、あらかじめその時はお願いしたいという旨はお願いして、心地よく迎えていただいたのです。それが本当に急速にご住職とのつながりが強くなったように私は思って。そういった大事なことを送っていただいたわけですから、ありがたいなと思います。
司会:実は、伊佐社長とのつながりといいますか、伊佐ホームズで児童絵画展を主催して、今ちょうど開催中ですが。こちらのほうにも「ぼくの町、私の好きな場所」、浄真寺さんの絵が出てきているのですよね。毎回ありますよね。
伊佐: 毎回出ていますね。今年はなかったのですがね、昨年素晴らしい作品がありましてね。準優秀賞をとった「九品仏浄真寺総門」というタイトルのですね。
司会:あ、ありましたね。
伊佐: 小学校3年生でした。で、子供さんがこう書いているのですね。その場所が好きな理由、「夏休みに毎日九品仏のラジオ体操に通いました。この門をくぐると、緑が多くてとても気持ちがよいです。夏の間にこの門の近くでセミの抜け殻を10個以上拾って持ち帰りました。自然がいっぱいの九品仏が大好きです。」という素晴らしい絵でした。
司会:本当に素晴らしい。あの、重みがある絵ですね。住職…
清水:ええ、さっき拝見しました。大変雰囲気が出ていますよね、見事ですね。
司会:やっぱり、好きだという気持ちが絵に表れている…これだけいろいろな方に親しまれている場所なのだなというのを感じますね。
清水:改めて私も感じます。ありがたいですね。
司会:あ、やはり、ありがたいという思い…。
清水:えぇ、思います。
伊佐: 子供さんにとっても、歴史があるものというのは、やはり関心があるのですね。だから歴史というのは古いだけではなくて、続いていくのだなと思って。力があるのですね。ただ古いのではなくて、力があるから書きたくなる。やっぱり人間の根本に立ち返ることが出来るかなというふうに思いますよね。
清水:やっぱり味が出てくるのですよね。
伊佐: そうですね。そういえば、ご住職は木に大変造詣が深くていらっしゃって。秋田のほうに植林をされて、将来の建て替え用の材を用意されているということで…。
清水:実はね、私そんな木に造詣も全然深くなくて。むしろ逆でね。現在の浄真寺の境内を見ますと、やたらと木があるでしょ。で、京都とかああいう神社に行きますと、境内にはあまり大木はないのですよ。むしろ裏山とか、ちょっと伽藍から離れた位置には緑があるのです。まぁ、何を言おうとするかというと、うちはね、みんな落葉樹で、その時期になると落葉掃きが大変なのですよ。だから境内に木があることを良しとあまりしていなかったのです、若い頃からずーっと。願わくば、ない方がいいと思っていた。ただあまり切ることも出来ないし。なんでこんなに境内に木が鬱蒼としているのだろうと思っていたのです、しばらく。で、あるとき、奈良のあれは薬師寺でしたかね。訪れたときに、薬師寺として植林をしていると、山に。将来お堂のね、伽藍をいずれ建てなおさなければいけない時期が来る。そのための用材として植林をしているという話を聞きまして。あ、なるほどなと。そういえば、境内に、木を植えるということは、将来、そのお寺の、神社のお堂を建てなおす用材としてやっぱり境内に植えたのかな…そこからスタートで。たまたま私の家内のお父さん、岳父が秋田県の営林省に勤めている。そういうこともあって、その話をお父さんに話したところ、将来国有林になっちゃって、今なら、山というかね、そういう土地がすごく安く手に入るからということで。そんな話からトントン拍子に。平成の7年くらいでしたかね、約2万坪の山を、お寺で購入したのです。そこに4千本のけやきを植林しました。で、すでに秋田ですから、秋田杉が2千本植わっているのです。ですから、合計6千本、お寺で育てることになりまして。育てると言っても、目先のことじゃなくてね、もう300年、400年先を思って植えました。そこからだんだん木に親しみというか、愛着が出てきたというか。ですから、全く最初は逆でした。で、今はむしろ木が大事だなと。で、木というものはお金で買えないのですよ。要するに、時間はお金で買えないのです。木を育つには、それだけの時間がありますからね。ですから、今からやっとかないと間に合わないなと、そういう思いで植林をしました。
伊佐: 私も長年こうやってお寺さんを見ていましてね、やはり木が増えてきて、庭が整備されて、非常に参拝者が増えましたね。
清水:おかげさまで。
司会:こちらのほうも、前はもうちょっと公園のような雰囲気だったと…。
伊佐: もっと土が硬くて、すこし公園のような状態でしたね。それが、緑が増えたら、非常に参拝者が増えて、建物が余計生きてきましたよね。
司会:なるほど、みんなわかるのですね。感じるのですね~。
伊佐: やっぱり美と宗教は背中合わせだと思うのですよ。美しいところで、気持ちが気高くなって、心が整って、意識が高まるというか。一緒だという気がします。
清水:私の代になってからもみじを植えだしたのです。それまでは境内にもみじはあまりなかった。で、昔から銀杏・イチョウは有名でして、300年くらい歴史がある木で。ただそのイチョウの黄色を映えさせるには、朱が欲しいということで、もみじを何種類かに分けて植えたり、植え替えたりして現在に至って。なんか今、紅葉の時期は、私から見て綺麗だなと思うようになりました。
伊佐: 12月の第1週まで素晴らしいですね。でね、色が抜けた後のまた色というのがいいのですよ、もみじは。本当に落ちる寸前まで。鮮やかな赤もいいけど、抜けたあともまたいい!それが12月の中旬までありますね。
清水:それでね、朝いちばんとか、夕方、皆さんがひいたあと、下に敷き詰める…それもまた綺麗ですよ。
司会:こちらは時間帯として、何時から何時まで入れるというのはあるのですか?
清水:朝6時から5時閉門です。
司会:6時から5時まで。もう本当に心を安らげる場としていつでも来られる場所ですよね。
清水:はい、是非お越しください。
司会:社長にとっても、とても大事な存在になっているところということで。私もいろいろな思いでまた訪れてみたいなと思っております。今週は九品仏浄真寺住職 清水英碩さん、そして伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わってお話していただきました。ありがとうございました。
清水・伊佐:ありがとうございました。
中村一也さん
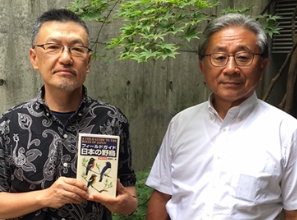
司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、日本野鳥の会東京・元代表の中村一也さんです。よろしくお願い致します。中村さん、1956年東京都のご出身。1993年から日本野鳥の会の活動に参加されています。幹事、副支部長を経て、2009年から現在の日本野鳥の会 東京の代表を4年間務められました。そして現在も、多摩霊園探鳥会、多摩川丸子橋上流探鳥会のリーダーとしてご活躍でいらっしゃいます。
そして、今週はこの方にもご一緒いただきます。伊佐ホームズの伊佐裕社長です。よろしくお願い致します。実は、中村さんのお家は伊佐ホームズが手がけられたということなのですよね?
伊佐:そうですね、もう10年近くになりましょうか。
中村:そうですね、来年ちょうど10年目になります。
伊佐:どこかご不便などございませんか?
中村:おかげさまで心地よく暮らせております。
伊佐:ありがとうございます。私、前回、前々回とお話聞いておりましてね、私は、お盆はですね、福岡に帰っていました。ちょうど私の家が海岸の近くなのですよ、百道の海岸で。で、そこにやはり川がありましてね、河口周辺を歩くのが好きでしてね。やはり今はですね、白鷺が多いのですよ、河口周辺で。あれが、川が引いていきますとね。引くというのは干潮になってくると、じっとこう川面を見つめながらですね、動かず、動くときは一瞬なのですよ。それとか別の鳥はですね、バタバタと水面を叩きながら、魚をおどかして捕るのですよね。さまざまな鳥たちの、なんでしょうねぇ、漁といいますかね、餌の取り方のうまさに大変感じ入ってですね、観るのが楽しみでしてね。なかなかあの辺というのは皆かしこいですよね。
中村:九州はとてもいい探鳥地が多くて、渡り鳥もたくさん通過していきますしね。それから、福岡のほうの海岸線もいいですし、それから有明海の干潟なんかもとっても野鳥の多い場所ですよね。
伊佐:私はね、前回、前々回ですか。昆虫がお好きだった中村さんの少年時代…私も一緒なのですよ。夜、田舎の私の親せきの家にいっておったら、電球にカブトムシが飛んできたのですよ。それが今までに見たことのない、形であり、力強い形でしてね。そこから一気に虫好きになりましてね。それで私も櫟の木にですね、カナブンとか、クワガタとか、カブトとかですね、蝶とかですね、蜂だとか、さまざまな生き物が群がっているのですよね。あれ見るとね、胸が躍ってですね。私はいつも、学校に行く前に、朝昆虫採集に行って学校に行くというような少年でした。あの驚きの胸の高鳴りはですね、もうどうしようもないですね。
中村:そうですよね。昆虫は野鳥と違った綺麗さがあるので、本当ドキドキしますよね。
司会:中村さんはそんな少年時代でいらしたのですか?
中村:そうですね。まぁ近くに日比谷公園があったものですから。もうほとんど、日比谷公園とか愛宕神社とか芝公園なんかが私のテリトリーで。
伊佐:あそこは山の斜面ですもんよね?(昆虫がたくさん)おったのでしょうね?
中村:そうですね。昔はアオダイショウなんかもいましたしね。
司会:そうですか。じゃあ、場所は違えどとても自然に親しんだ少年時代をおふたりとも過ごされたわけですよね。
伊佐:それと私は今こうやって建築というデザインの仕事をしていましてね、鳥の色の配色ほど凄いものはないなと思ってですね。一羽一羽の配色っていうのは凄いですよね。どっちかというと反対色が多いですよね、それぞれ。補色関係の色が、それぞれ…腹が赤だったら背がこうだとかですね。共色であるよりはどちらかというと補色関係の色の配色が多いなと思ってみるのですが。
中村:今、社長が思い浮かべたのは、たぶん河原のカワセミのことを思い浮かべたのだと思うのですけど。近年都内でもカワセミに会える率が増えてきまして。ですけども、カワセミの場合は背中がブルーで、仮面がオレンジ色っぽいですよね。上から見たときにブルーが水面に溶け込んで見つけにくくなっている側面があるし、下から見ると、きっとオレンジ色が空に映って、獲物の魚からは見えにくいような、そんなふうになっているのですよね。
伊佐:はぁ~。そういうことですか。
中村:でも、カワセミのブルーはね、青の色素ではなくて、構造色といいまして。光が羽毛にあたってそれが乱反射して、たまたま青い波長だけ出ている…そういう色なんですよね。なので、鳥には青い色素はないものですから、おもしろいです。だから見る角度によっていろいろな色に見えたりするので、そこもまた楽しいですよね。
伊佐:それと私ね、鳥の隊列といいますかね、群れで飛びますよね。あれ、群れでおりながらなんと美しい並び方といいますかね、あの辺の差異というのはどういうふうになっているのかなっていつも疑問があるのですよ。
中村:なるほど。鳥もね、飛ぶのにはエネルギーが必要なので、なるべくエネルギーを省エネで飛びたいわけなのですけれど、一羽の大きな鳥が飛ぶとその翼の翼端部分に渦が出来るのです。その渦に乗るとほんの数パーセントだけ、斜め後ろにいれば、ほんの数パーセントだけ省エネ飛行が出来るので、それで斜め後ろ、斜め後ろっていうふうになって、ああいう鉤型になるのですけどね。
司会:それを本能で知っているという…
中村:そういうことですね。
伊佐:きれいですよね、あれ。雁が渡っている群れも美しいし、さまざまですよね。
中村:代表的な、おっしゃった雁というのは、今の名前でいうと、マガンなんか多いですけども。あと多摩川なんかでは、カワウなんかがそういう飛び方をしますのでね。
伊佐:凄いですね。
司会:あの先ほど、「最近見られる確率が多くなった」というようなことをおっしゃったのですけれど。なんかどんどん自然が破壊されてきて「鳥減っているのかな」なんて私なんか思ったのですが、そんなこともないですか?
中村:そうですね。野鳥は「自然環境のバロメーター」ということで、野鳥がたくさんの種類とたくさんの個体がいるということが、自然が健康であるバロメーターになっているのですけれども。総じて特に渡り鳥なんかは、世界的に数を今減らしているのですけど、でもよーくよく見ると、例えばカワセミとかキツツキの仲間のコゲラとか、あとは21世紀に入って、エナガなんかは、この世田谷区、東京ではかえって増えているのですよね。そういう面白い現象もあるのです。
伊佐:話変わるのですがね。私は建築やるのに、森と取り組んで…。まぁ森を取り組みだしたのは、森林環境が大変悪化しているということで。森の豊かさはやっぱり土壌なのですよね。土の力なのです。それがすべて水も水源も関係あるしですね。私も仕事をしながら、社会とのつながり、環境とのつながりを考えた仕事をしたいなと思っていましてね。そういう点では、単なるものを作るのではなくて、地球に適したといいますか、環境に応じたものをしたいなと思ってですね。お住まいになって例えばご自宅の中で、ですね、こう…人間って違和感があるというのはよくないですよね。自然環境もそうだと思うのですけど。どうですか、当社がやった住まいの中で、このへんの材料的なこととか…。
中村:おかげさまで、今家にいると林の中にいるような、すがすがしさを感じるのですが。シンボルツリーのやまぼうしの木が家じゅうから眺められて、そのやまぼうしの木が夏場大きな日陰を作ってくれる。秋になると実がなって鳥や虫がやってきたりとか。冬になると葉っぱが落ちて陽射しを家の中まで入れてくれる、そういう楽しみがあります。
伊佐:そうですか。嬉しいですね、そんなお話を聞くと。
中村:あと木がね、日本の杉やヒノキで、限定で作っていただいたものですから。それで壁なんかは、漆喰や珪藻土なんかの自然素材で作ってもらって。なので、物理的にいって自分の周り・家の周りがもう自然に、林の中にいるのと同じような状態なので、そこらへんはとっても爽やかな家だと思っていますね。
伊佐:現代の住宅はね、ある面じゃ建材メーカーの建材の羅列なのですよね。やはり建材とかというのは、工業製品というのは経年的変化すると劣化してきて、なにかこう人間に違和感があるのですが、天然素材というのは自分と同じ、人間と同じように経年変化が美しくなっていくというか。そういうことによって、人間の心の居り場所があるような気がするのですよね。だから私、家を作ってみて、野鳥の会の中村さんのお宅ということで、非常に自然に敏感な方のお宅ということで、ですね、緊張感も後で覚えました。怖いくらいでした。今もそうですけどね、それは。
司会:中村さんは田園調布にお住まいでいらっしゃいますね。そういった家の中の林で鳥が迷い込んでくることはないですか?
中村:実はね、実のなる木も何本か植えてもらっているのですけどね、それを食べに来たりとかするのですけれども。おすすめとしては、庭に水盤を置いて、浅い、1cm2cmの浅い水を毎日取り替えると鳥が喜んで水浴びにやってくるのですよ。なので、部屋からバードウォッチングが出来てしまう。
司会:へぇ~、じゃあお部屋から楽しんでいらっしゃると。
中村:そうですね。それで、やまぼうしの木には2年続けてメジロが営巣したことがありましてね。その時は嬉しくて、嬉しくて、カーテン締めっぱなしで。鳥に刺激しないようにカーテン締めっぱなしで カーテンの陰からちらっと覗くという感じで、そういう楽しみがありました。
司会:田園調布ではどんな鳥が見られるのですか?
中村:世田谷区も同じですけど、緑地が多いですので、スズメから始まって、シジュウカラ、メジロ、世田谷区の鳥のオナガ、あと冬になって、ツグミとか。あとは冬鳥のスターのジョウビタキなんかが来てくれたときはとっても嬉しいですよね。あの、紋がついている紋付鳥なんて言いますけどね。
司会:鳥の好きな方のお宅だとわかって入ってこられているのではないかしら、なんて思いますけど(笑)
伊佐:表札が出ているのでは(笑)
司会:そうですね(笑)また伊佐社長も森に出かけられることが多いので、また楽しみも少し増えられたのではないでしょうか。
伊佐:そうですね、また新しい角度で野鳥と接したいと思います。
司会:今月のゲスト・日本野鳥の会・東京 元代表の 中村一也さん、そして今週は伊佐ホームズの伊佐裕社長にもお話していただきました。お二人、どうもありがとうございました。
中村・伊佐:ありがとうございました。
渋澤寿一さん

司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、農学博士・NPO法人共存の森ネットワーク理事長、渋澤寿一さんです。よろしくお願い致します。渋澤さんは長年にわたって、山村を中心とした地域づくりに貢献し、森林文化保全の教育、啓発、人材育成の第一人者でいらっしゃいます。
そして、今週はこの方にもご一緒いただきます。伊佐ホームズの伊佐裕社長です。よろしくお願い致します。さて、お二人の出会いのところから、まずはお話しいただいてもよろしいですか?
伊佐:はい。あの大変嬉しいことなんでですね…。このひと月前ですよね?渋澤さんと(出会ったの)は。その後、杯も1回重ねましてね。それは森のこと、暮らしのこと、あるいは私がやっている林業、建築のこと、さまざま話題は飛んだのですけど。どうでしょう、今自分が生きているテーマを語り合って飲むほど、幸せなことないですよ。その日は酒も進みましてね。私今日渋澤さんとお会いして今日3回目だと思うのですけどね、まぁ旧知の間柄って勝手に大先生を思ってしまっていて。まぁ、年齢も近いのですよ。私のほうが2つ上で。1回、2回、3回と先生のお話を聞いていまして、同じ時代を生きてきたのだなと思って。あの頃、学生運動のことは大変話題がありますよね。その後、人生も変わった人間もいますよね、あの学生運動で。先生はそれから農業に行かれたということで。何でしょう、一番経済と違う道というか。私はやはり総合商社というところに入って、さまざまな開発を会社自体がやってきたのですが。私はやはり自分の仕事を通してですね、もう少し地に足がついた仕事をしたいというか。本来が絵描き志望だった人間が、ある面じゃ総合商社という産業のほうにいったわけですから、家づくりというのはやはり産業といっても、もっと違うところあるかなという。まぁ、文明じゃなくて文化というかな。一棟一棟、だから大事なことがあるのでですね、そこから始めて、もし事業が成立するならば、というふうに思ったのです。それが成立するならば素晴らしいなと思ったし、その前に本当の家を一軒一軒作ろうというのが、私のスピードだ。ある意味では渋澤さんがおっしゃった「農業」ですよね。「農学」じゃなくて。それがどう成立するかというのは、渋澤さんもおっしゃっていましたけど、いまだに私にもわかりませんがね、まぁそれをやってきて今に至っているというふうで…。
司会:今のお話でどうでしょう?やっぱり共感するようなところが、渋澤さんおあり…ですか?
渋澤: 私はもともと農業でスタートした人間なのですけどね。その、山と農との違いというのは、農業というのは、種をまいてその年ほとんどのものが収穫できるのですよ。ですから、自分が植物と話たりとか、自分が土と話すことが基本的に農業の一番重要なことなのです。ところが山の木というのは、植えて、そうですね…、大きい木で切れるようになるのが80年、杉の木で。本当は250年くらい経った木のほうがいいですし、彼らの寿命は1500年とか、縄文杉は7000年と言われています。で、つまり、年代が長いのです。そうするとどんなにひとりの、林業が凄くよく出来る、機械が使えて、森のことをよく知っていてというような人を育てても、その人が働けるのが、まぁ20代から60代までの40年間です。で、その人を10人繋いでいかないと400年の森を作ることが出来ないのですよ。で、やっぱり人が繋いできたもの、それを建物という形にしながら、木の寿命からそして建物の寿命に変えてやって、そしてその中で人の暮らしを溶け込ませながら繋いできたのがね、日本の森なのです。で、人と人とをどうつなぎ合わせて、あるいは世代と世代をどうつなぎ合わせていくのかということが、昔の人たち、日本人たちはとても考えて、いろんなことをやってきた。それが今、私たちが、木の家に住める、あるいは木の器を使えるという結果なのですけど、そこまで私たちは考えないでね、森と付き合っているという…。
司会:それってものすごくありがたいという思いがしますね。
伊佐:一番最初にお会いした時にですね、渋澤さんは大変広大なる世界を知っておられての「森」だったのです。私は産業としての林業について新しい取り組みをしていますよということで、だいぶ教えられました。そういう点では、私なんて言うのは、森の中の一部に今入ってきたという。しかしどこかで経済が成り立つことが暮らしを支えるし、経済の在り方もやはり生態系に適うような伐採方法を我々でしたら出来るのじゃないかという可能性を持っているということもお伝えしてですね。そういう点では先生と出会ってですよ、渋澤さんと出会って、我々のやっていることがもっと大きく導かれるなと思って。
それとあの、渋澤さん。私初めて会った山の人たちが、それぞれ素晴らしかったのですよ。私、「山の衆」と呼んでいるのですよ。確かにね、私、山の方々みているとそんなに収入があるわけではないのですよ。…慌てていないのですよ、目が。で、一人の中心人物はですね、大学の仏文学科を出て、お父様の困苦を見てですね、決意して林業をそのまま継いで。で、この方が、埼玉県の、いわゆる日本の公園の父と呼ばれる本多静六さんの記念すべき第一回目を貰った方なのです。そして、非常に哲学も語り、文学を語る。もう一方もですね、自分の家が火災になったので、慌てて浪人しているとき、学業を辞めて帰ったそうなのです。で、二人ともそういうアクシデントがあったことが今の林業を支えてきて、ほんの少し伊佐ホームズとの取組みによってですね、林業が変わって、新しい林業のあり方が、道が開かれたら自分の人生喜びだと、いうようなことを今おっしゃてですね。そういう点では、標高400メートルところが生活の中心ですよ。高いところでは700メートルの秩父地方で栃本に住んでいる人もいます。やはりいいそうですよ、そこから見る毎日の山の景色が。何事にも代えられない価値をお持ちなのですよね。経済は二の次でしょうけど。でも大事にする必要はあると思いますけど、両立を我々も何らかの形で。今後渋澤さん、いろんなことをお教え頂いてですね、我々はビジネスで来た方ですから…お願いしたいなと。
渋澤: 日本の森って約4割が、人が植えた森なのです。で、その4割が、当初は孫子の代には大金持ちになれるぞと思って、みんな夢を持って植えたのです。本当に大変な思いをして、戦後。だけど、金にならないぞとなった瞬間にみんな見捨てた森が約4割。それが、人間が植えた森なので、まずは人間が手入れしなければいけない。あと6割は、炭だとか、薪だとか、人間が使ってきた森です。で、こっちのほうが、少し余裕があります。だけど、両方とも人間がこの50年間見捨ててきた相手であることは事実なのです。ですから少なくとも、人間が植えたものを人間の経済のシステムの中でも回って、100年前に植えてくれた木を使って、自分たちの100年後の子孫が住む家を建てるということがどんなにありがたいことかというのが、家の価値として皆が持つようにならないと、自分のためだけの家の価値じゃないのですよね、家って。
司会:伊佐社長がおっしゃられた、今森に生きている、その素晴らしい人たちが、次にどんなものを残していくかということも大事であるし、また外から見ている私たちの意識も変えていかなければいけないということですよね。
伊佐:だから渋澤さんがおっしゃっている、その高校生を山に連れて行くという活動は素晴らしいなと思って。やっぱり理解する人を増やして裾野を広げたいというふうに思いますよね。
司会:今回このラジオをお聞きになったリスナーの皆さんの中には、そういった考えがちょっと目覚めたという方もいらっしゃるのじゃないかなと思うのですけれど。お二人はどうでしょう?目指すものというのは、たぶん共通のところがおありなんじゃないかなと思うのですが?
伊佐:本当にご指導を頂いて、これから同じ道を歩かせていただきたいですね、私は。
渋澤: だけど、僕たちは先祖が植えたものを相手にしている商売ですから、それを次の代にどう繋いでいけるかということが必死で、自分たちが何をやるかということよりも、ここまで繋がれていたバトンをね、この50年でバトンを落としていいのかどうか。僕はいけないと思うのですよ。で、何とか必死の思いで繋ぐ。で、それは、ひとつは高校生たちの教育、あるいは高校生だけじゃない教育という分野もあるでしょうし、それから経済という分野がそれはやはりすごく重要なことです。やっぱり経済は世界の共通言語ですから、とてもわかりやすいし、とても語りやすい。で、いろいろな文化ですとか、あるいは健康ですとか、その中でそのストレスをなくすとか、いろいろな要素で森をつないでいかないと、ただ金にならないから手を入れませんよ、水害が来てから国がどうにかしてくださいと言う話はね、ないなと思います。
伊佐:おっしゃる通りだと思います。あと我々は、杉の木を伐採したあとはカエデの木を植樹していっていましてね、混合林になっていっているのですが。針葉樹よりは、いわゆる広葉樹のほうが、保水力が大変高いというふうに聞いておりますので、そういう点では大事な作業かなと思っていまして。
司会:その取り組みはどうですか、渋澤さん。
渋澤: あの、自然界にひとつの作物だけが全部生えているっていうことはありえないのですよね。農業もそうなのです。お米だけ作っているというのは、本当は自然から見たらとっても異常な行為なのですよ。やっぱり山も多様な植物が生えるのが、健全なもともとの山です。で、高いところを占有する木、中くらい、それから地面のところ、それから根っこもそれと同じように下に張っていく。そういう山にね、やはり戻したいなと思いますね。
司会:そういうもともと山なのですもんね。日本の山は恵まれた山なのですものね。 どうぞ、その山を守るために、そして私たちの生き方を考えさせていただくためにも、お二人にはますますご活躍いただければと思っております。
渋澤: ありがとうございます。
司会:今週は、農学博士、NPO法人共存の森ネットワーク理事長 渋澤寿一さん、そして伊佐ホームズの伊佐裕社長にもお話していただきました。ありがとうございました。
渋澤・伊佐:ありがとうございました。
市村禎二郎さん
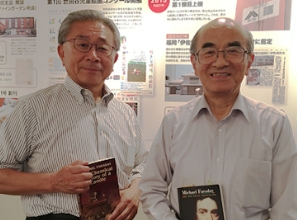
司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、東京工業大学名誉教授の市村禎二郎さんです。よろしくお願い致します。市村禎二郎さん、1945年山口県のご出身。東京工業大学大学院理工学研究科で、理学博士号を取得され、以来40年以上に渡って、物理化学、特に光科学の研究を国内外で精力的に行っていらっしゃいました。2010年には東京工業大学を定年退職され、現在は東京工業大学 教育・国際連携本部 特命教授として、化学・技術の普及、振興に尽力されています。
そして、今月3週目の今日はこの方にもご一緒いただきます。伊佐ホームズ・伊佐裕社長です。よろしくお願い致します。まずは伊佐社長。先週、先々週と市村さんのお話をお聞きになったと思いますが、いかがでしたか?
伊佐:いやぁ私ね、先生。もう先生とお付き合いが8年超えたと思うのですよ、お会いしてから。それまで先生いつもね、にこやかに来られるのでですね。そして、エジプトのお話を聞いたり、お酒飲んだりしてですね、このあいだ。非常に親しみ深い先生でおられたのですけれども、1回、2回と、先生の研究のご略歴聞きましてね。大変今日はもう恐くてですね。虎の尾を踏むような思いで今日来ておりましてですね。第一私は大変な文系人間、仕事は建築というのはまぁ技術なのですがね。本来私人間学から入ってきた感じがするのです、自分で。住居学といいますか。人間の心をどうするかという問題、それから歴史とどうつながっているのかという問題 から私は入ってきて、建築の仕事をやっているというような人間なのでですね。まぁ幸いにもうちの会社のほとんどが皆理系の人間なのでですね、私の文系的な発想をこう、理系の人間がうまく処理しているというか。で、構築していっているという会社なのですが。非常に私は高校時代、物理・化学なんていうのは、それから英語数学、全部避けて通っていたのでですね、いや、この1,2回の話を聞くまでね、私物理と化学のね、境目がわからなかったのですよ。
司会:あぁ。物理と化学の境目…、そういわれると、私もあれって思っちゃいますねぇ。先生、その境目ってあるのですか?
市村:はい、境目ってありますね。物理っていうのは物質自体が変わらないのですけど、化学は必ず変化する、化けるという。
司会:なるほど。
市村:水が例えば、蒸気だとか氷になるのは、同じ水に変わらないのですけども、それが例えば電気を流すと、電気分解で水素と酸素になる。要するに完全に物質が変わりますので、これは化学ですね。状態が水から蒸気になっても、氷になっても、これは変わりませんので、これは物理現象ですね。
司会:なるほど~。その二人が出会われたきっかけというのはどういうことだったのでしょうか?
市村:実はですね、私が終の棲家を探しているときに、いろんなところを訪ねて行ったのですけれども、結局ですね、伊佐ホームズがいいんじゃないかと私の妻が言いまして。で、実はですね、伊佐社長の出身校がですね、私の妻が高校生の時に一時期通っていた福岡の修猷館高校であったということも、そのことも何らかのご縁かもしれないなと思っていますね。
伊佐:驚きましたね。あとでわかったことですよね、お会いした後に。ちょうど私の1年先輩でおられた。
市村:1、2年の時にいて。まぁ私は山口の出身なのですけども、家内は一時福岡にいて。そのあとまた山口に移って、結果的には私と同じ山口高校の卒業をするのですけどね。
伊佐:先生、私、改めて今から、科学、勉強したいなと思いますね。
市村:あ、そうですか。それだったら、いくらでも、いくらでも(笑)
伊佐:特に色彩の話なんて言うのは実に面白かったですね。色の捉え方っていうのは。大変な精密機械というか、人間が。機械なのですか?これ、精密化学機械?
市村:はい、精密化学機械って言っていいと思いますね。だから例えば、モノを食べてエネルギーにして活動すると。先ほど言われた人間学の中の、人間の構造のほうの部分なのですけども、これらもすべて化学反応でして。ですから、でんぷん質とかを食べるとそれが酵素の働きで、たかだか人間の体温の温度で酸化反応が起こって、そこで出てくる、結合が変わる度ごとに、エネルギーが出てきますので、そのエネルギーをうまく使って、我々人間の体温を維持して、それで活動しているというわけですので、人間が生きているということ自身がすべて化学反応ですので。
伊佐:あらゆる元素は、かなりいろいろな役割を果たしているということですね。地球上の存在する元素は。
市村:特に重要なのは、人間の生命が海から出てきたといっていますけれども、そうすると海の中には、ありとあらゆる、金を含めてすべての元素が入っていますので、その中の適当なものをつかって、いろんな器官が出来ていますので、ほとんどのものがですね、ミネラルっていうのですけれど、そういうものが必ずですね、大切な働きをしているのですね、人間活動の中で。
伊佐:昨年秋に、私ども倉本聰さんの講演会を二子玉川でやったのですけれども。「伊佐さん、伊佐さんたちは木の建築だから幹を大事にするでしょ?実は葉っぱが大事なのだよ」と言われたのですよ。やっぱり葉っぱの光合成によって生命が存続しているというか。その大事さを聞きましてね。我々も二酸化炭素を出して、酸素を取って生命のサイクルがあるし。この宇宙の神秘さを知りますとね、もう驚愕しますね、本当に。
市村:そうですね。この宇宙の中というのは、たかだか化学の世界から言うと、100以下ぐらいの元素しかないのですけれども、それがうまい具合にいろいろ組み合わさって、ものすごいたくさんの、少なくとも2千500万種類くらいの物質が知られていますので、そういうふうなものがうまく循環しながら、宇宙の中で循環をしながら、その中で人間の営みというのが組み込まれているわけですね。不思議ですね、そういうのは。
伊佐:そう思いますとね、住宅もですよ、先生。あまりにも便利だという住宅というのは大変なる欠陥かなという気もするわけですよ。不自由さがあるとかですね、あるいは自然のいろいろな気候の変動がわかるというようなこと、相反する問題点を我々常に考えていかないといかんなというふうに思ってしまうのですよ。人間がそこにいることによって、快適だけだったら、これは今それを求める目的になってしまっているのですがね。それは考えますね、私も。
市村:ただ今の、これから高齢化社会を迎えるにあたって、そういう時にその快適さというものと、今言われた、伊佐さんが言われた、むしろあまりにもなんていうか、快適じゃなくて、少しでも不自由さがあったほうが、人間にとってはいいのではないかなと…。なかなか考えさせられる問題ですね。
伊佐:例えばね、私よく山に登るので、山小屋に泊まると雨の音がするのですよね。なんて良いかなと思うのですよ。で、今住宅で、雨の音がする屋根があるかどうか。それが騒音と思うのか、それこそそれを音楽と思うのかというか。さまざま、快適さの中には毒もあるなというふうに思うので。機能とか、いろいろなことは快適性が必要でしょうけれども、文化としての住宅というかな。その問題はやはり考えながらいきたいなというふうに、つくづく元素のありよう、あるもののすべてがこう生かされているといいますかね。だからあまりにも機能優先、文明優先じゃなくて。文明があって、文化があるような。文化のほうが優位にあるような住宅を作りたいとなというふうに思う次第ですよね。
市村:私もだから、伊佐さんに家を建ててもらって。今言った、文化のところまで行くかどうかわからないですけれども、残念ながら私が購入した土地というのがですね、細長いのですね。しかも狭いのですね。それで設計の段階であれこれと話し合って。「もうこれだったら路地風の建物にするしかないね。」って言われて。路地風ってわかります?京都のほうにあるのですけれども、通りに面している玄関がなくて、ぐるっと回りこむと、ちょうど細くなっていますのでその太字のところに玄関を持ってきていただいて。それで入ったところにですね、「地窓」というのがあるのですけれども、地窓を通してですね、自然を感じることが出来るのですね、緑のね。それがもう非常に気に入っているのですけれども。そういうものもちゃんといれてもらったりとか。あとは狭いながらもデッキと坪庭も作っていただきまして。孫たちがですね、夏には夕涼みをしながらちょっとした花火も楽しむことができるというところで。あと二階建てなのですけれども、一番本当は実は気に入っているのは、2階のところからですね、東南の角部屋なのですけれども、外がよく見えて。幸いなことに視界が比較的開けていまして、周りの家の家屋があまり気にならないのですね。そういう意味ではだから非常にラッキーだったかなと。
伊佐:だいぶ先生、愛着が出てこられましたか?
市村:そうですね。それはやっぱり家というのは住まなきゃダメなので。住んでみないとわかりませんね。
伊佐:先生、私ね、設計条件が厳しい方が結果的にいいものが出来るなというふうに思うのですよ。
市村:あぁ、そうですか。いやもう、本当に設計者の方と何度も話し合って、やっと…。
司会:それで、先ほど伊佐社長のお話にあった、エジプトに行かれてる間にお家が出来たのですよね?もう伊佐ホームズさんにおまかせというか、すごい信頼のある関係が結ばれていたのかなと。
市村:そうです。もう完全に。
司会:それはやっぱり、今お話を聞いていてもそうですが、お二人に、本物志向だったりとか、いろいろな繋がりを大事にするとか、共通の部分がたくさんおありだったからなのじゃないかな、なんてことも私感じて聞いておりました。
お二人のお話をもっともっと聞きたいところなのですが、すみません、今週もまたお時間になってしまいまして。「わたし歳時記」今月のゲスト、東京工業大学名誉教授の市村禎二郎さん、そして今週は伊佐裕社長にも加わっていただきました。ありがとうとございました。
市村・伊佐:ありがとうございました。
小泉俊己さん

司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、彫刻家の小泉俊己さんです。よろしくお願い致します。小泉さん、1958年東京都でお生まれになって、多摩美術大学彫刻科を卒業し、同大学の大学院美術研究科を修了されて、アーティスト活動に入られました。そして現在母校の多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻教授としてお務めでいらっしゃいます。
そして、今月3週目の今日はこの方にもご登場いただきます。伊佐ホームズの伊佐裕社長です。どうぞよろしくお願い致します。
社長は、美術のほうはお得意でいらっしゃいますので、いろいろなお話が聞けるかなと思いますが、先週・先々週と、小泉さんのお話をお聞きになって、いかがでしたでしょうか?
伊佐:はい、私はね、先生、こうやってお相手するのが大変楽しみでして。やっぱりこういろいろな人生の局面を歩いてこられた、先生の場合は、そして作品が生まれているわけでして。私ね、国分寺崖線のことを先生随分仰っているのですが、あれはやはり、在るものが接点ですよね、削られていくところと在るものが存在するところと。人間も生と死があるように、そこの中に生きざまがあったり、美しさがあったり。醜さもありますよね。先生は常にそのことを意識されているなというふうに、それが造形に及んできているのかなというふうに思ったりですね。大変感銘深く聞いておりましてですね。
私は、先生のご自宅、5年前ですか、やらせていただいて緊張しましたよ、うちの会社じゃあ。第一ね、彫刻家の美意識の中で耐えられるかなということで。
司会:伊佐ホームズさんが小泉さんのお家を手掛けられたと?
伊佐:それがね、全面リフォームだったんですよ。リフォームというね、一つの前提条件も厳しいものがあるわけですよ。それも先生ご夫妻は、二人ともアーティストですからね。果たしてうちの社員でやれるかなっていう…怖かったですよ。
小泉:ちょっと相続した家だったものですから、それがまだ築年が4年くらいだったので。ちょっとこれを潰して…というのは出来なかったということと。でもその限られた条件でもどういうふうに動かせるかっていうのが、ちょっと楽しみでもあったんですよね。で、実は僕、伊佐ホームズさんというのは、大学が今八王子と世田谷・上野毛にあるのですれども、僕は助手時代に、よく上野毛に行くときに伊佐ホームズさんの本社、そこの脇をよく通るときがあって。で、なんかイメージとして、いい建物だし、伊佐というのが頭に残っていて。で、ちょうど家をどうにかしなきゃと思った時に、それを思い出して。ちょっとネットで検索をしたら、すごいテイストが合ったんですね。でもリフォームだし、こんな立派な会社に頼むの、どうなんだろうっていうふうに、実はこっちはビビりながらですね。
伊佐:とんでもない、先生!何をおっしゃっているのですか(笑)
小泉:「あの、リフォームってやっていらっしゃいます?」って言って、入った記憶があります。
司会:お互いにちょっとびくびくしながら…(笑)
伊佐:ちょうど先生、あれが30年経ったのですよ。まぁ30年経っても今でも愛おしいなと思いましてですね。あの建物自体が売ろうと思って作ったんじゃないというか。先生の作品もそうだと思いますが、売ることを意識したらどうしても卑しいと思うんですよね。私はやっぱり豪華とか貧しいとかではなくて、なんでしょう、モノの存在があればそれが豊かだと思うのですよね。
司会:実際に小泉さんのお家を手掛けるときになにか、こういうことをしてほしいとかご要望とかってあったのですか?
伊佐:ちょっとうちの担当がそのへんは大分、よく限定された条件の中で、なんとかクリエイティブなことを出来たというふうに私も思いましたね。前は忘れてしまいました、前の建物を。
司会:あ、なるほど。
小泉:だいたい来るお客さん、友人、お客さんがリフォームだというふうには思ってないです。だから僕はわざわざ外回り連れていって、「ほら、ここがね、昔。ここからが新しい」とか。
伊佐:いい話ですな(笑)
小泉:もちろん建築ですから、お金のこともありますし、初め全部希望を入れていったら、工務店さんのほうから「もうそれはリフォームじゃないよ、だったら建て直しなさい」って怒られちゃって(笑)でもじゃあもう一回そこで「そうだ、リフォームだった」と思い直して、もう一回話してですね。よかったと思いますよ、結果的には。
伊佐:うちの社員の場合ですね、そうやっていろいろな難しい課題を越えながら、みんなが力をつけていくのですよね、これが。
小泉:あとは、やっぱりすごい話を聞いてくださるし。で、僕も話ながら、「この人はこういうことを考えているのだろうな、じゃあ多分、次打ち合わせの時はこういう話持ってくるかな」とか、そんなことでお互いこうやり取りをしながら、最後はもう「施主」と「会社」という考えではなくて、なんか…
司会:同志みたいな?
小泉:正直言って、お酒も酌み交わしながら、とか。そんなことで、お互いの人間性がわかりつつ、物事が作られていくので、やっぱり作品と同じ。まさに伊佐ホームズさんにとっては作品でしょうから、凄くきもちよく…、でもドキドキもしましたけどね。
司会:一番小泉さんが住まいとしてこだわられたところというのはどういうところだったのですか?
小泉:やっぱりその質感って当然あります。室内の質感というのはありますし。リフォームですから、ある間取りというのは制限を受けてしまいますけれども、でもやっぱりあと光ですかね。それがちょうど2階増築した部分、本当に明かり取りだけのスペースですけれども、1坪くらいのスペースが、何にもないけれども、その何にも無さがとても癒されるというか。
司会:なるほど。なんか豊かさを感じますね。
小泉:そうですね。あとは随分植栽も…
伊佐:だいぶ豊かになったでしょうね。先生、私ですね、いい建物でも作品でもやっぱり無があって、無の奥に、なんでしょう…、時間が更新されていくようなやはり移ろいがあるというか。無というのは、止まっていると思うのですが、いいものは、止まりながら実は流れているのだよっていうような、ものだろうと思うのですよ、たぶん。すべてのことはたぶん。で、先生の鉄の表現、鉄って決してこう美しいとは思わないですよね。でも、あの素材の正直な表情というのに、我々心を打たれるわけで。そういう点では、やはり私は、住宅は、空間と素材と。もちろん色彩もありますよね。そして、光と風だと思うんですけど。
小泉:僕らが一番伊佐さんで気に入っているのは、先ほど素材って言いましたけれど。で、社長仰るように、いい素材は、時間が経って、いわゆるエイジングがかかって、それぞれの、その時その時で、すべての時にその素材の良さが現われるというか。新しいときは新しい良さがあるし、5年経ち10年経って、その素材の良さが現われる素材を使われているんだろうなというのが初めあったので、まさに今5年経って、自分は毎日見ていますから、本当はエイジングで古くなっている部分もあるんでしょうけれど、実は全然古くなっている感じしないんですよね。 まぁ、掃除もよくしてますけれど(笑)
伊佐:あぁ、そうですか?先生が、ですか?奥様が?
小泉:いやいやふたりで。じゃなくて、女房が主体で、僕が手伝っている(笑)
伊佐:そうですか、問題ありません(笑)。でも私はね、こうやってお客様と改めてこういう出会いの場があって。で、先生ともね、酒も酌み交わさせていただいているのでですね。僕は仕事が終わって、認めていただいてね、酒が飲めるほどうれしいものはないですよ。出来るまではね。認めていただくまでは、やっぱり酒を飲みましょうとは言えないですよね。それは、私は、まず仕事が終わって、どうだったかなと思ってご一緒したいなというのが…
司会:それが社長のけじめでもあるのですね?
伊佐:そうですね。途中では、ちょっと…私の矜恃です、それは。
司会:今はもう本当に楽しく時間を過ごされるお仲間に…
小泉:まぁ、お仲間といったらあれですけどね。
伊佐:いやーもう…(笑)
司会:でも本当に、私今手元に、伊佐ホームズさんが出している冊子の中に、小泉さんのお家が移っている写真を持っているのですけれども。
伊佐:そうですね、第9号でしたね。
司会:光がすごく綺麗に取り入れられているし、その中に飾られている小泉さんの作品がまたすごく生きる家でもあるなと思うのですが、こんなふうに時間をかけてお互いによく分かっていくと、こういう素晴らしい作品が出来ていく、のですね?
小泉:そうですね、だからまだある意味、製作途中かもしれないですよね。先ほど言った植栽もそれは当たり前のことですけど、時間が経っても成長していく、変わってゆくという意味では、まだ未完かもしれないですし。それは、僕が、僕らが中心となって今また家を育てているということになるかもしれないですけれど。
伊佐:そしてまた家が人を育てるのですよ。これ私、お互いなんだと思うのですよ。
司会:それが本物ですよね。素敵です。
今日は本当に素敵なお話をお二人にお聞かせいただきました。あっという間にお時間になってしまって、このあとどうぞゆっくりまたお時間を別にして頂いて…(笑)
「わたし歳時記」今月のゲスト、彫刻家の小泉俊己さん、そして今週は伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきました。ありがとうとございました。
小泉・伊佐:ありがとうございました。
木村龍治さん
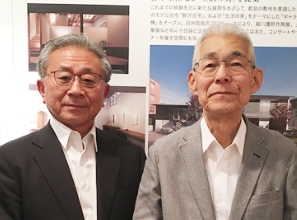
司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、気象学者の木村龍治さんです。どうぞよろしくお願い致します。そして今週はこの方にもご一緒していただこうと思います。伊佐ホームズの伊佐裕社長です。よろしくお願い致します。
さて、お二人の出会いなどのお話もお聞きしたいのですけれども、社長、先週までのお話聞いていて、何かいろいろ感じるところが…?
伊佐:はい、興味深く聞かせていただきましてね。先生の退職後の新しい生活の、我々お手伝いしたということで。まぁご自宅ですよ?「観天望気」とおっしゃった、自然を観察されるということを、もう1回研究室から外に出るという場所を作らせていただいたという。大変我々にとっては、大変な節目に先生のお手伝いをしたなと思います。
司会:先生の新しいお宅を手掛けたのが伊佐ホームズさんだということですね。
伊佐:先生ね、私もですね、気象では2つあるのですよ。私は福岡の生まれなんですね。福岡っていうのは、冬は結構雪が降るのですよ。どっちかというと金沢と似てるんですよね。で、雪が降った朝が嬉しくてですね。それから私天気図を見るのが好きになったんですよ。いわゆる西高東低の気圧配置になるのが。で、寒冷前線とか見るのが好きだったんですよ、先生。で、その頃私もですね、日本に気象大学があるというのをその頃知りましてね。「あぁ、気象大学っていいなあ」と思った…ちょっと私、中学校時代の思いがありました。
木村:そうですか。気象大は今もあるのですよ。気象大学校というのは、気象庁に所属している大学でですね。そこに…大学に入ると気象庁の職員として扱われるというか、そこで気象の勉強をして、その後気象庁に就職すると。いわば、気象庁の養成機関。それが、気象大学校といいましてね。今でもありますよ。
伊佐:そうですか。ちょうど私どもの小学校の横がですね、気象台がありましてね。いつも気球が上がっていたのですよ。で、上がり方がね、風が強い時はまたこう動くわけでしてね…。
それと先生、もう一つありました。高校時代に阿蘇山に行きましてね、絵を描きに。で、早朝、大観峰というですね、外輪山の一角に大変眺望のいいところがあるんですよ。いわゆる阿蘇五岳を見下ろすところで。朝、雲海が凄かったんですよ。これがね、朝日が昇るころからだんだん雲海が動き出してですね、いわゆる熊本の下流の方に流れ出すのですよ。その動きが見事でしてね。そういう点で、私は幼少のころの雪のことと、絵を描くために行った阿蘇の雲の動きには感動しましたね。 まぁでも先生はそういうことから始まって、それを学問としてずっとやってこられた…尊いご一生を送られて、また今も現役だなと思うのですが。
司会:先生は今、そういうお話をお聞きになってどうですか?
木村:そうですね。私も子供のころからそういう自然に興味があって。私の場合はそれがそのまま大人になってしまって。その興味がですね、ずっと持続して大人になってしまったという、そういう感じがしますね。
伊佐:日本では雨がいろんな降り方をしますよね。確かですね、雨の表現が600種類あるっていうのですよ。季節ごととか、降り方とか、その時の人の様子とか、暮らしの様子とか。あるいは農作業とか。どっちかというと、私は科学じゃなくて人間の営みのほうの雨を体感するのですけれども。先生はもっと大きく成り立ちのほうを見てこられたと思ってですね。
木村:成り立ちから言うと雨は2種類ある。それはザーッと降る雨と、しとしと降る雨。
これでメカニズムがひどく違います。だから集中豪雨なんかは、ざっと降る雨でして。それのひどいものが集中豪雨になるわけですね。それからあと何百種類も名前があると言われましたが、それはしとしと降る雨に多い。例えば、京都で「時雨」なんていいますよね。
伊佐:糸雨とかありますよね、微雨とか。
木村:えぇ。いろんな言葉で、そのしとしと降る雨が呼ばれると。
司会:そういった日本の…、これから6月になると梅雨に入っていきますけれども、 いろいろな気候の問題が、日本の住まいとかいろいろなところに関係しているのかなと思うのですが…。
伊佐:じゃあそのへんについては私が。
私も会社を作って30年になりますがね。鉄筋コンクリートの住宅に入った時と木造ではやはり体感の、感覚が違うのですよ。やはり湿度の感じ、状態が違うと思うのですけれど、そういう点では、私は人間の暮らし方から家づくりをしたようなほうで。どっちかというと科学的な方面から建築をやったのではなくて、暮らし屋から入ってきてそれを追求してきて今の会社があってですね。その中で随分近頃は、会社の技術的な開発も進んできてですね、大変いい形になったなと思うのですけど。ますます木の凄さを今感じたり、和紙の凄さとかですね、そういうものを機能的に作り上げていって、現代の住宅を作りたいなと思って。もうどっちかというと、私は暮らしからずっと今までやってきて。今そのへんの特性を生かした、素材を生かした、性能が高い住宅で美しいものを作りたいなと思ってですね。人間ってやっぱり正直なんですね。同じ自然界にいるもの同士の素材というのは、ピンとくるのですよね。どうしても鉄筋とか…まぁ鉄筋の成り立ちも本来は自然なのでしょうけど、こう空気の流通がないというか、息をしていないというものは、やはり体感的にすごく正直だと思いますね。
先生お暮らしはいかがですか?もう16年ですよね?
木村:大変ね、快適な家を作っていただきまして。
伊佐:そうですか、科学者の目で見られて…そうですか(笑)
木村:はい、完全バリアフリー。
伊佐:あの時からそうでしたか!
木村:えぇ。大変ありがたい、生活しやすい家で。エレベーターもつけていただきましてね。
伊佐:そうでしたね。あのころまだ珍しかったですよね。
木村:珍しかったですよね。でもエレベーターは大変便利だということは、今でもね、居間とか台所は3階にあるのですけど、1階から3階までエレベーターで買い物したものをみんな上げ下ろしが出来る…大変便利です。
司会:その3階に台所というのは、木村先生のご希望で作られたのですか?
木村:えぇ、こう…明るいところで住みたいなと思ってね。景色のいいね。そこで3階に今台所、それから食堂、キッチンがある家です。
伊佐:あの頃私どもから見ると、やっぱり先生の発想には驚くべきものがありました。
木村:いやいやいや、僕の発想じゃないですよ。それはデザインをしていただいた方の発想なんですけれど。カミさんはね、天守閣って呼ぶ。天守閣に住んでいるようだと。眺めがいいのですよ。
伊佐:そうですね、南の眺望が良いですよね。
木村:しかも家が小さいからまさに天守閣(笑)
伊佐:最上階で!
司会:それは街の眺めもそうですが、空の眺めもよさそうですねぇ。
木村:まぁ家の中からというよりはね、特別に空を観察する天文台みたいなものを作っていただいたのでね。そこでどうやって観察するかというと、一日中僕がそこに立って空を眺めるわけにはいかないので。そういうことはしないで、そこにビデオカメラを備え付けまして。そのビデオカメラはコマ撮りで朝から晩までだいたい10分くらいで空の動きを撮ってくれるんです。そこで朝起きたらビデオカメラをスイッチ入れて、あとは全然関係なく別の仕事をするわけです。で、夜になったらそれを回収するわけ。で、それをテレビで見ると10分でね、その日の朝から夜まで、空の景色がダーッとわかるんです。変化が。それを3年間繰り返しました。もちろんね、日によっては雨が降った日にはそういう観測は出来ないですし。それから快晴の日、雲一つない日もありまして。そういう日は朝から晩まで青空がずーっと出て変化が全くない、そういう日もあるわけですよ。
司会:それもまた楽しい?
木村:いや、楽しくない(笑)やっぱりね、楽しみを感じるのはいろいろ雲の変化…するですね。
司会:それを見てまた学問のほうに結びついていくことも?
木村:その通りです。
司会:そうですか。そういう話を聞いても、木村先生に学ぶことって多いですね、社長ねぇ?
伊佐:これでも、小学校の子供たちにね、先生、少し授業をやっていただいたらいいなぁと思うのですけど、いかがですか?課外授業で。
木村:いやぁ、もう随分やりました。小学校5年生で天気のことを学ぶのですよ。で、僕はボランティアで小学校に行ってですね。小学生相手に天気の話をね、随分しました。
伊佐:やっぱり学問の深い方がお話される授業とただ覚えたての授業とでは違うでしょうね。深さがある分だけ伝わり方が違うと思うのでですね。
司会:私もここまで毎週聞いてきて、本当に楽しくて仕方がないので。
木村:そうですか。
伊佐:私もね、初め難しい学問で、先生のお相手とはどういうことかなと思いましたがね、楽しいですなぁ。
司会:楽しいですよねぇ。実はもう一週今月はありますので、次週もまた先生に、さてどんなお話か次週まで考えたいと思いますが、お聞かせいただきたいと思います。
今月の「わたし歳時記」のゲスト、木村龍治さん、そして今週は伊佐ホームズの伊佐裕社長にもご一緒いただきました。お二方ありがとうとございました。
木村・伊佐:ありがとうございました。
涌井雅之さん
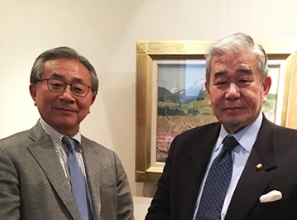
司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、造園家の涌井雅之さんです。どうぞよろしくお願い致します。涌井雅之さん、1945年神奈川県でお生まれになりました。東京農業大学農学部造園学科に進まれ、造園会社・石勝エクステリアを設立なさいました。先週のお話で、東急宮古島リゾートのお話も出てきましたが、たくさんのランドスケープデザイン手掛けていらっしゃいます。先週予告しましたように、3週目の今日はこの方にもご一緒いただこうと思います。伊佐ホームズの伊佐裕社長です。よろしくお願い致します。もう2週、いろんな涌井さんのお話をお聞きになって、社長いかがでしたか?
伊佐:まずですね、私大学時代あまり授業を受けていないんですよ。いやぁ、こういう先生と私出会っていたら自分が変わったなあと思いました。もう67になりますがね、しかし、今先生と出会って、お会いできて良かったなと本当に思いますね。私、去年の暮れでしたか、ある勉強会の懇親会で先生がいらっしゃるのを知ってですね、駆け寄りましてご挨拶しました。で、そのあとラジオの出演をお願いしたということで。もう前から先生のお名前は聞いておりましたし、学者さんであり、なんでしょう、現場主義者であり、大変な世界観をお持ちであり、人情家のようにもお人柄を感じましてね、こんな魅力的な方とお会いできてよかったなと思います。私は、大学時代は絵描きになりたいなと思っておりました。そして、しかしながら、私も建築に行きたいなと思いながら、数学が悪かったものですから。で、建設会社か不動産会社、どちらかに行こうと思ったんですよ。でも、どっちもつまらないなあと思ったんですよ。建設はハードだけのような気がしたし、不動産は平面だけだと。私、商社の都市開発部を選びましてね、商社に行くと、もっとこう、ダイナミックに全体像を描けないかなという、経済とか文化とかからんだ開発が出来ないかなということで選んだんですよ。で、14年間街づくりをやっていましたけれども、その頃は土地が値上がりましてね。ある面じゃ数字が合えば売れるわけですから、本質論じゃなかったんですよ。私もね、やはり人生は一作でもいいものを作って死んでいきたいと思っていましたのでね。一作の建築をしたいと…絵を描くように、一作の建築を作りたいと思って、何も知らずに飛び出したわけで。先生は27歳、私は37歳のスタートでしたし。先生のその後の人生の広大無辺さというのは我々知るところでありますが。私は、ちょうど今年で30年になりました。
涌井:ご立派ですねぇ。
伊佐:今、その一棟一棟の家がですね、街並みを作るきっかけになればなという願いを持って今建築をしていまして。建築はやはり公のものですよね。絵を描く目から見ますとね、自然の中に、人工物でもいいんですよ、絵を描きたくなるなという人工物はね、人工物と自然がマッチしているんですよ。どうも違和感がある人工物はね、描きたくないんですよ。
涌井:非常によくわかります。あの、私は伊佐さんとお目にかかってですね、まぁわかりやすく言うとね、普通ね、住宅だとか不動産をやっている人というのは、ある種の、なんていうかな、脂ぎった、ギトギトした雰囲気があるんですけどね。この方には全くそれがないんですよね。あれっと思ってね。それで、私は実は二子玉川に石勝エクステリアの本社があった時代、しょっちゅう伊佐さんの瀬田のところの…あそこを通って。で、佇まいを感じたんですね。で、なんでこんな佇まいを感じるような家が出来るのかなというふうに思いながらですね、お目にかかって初めて、あぁこの人は多分右脳の方なんだと。つまり、わかりやすく言うと、アーティストなんだと、いうふうに思いましてね。それでね、なんとなく魅力を感じてですね、今日ここの場にいるという感じですね。
司会:まさにぴったりの表現でした。社長。
伊佐:いやあ、もうありがたい言葉を頂戴しましたけれどねぇ。私は家内とよく話してたんですよ。生まれ変わったら造園の仕事いいよなって話をしたことがあったんですよ。たった畳1畳でも宇宙ができるわけですからね。また、先生のようなあれだけの会場の構想を練られたりですね、まぁ大きさ問わずですよね。それと、私、日本の美というのはですね、非常に閑静な美しさというか、何もない中の美しさをやはり求めたいなというふうに思って。華美じゃないもの。で、今回田園都市線のあざみ野に「田園都市の家」というテーマで住宅を作ったんですが、これは普通を極めた住宅と思っていましてね。本当に普通の良さを追求していきたいなとずっと思っていまして、それがいろんな普遍的な生活というか、が、あるかなと思って。 先生、これ私結構自信作なんですよ。
涌井:是非見させていただきたい。
伊佐:是非ひ見ていただきたいと思いますし。これから私も一棟一棟から街が作れるきっかけになればという思いで人生を歩んでいきたいなと思っています。
涌井:余計なことを言うようですけどね。実は昔の日本人というのはですね、地図という言葉ありますでしょう。あのね、図を描いてきたのかというとね、そうではないんですね。大陸国家というのはですね、非常に大草原とか大砂漠とかね、そういう状況なものですから、図を描かないと不安なんですよ。だから中国の人はですね、壁をね、模様で埋め尽くさなければ不安なの。イスラム教徒もそうです。
伊佐:そうかそうか、すごいことですね。
涌井:ですね?日本人はですね、非常にさまざまな風景の多様性や生き物の多様性があるものだから、図を描いていったらね、喧嘩しちゃうんですよ。それで地をどうするかって考えるわけです。地図の地。つまりね、そこで働く能力というのは引き算なんですよ。
司会:なるほど。日本の美に繋がりました、今。
涌井:そうそう。で、いわゆる足し算ではない、引き算。多様性の中に、そのいかに引き算をしながら最低限の、風景を邪魔しないものを作る。しかも美しいと。その佇まいを伊佐さんに僕は見たんです。
伊佐:それはもう恐れ多いことで、もう恥ずかしいです。本当に
涌井:だから、どちらかというと建築というのは、すぐ図に行っちゃうんだけども、実は地を考える建築というのはそう多くなくて これは日本のね、日本美の本質なんです。だからしつらえという言葉があるでしょう。しつらえというのは、日本の家はですね、日々のものは全部押し入れで片付くんですよ。それから月のものは納戸なんですよ。年に使うものはね、蔵なんですよ。で、収納するわけね。それで、その中からそれぞれ舞台の装置みたいに、月並みの行事とか、その雰囲気に合わせてモノを運んでくるから、結果引き算なんですよ。
伊佐:そうですね。
涌井:いやいや、そうですねって、そういうものを作っておられるじゃないですか!
伊佐:いやいや、そこまでのことは思ってもなかったですけどね。
司会:自然に出来てきたということですね、社長ね。
涌井:だからそれはね、右脳なんですよね。
司会:なるほど、素晴らしい。もう必然の中で生まれきたものなんですね。
涌井:そうですね、それでね、この右脳って僕言っているけれどもね、技術ってね、イノベーションがなきゃ技術じゃないでしょ?だけどね、それはね、技術というのはですね、イノベーションをする、その体系があればイノベーション出来るんですよ。でも、一番大事なことはクリエイションが出来るかどうかなんですよ。で、クリエイションというのはね、まさにアートなんですよ。だから、リチャード・フロリダという有名な都市計画学者がいるんですが、彼がこういうことを言っていますね。テクノロジーというのはよく考えてみると、そのクリエイションのサブセットじゃないかと。つまり、イノベーションというのは、クリエイションの結果なんだと。
で、大変僭越ですけど、伊佐さんの、いろんな伊佐ホームズを見ていると、日本の数寄屋のようなところに媚びているわけでもないし、現代の生活というものと合わせながら、でもね、余白をたくさん作ってね、どうぞお客様自身がそれをね、しつらえてくださいという、こういう感じがある…違います?
伊佐:そうですね。 いや~、先生のお話を聞けば聞くほど教えられますね。私もですね、サイエンスが後でついていくわけで、証明されるだけであって。先にアートがないとモノはやはり出来ないですよね。
涌井:これね、ちゃんとね、安心してください。アインシュタインが言っているんですよ。
伊佐:あぁ、そうですか!(笑)
涌井:knowledgeよりimaginationって。
伊佐:これからの社会、よけいそれが必要とされるというふうに聞きますけど。
涌井:そうです。おっしゃる通りです。
伊佐:感動を与える仕事をして、それが、サイエンスが支えていくというか、そういう仕事をやりたいなと思いますよね。
涌井:でもやっぱり、それは伊佐さんの、その…。ある種伝統とイノベーションというのはセットですから。伊佐さんが、博多で非常に地域に影響力のある豪商の系譜におられた。つまり、しょっている伝統というのと、そこから脱却したいとかですね、そういうイノベーションとね、この相克の中に出てきたんじゃないですかね。勝手に言ってますけど(笑)
伊佐:いや、確かに自分の内面ではそういうものを背負いながら、外に開こうとしてきた人生がありますよね。
涌井:あぁ、やっぱりそうですね。占い師みたいなことを言ってすいません。
伊佐:やっぱり葛藤がないとモノが生まれないなというふうには思いますよね。先生が1回目でしょうか、先生の生い立ちの中でもいろいろな内的な…とおっしゃった。内的なことがないとやはり話になりませんよね。
司会:本当に共通する思いというのがたくさんおありでいらっしゃいますね~。何かタッグを組んだらもっとすごいことになるような…。
伊佐:いや、もう本当に先生のご指導の中で仕事をやりたいですね。
司会:ぜひぜひ。「田園都市」という言葉がひとつ今回キーワードになったような気も致しますけれども、また来週も本当は伊佐社長にもお聞きしたいところなんですが、まだまだ涌井さんにお話足りないところがおありなんじゃないかなと…
涌井:伊佐さんは来週来ないんですか?
司会:はい、対談は今週だけなんですけれども。
涌井:じゃあこれでやめたらいいじゃないですか。
司会:いやいや(笑)是非来週もまたお話をお聞かせいただきたいと思います。
伊佐:(笑)
司会:ラジオで、是非社長またお聞きいただければと思います(笑)
「わたし歳時記」の今月のゲスト、造園家の涌井雅之さん、そして今週は伊佐ホームズの伊佐裕社長にもご一緒いただきました。ありがとうとございました。
涌井・伊佐:ありがとうございました。
服部紀和さん

司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、建築家の服部紀和さんです。どうぞよろしくお願い致します。もう何度もご紹介しておりますが、大学卒業後、竹中工務店に就職されて、一貫して設計部門、そして副社長も務められました。数々のオフィスビル手掛けられまして、現在はアトリエKIWA、主宰なさっています。そんな中で、最終的には住宅だというところに思いが至ったというお話ですが、今月四週目の今日、この方にもご一緒していただきたいと思います。伊佐ホームズ 伊佐裕社長です。どうぞよろしくお願い致します。
お話を聞いていて、伊佐社長とはたくさん通じるところがおありだったと思うんですが、まず出会い、どんなところからだったのでしょうか?
服部:「私、最初の出会いはですね、伊佐社長というお人に出会ったわけじゃないんですね。私が初めて出会ったのは瀬田の本社。今の本社ですね。これは住宅の構えをしている、非常に落ち着いた…私は名建築だと思っておりますけども。あの前を車で通りがかって、こうなんか、ふっと…こんなところにただならぬ建築、気配を感じさせる建物があるなということで、また戻ってきて車をとめて。そして勝手に門をたたいたんですね。そんなことはめったにないんですけれども。そしたら、たまたまそこに伊佐社長ご自身がおられましてね。それから、初めてお会いしたのに建築談義・デザイン談義をするようなこと、かなり長く、熱っぽくお話して。これが最初の出会いです。
伊佐:「いや本当、服部さんとは長くなりましたね。今日はゲストにありがとうございます。私、この放送を1回、2回、3回と聞かせていただきましてね、服部さんご自身の運のお強さもあったと思いますし、出会いがそれぞれ凄いなと思って。服部さんはその中でも、清家先生との出会い、バンコク、イランでのこと。もともと建築で初めが集合住宅という、人間にとって一番肌触りの大事なところの仕事をされたということが、服部さんの立派な建築がずっと続いていった由来があるような気がしておりまして。その中で私は光栄にも服部さんとこういうご縁を頂戴しまして。
服部:「とんでもない.
伊佐:「いや、本当に。この5年はともに旅行をしたり…。
服部:「あはは…。そうでしたね。
伊佐:「九州の唐津にいい旅館がありまして。大変建築もいいし、器もいいし、料理もいいし、景色もいいんですよ。そこに波の音がしましてね、それを聞きながら語るとですね、とめどなく話が続くんですよ。服部さんと私も、年齢もお立場も違うわけですがね、こうやって兄貴のようにお付き合いをさせていただいて。この3回聞かせていただいて、本当に私も嬉しく思っております。
服部:「いえいえ。今ね、伊佐社長から直々にもったいないお言葉を頂きまして。私こそね、伊佐さんのように経営者であられて、大勢の社員、立派な職人さんたちも含めて、抱えられて。そういう方にはなかなかたどり着けない面があるなと、私こそね、尊敬しているんですよ。
伊佐:「ちょうど私、丸紅で14年間、どちらかというと街づくりやってましてね。その頃は20万坪の宅地造成とかを2人で担当するんですよ。で、何百戸という住宅を作っていくわけですよ。その頃はもう土地が値上がっているわけですから、土地の力で売れていくんでですね、正直建物に対する意識が薄いわけで。そういう中でわたしはどこかで疑問が出てきたのは、人間として住む家、あるいは私はどうかという問題。自分への疑問があった。私はどうも仕事をやるにしても、自分はどうなんだろうという、社会のことでも、自分に戻るような、いつも考え方をするんですけれど。それというのも服部さん、私には2つの小さい頃思い出がありましてね。モノの存在というか、生意気言いますと。私が生まれる半年前に、母は私の兄を亡くしているんですよ。その半年後に私が生まれていることと。私が母の実家に行った時に、餅つきで大騒ぎしましてね、私。私が小学校の1年から幼稚園だったと思いますが。その晩祖母が倒れましてね、結果的には年が明けた1月4日に亡くなったんですよ。私はずっと罪の意識がありましたね、正直。そういう点で、やっぱり人間の…なんでしょう、生と死については少し意識が高くてですね。モノの存在、あるものがどうあるかということについては、考えたりしているうちに絵を描きだして。モノをつかむというか、存在を絵から私は迫ったような気がしてですね。だんだんにその存在を確認しないと人生がないような、いつも衝動がありました。それが結果的には、前の会社を辞めて、家づくり、本来の家とは何ぞやということで来て。その点で服部さんは、住宅から竹中のお仕事を進められて。常にその辺の、自分の空間とかという置き換えがあったというような気がするんでよすね。多くはみんな、自分を捨てて、その世界に入ってしまうんですけれども。自分があって物を作っていることこそ、長く残る仕事に至るような、私は気がしているんですけども、いかがですか?
服部:「そうですね、今のお話のように、原点が絵とかね、そういうところであることも共通項でありますし、何より伊佐さんは建築、住宅、住まい、家ですね。そういったものに対して、夢を長らくお持ちになって。ただ夢で終わらずに実現しようというところに、一番の私は尊敬の念をもってるわけでありますけど。今のお話のように、ただ夢を追い続ける「九州男児」と私は勝手に伊佐さんを表しているわけでありますけども。それぐらいですね、一本骨が通っている。これは私にはないところ。今、年は私のほうが上ですけれども、教わりたいと常々思っているんですね。ただ共通する価値観というのは凄くあって、それは当然建築への思い、住宅への思いもそうですけれども、本物志向であること。それから美しいものに対する非常に敏感な反応、美しいものはありとあらゆるものですが。それからですね、日本を大切にする、つまりこれがアイデンティティと横文字になるんでしょうけども。日本・日本人・自分たちを大事にするという、この3つのことがね、根底にあるということ。非常に共通項であると。それをありきたりでありますけど、言うならば「温故知新」といいますかね。きちっと、今までの先人たちの文化とかそういうものをふまえて、それでこう住宅を…、よい住宅・よい住まいを作っていこうという、伊佐さんには少なからず私も、少しでもご一緒に歩ければいいなというのが今の思いです。
司会:「服部さんは、今は伊佐ホームズのシニアアドバイザーでもいらっしゃるわけですよね。
伊佐:「そうですね、ちょうど去年の4月に就任頂いて。素晴らしい勉強会、ご指導を頂いています。
服部:「これはね、伊佐ホームズには大変優秀な若い建築家・モノづくりの人たちがたくさんいましてね。そういう人たちに、私の年だから経験だけはたくさんある、それからいろいろ思ってきたことで、思い通りに行かなかったことも正直言ってある。そういうものをですね、ありのままに伊佐ホームズの若い方々に伝えられれば…。それが、もうそれしか私は仕事ではないんですけどね。アドバイザーというとちょっと語弊があるかと自分では思っています。
司会:「そういうご関係でいらっしゃるというのも、お二人が目指すものというか、追うものが一緒だということになるんでしょうか?
伊佐:「そうですね。ちょうど先月の2月17日に、田園都市線のあざみ野で発表した「田園都市の家」というのは、デザインと性能と環境を両立させた住宅なんですね。私のこの仕事の人生で、44年になりますが、その中でようやく念願のものが出来たという出発点に立ったという思いでおります。それは新しい住宅のフォルムがあるし、エネルギー問題があるしですね、環境問題を考えた家ということで。それでちょっと皮肉を言いますとね、近頃プレハブメーカーさん、どっちかというと工業化した住宅なんですが、ある会社は「私の家」というのをキャッチフレーズにしていますね。それからあるメーカーは「生きる家」という。非常にマスの企業が、人間の内心に入ってきたなという感じがしております。本来はそういうことだと思うんですけれども。工業化した住宅の大手企業がですよ、そういう意識を持ちだしたという、今、時代の変化を感じますね。まぁ我々は出発点がそういうところから始まったわけですから、今はそれを性能とかいろいろなことを整備していきたいなと思って。より本物の時代の戦いというか、知っていただく時代かなと思いますけれど、服部さんいかがですか?
服部:「やっぱり本物だけが残る。見かけの華美というのかな、そういうものは、その時だけの商売の道具でしかないと思うんですね。商品じゃないか。本当に残る、そこで人が住んでですね、健全な生活が営まれるというのは、都会・田舎に関わらず、やっぱり本物だけが残っていくんじゃないかというふうに、それを目指したいですね。
伊佐:「そうですね。そう我々もなりたいもので。
司会:「本物を目指すお二人がこれからまたどんなことをしていかれるのか、私も楽しみにさせていただきたいと思います。まだまだお話をお聞きしたいところなのですが、申し訳ありません。お時間になってしまいましたので、今週はこのへんで終わりということにさせていただければと思います。
わたし歳時記」今月のゲスト、建築家の服部紀和さん、そして伊佐ホームズの伊佐裕社長にもご一緒いただきました。お二人ありがとうとございました。
服部・伊佐:ありがとうございました。
椎野潤さん

司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、早稲田大学元教授・工学博士の椎野潤さんです。どうぞよろしくお願い致します。椎野さんは日本のロジスティックス研究の第一人者でいらっしゃいますが、日本の林業・木材産業の発展にも力を入れていらっしゃいます。
そこで、今日はこの方にもご一緒いただきます。伊佐ホームズ 伊佐裕社長です。どうぞよろしくお願い致します。お二人の出会いはどんなきっかけだったのでしょうか?
伊佐:私がちょうど今年30年になるんですね、創業して。創業して30年の中で、今から14、5年前から非常に建築業について疑問を持ちました。いろいろな不合理な取引だとか、無駄があったりということで。それで私は、建設業を合理的にしたいなという…、いいものを合理的に作りたいという、いいものを作るための合理性といいますか。その中でひとつの材料の調達だとかですね、そういうことに意識がまずいきました。その中で山との取組み等が始まってきたわけですけども。その中で椎野先生という方が日本のロジスティックスの権威者でおられるということで、ある仲間の紹介で早稲田大学を訪ねました。私は、卒業は慶応なんですが…まぁ早稲田を落ちたほうなんですよ、私は(笑)
それで、その日からですね、先生には胸襟を開いて、まるで我が子のように先生に扱っていただいたように思います。それ以来ですね、もう12年くらいになりましょうか。この間、2年くらいは、先生はご年齢もいかれましたんで、勉強会はやめたんですけれども、約10年間、毎月「椎野塾」という、国の木のことを考える「国木会」と命名しましてね、椎野先生を囲む勉強会を当社でやってまいりました。
司会:「国木会」という名前なんですね。
伊佐:杉のことを国木と言うくらい、スギの木は日本人にとって大事な木なんですよね。
そういう名前で、毎月1回当社でやってきた。その中で、ロジスティックスからサプライチェーンということに、これはまたバリューチェーンという、お互いが生かしあう、そして価値を持つというか…。その中で特に山の問題に突き当たりまして、大変山が、林業が低迷している。ついては森林の荒廃になっているわけでしてですね。そういう点で、我々それまでは、木材は九州の熊本から調達していたんですね。これ、走行距離トラック1000kmを超えているわけで、環境問題から言ってもCO2排出量が大変高いわけでして。その中で地域を見直そうということで、地域の中で一番先端的な林業家と出逢ったのが秩父だったんですね。そして、秩父ではかなりITを駆使してですね、新しい林業を始めておられました。それによって我々も、会社も、非常に新しい生き方をするようになりました。
この5年前に住宅のほうで特許をとりました。これは「校倉」という住宅なんですが、設計方法で特許をとりまして。生活スタイルが変わってもですね、家族の変化に応じて住まい方が対応できるという。我々、材料のことも考えながら、住宅のありようも考え出してですね、そんなふうにして先生との出会いが当社を変えたという…。
司会:なるほど。
伊佐:で、正月に先生から頂戴した詩を皆さんにご紹介しながら、先生のお人となりを知っていただければと思います。
正月、先生からブログで頂戴しまして。ある方からの詩のようなんですけど。
先導者たちへ
先導者=高い志をもって時代を先駆ける者は、
常に孤独である。
漆黒の闇夜に一艘の小船を漕ぎだし、
大海を渡らんとする如き、
そういう孤独をきっとみな、
味わっているはずである。
人の先に立って、未踏の明日を切り拓こうとすることとは、
そのような勇気ある精神の戦いである。
松明に火を灯し舳先に掲げよう。
この一点の小さな明かりが、
思いかけず、遥か遠くにある同じ志の者を励ますとしたら、
やがて次々と狼煙のように伝播して、
煌めく数多の松明が、満天に輝く星空になるとき、
先導者=高い志を持って時代を先駆ける者は
消して孤独ではない。
これは、社員にも何度も私読んで聞かせたんですけれども。先生ご自身がこういう方でおられて、我々も迷っていた工務店の経営、あるいはサプライチェーンの凄みを我々知ってですね、今我々にとっては、林業家も製材所もプレカット会社もですね、お互い儲かるための取引の駆け引きをするんじゃなくて、全体で利益を考え、無駄を省き、そしてお互いが存続しようという…大変美しいといいますか。
私ですね、1回目・2回目と先生の放送を聞いておりまして、やはり心の美しさがいろいろな矛盾に気づき、技術が開発され、市場を作ったりしていくのかなと。私やはり知識というか頭脳よりは、そういう志・心の美しさが新しい未来を開いていく原動力かなというふうに1回目・2回目と聞いておりましてね。先生の場合、大変分野が広くいらっしゃって。他の分野から見られたこの業界のありようというか。その中で私は一番遅れているこの木材業界・建設業界についてですね、本当に私は偉大な師匠とお会いした。遅れてる人間ほど、気づくというか。そういう点では、林業もそうなんでね。そういう未来を作れるような林業のありよう、あるいは建設業で美しい住宅ができるような仕組みづくりが、私の今、仕事になっています。先生長くなりまして、まだまだ足りない不肖の弟子ですが、折々またこれからもお教えいただきたいと思いますが。
椎野:私も実は伊佐さんとお会いできたのが大きかったんですよね。何かというと、本当に美しい日本の家、今世界の人たちがあこがれています。俄かに富裕層が増えていまして、日本の家にあこがれています。昔は世界一の教会を作りたがっていたんだよね、ヨーロッパが中心のときは。今は日本の家を作ろうとしています。そういうときに実物がなきゃだめですよ。そりゃあできないですよ。それでね、そういう伊佐さんが、私がやろうとした、まさにサプライチェーンの合理化のようなことで、合理的な建設業をつくりたいと、学ばれたいと来られたんです。で、私は、今それをすぐ指導すると、伊佐さんがここまで作ったこの会社を潰すなと思ったんです。だからそれは絶対してはならない。だから相当辛抱強く、我慢して、急がないことだったんです。何故かというと、伊佐さんのところにはね、14人の素晴らしいデザイナーがいたんですよ。いわゆる感覚ですよ、感性です。このようなサプライチェーンをどんどんやっていきますと、最後は感性なんですよ。それがなきゃ世界でね、本当に日本の住宅が凄いといわれるには、感性がある作品じゃないきゃだめなんですよ。
伊佐:先生、ちょっと話が飛ぶんですがね、ドイツではフォレスターという、森の管理者があるそうで、弁護士・医者に続く社会的な評価を受けるという。ドイツというのはそういう点ではいつも我々の師匠でありますし。私も森に入ったら幸せなんですよね。これで経済が成り立ってですよ、文化が存続していくような地域を作れるように、やはり都市と繋がるというか。で、一番大事なのはやっぱり木の文化にお客様に共感いただくというマーケットを作ることだと思ってですね、ちょうど2月17日に田園都市線のほうで美しい木の住宅で、「田園都市の家」という木を活かした、外壁の美しい住宅がオープンします。これ全部秩父の木から持ってきて。有効活用なんですよ、これは。
椎野:いやー、この伊佐さんの芸術性というのは凄いです。それを大事にしなきゃいけない。それは日本人の特性です。江戸時代の版画が、ヨーロッパの画家たちがみんな共感したでしょ?あれは原点ですから。家こそ日本人の原点です。それを大事にしなきゃ。それがモノになって、絵じゃなくて、モノになったのが家ですから。
伊佐:そうですね。
椎野:もうひとつは生活なんです。家ということは生活なんです、生活の器ですから。生活が、本当に幸せになっていく生活とは何かということ。それを実現するのが家ですから。それを考えるのが、家を建てるときですから。それもね、実は私の、この今のサプライチェーンのをやれば、一番最初は、家を建てたいという人が何をどういう生活をしたい、どういう家を作りたいかが厳重で、それから山に行って、最後にまた家を建てるところに、建物に行かなきゃ…こう輪になって、最上流と最下流が家なんです。
司会:本当に根っこにあるのは、私たちの生活そのものということなんですね。
椎野:それが大事なところなんですよね。
司会:バランスがものすごく大事だなということが今お話を聞いていてわかりました。
今日はとても深い話をお二人にして頂きました。ありがとうございました。
今月のゲスト、早稲田大学 元教授 工学博士の椎野潤さん、そして伊佐ホームズの伊佐裕社長にも伺いました。お二人どうもありがとうとございました。
伊佐:先生、ありがとうございました。
横田尭さん

司会:「わたし歳時記」今月のゲストは、松本記念音楽迎賓館 館長の横田堯さんです。どうぞよろしくお願い致します。松本記念音楽迎賓館、二子玉川駅からバスで20分くらいのところ。世田谷区・岡本の閑静な住宅街の中にある音楽施設。横田さんは8年前からこちらの館長でいらっしゃいます。
そして、今週は伊佐ホームズ 伊佐裕社長にも加わっていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
伊佐社長、先週まで3週にわたってラジオお聞きいただいたと思うんですが、いかがでしたか?
伊佐:私、音楽ということで、非常に私にとっては苦手な世界だったんですけど、回を重ねるごとに引き込まれていきましたね。特に私は、自分も創業者なんで、パイオニアを築かれた松本望さんがどういう胸中があってこういう事業をされたかなということに大変関心もありましたし、大企業とかサラリーマン企業ではこういう開館はないと思うんですよ。オーナーの思いがあるからこうやって記念館があると思うんですね。やっぱり自分の商売の道具ではなくて、こうあってほしいという社会への思いとか人への思いがおありだっただろうと思うんですよ。そのへんを本当お聞きしたいなと思ってですね。ましてや、音楽だけじゃなくて環境問題とかもされたりして、素晴らしいなと思いますね。
横田:ありがとございます。
司会:横田さんは今、松本さんの思いを継いで館長をしてらっしゃるんですよね。
横田:そのつもりで頑張っております。おそらく松本望が生きていたらこういうふうにしただろうと思うことを、微力ながらですね、私は館長として繋いでやっていこうと思って日々やっておるんですけれども。とにかく人望のあった方ですからね。そういう意味では発明とか、ちょっとしたいたずらだとか…例えば、ゴルフのクラブに、パターに真ん中に穴を開けて、ちょうどゴルフボールが挟まるんですね。そうすると体を曲げずに、クラブで拾って次に行けると。そういうことを作って見せて皆に喜んでもらう、そんなことをしてたようなんで…。
司会:遊び心がおありだったんですね。
横田:遊び心ですね。遊び心と、本当に壁を作らずに人と接する、そういう人だったようですね。
伊佐:神戸のお生まれですよね。
横田:神戸ですね。けっこう牧師さんの息子さんだったので。それも清貧な牧師さんのお子さんだったので、とても生活には苦労して育ったそうです。それで、あちらこちらに奉公に行きながら、そこでいろんなことを身に着けていった…多分可愛がられて、いろいろ教えてもらったと思うんですね。で、まぁそういうことで覚えも早くて。
伊佐:私はちょうど今年が創業して30年という年なんですよ。
横田:おめでとうございます。
伊佐:で、事業というよりも美しい家を作りたいという一心で進めてきて。当社ギャラリーを持っていましてね、そこは、家の中には生活があるわけですから、高級とか安いとかじゃなくて、良い豊かな生活のシーンを再現したギャラリーを持ちましてね。そういう点では、物心の問題を一体化して、こう私は表現したいと思ってですね。それが社会に繋がっていくような仕事をしたいと思って。
横田:すばらしいですね。
伊佐:特に木の文化には、私も大変関心があってですね、木の美しさを中心にうちは建築をやってきた。近頃は森の問題について大変関心を持って、森を再生したいと思って林業とも取り組んだりして。だから、ただ住宅という物質を作るのではなくて、そこから始まる精神世界とか社会とのつながりとかを改善しながら事業をしていきたい。という点では、領域が広くなってきた気かするんです。たまたま私が雇われ社長じゃなくて、自分で創業した人間だからそうやって自分の思う方向に走って行ってるように思うんですけれども。それが僕は、新しい…なんでしょう、今後の時代のありようを、住宅業界で開けたらなというふうに思ってましてですね。そういう点で大変パイオニアの、これだけ会社にされた松本さんの、創業者のですね、望さんの生き方についてはまだまだ知りたいなと思いますし、館長とのこういうご縁でですね、今後ともいろいろなお話を教えていただきたいと思っています。
横田:森林が良くないと水もよくなりませんし。ですから、人間が生きていくための基本ですよね。木の良さというのはね。
司会:また、パイオニア時代は木についても研究されたというふうなお話も前出てきましたけれども…。
横田:私自身ですね?
司会:はい、そういったところで木にも関心が、横田さんもおありでいらっしゃいますもんねぇ。
横田:あぁ、ございますね。
伊佐:木材と音響ですよね。大変な深い領域ですよね、それは。
横田:そうですね。
司会:そして、邸宅のほうも、もしかしたら社長、ご興味がおありじゃないかなあと…
伊佐:素晴らしい景観を取り入れられた建物ですよね。
司会:それがすべて、邸宅の在り方と音楽の在り方と全部一体になってあそこで皆さんに楽しんで頂ける空間になっているわけですものねぇ。
横田:そうですね。まず建物が豪華なものですからなかなか足を踏み入れにくいところありますが…
伊佐:そうですよ(笑)
横田:一歩入ればというところで…(笑)とても撮影なんかも多いので。
司会:あぁ、そうですか。
横田:はい、素敵だと言っていただくので、そこの中にまた音楽があふれてくるようにしてありますので、まぁご満足いただけて…というふうに思っておりますけどね。
伊佐:話ちょっと戻りますがね、ある木材の専門家が、木材繊維の中で一番極小な部分が「セルロースナノファイバー」っていうんですよ。「セルロースナノファイバー」。千分の一ミリの単位なんですね。この細胞の組織が一番美しいっていうんですよ、世の細胞の中で。で、私ですね、美とサイエンスはイコールだと思うんですよ。だから美しいものには必ずサイエンスがあると思うんですよ。そんなふうに聞きましてね、たぶん音響の問題もそういう材質の中にある、一つの秘められた自然の摂理の構成。音響というのは大変関心があります、私も。
横田:キーワードはやっぱり自然ということだと思うんですけどね。無理なものとかね、いじりまわしたものではない良さですよね。
伊佐:私も建築を見ましてね、自己が出すぎた建築って嫌だなと思うんですよね。おのずから出来上がったものしたいなというふうに思うんです。自然の細胞の結晶なんですね、それは。やっぱり我が強いというかなぁ、そういう思いが強いと、どうしても異常な部分があると感じられましてね。やっぱりおのずから成るものに仕上げたいというのが私の念願ですね、仕事として。
司会:そのへんについては横田館長、同じような思いをお持ちですか?
横田:そうですね。おかげさまで、松本記念音楽迎賓館、パーティーでも使えるんですが、ある著名な音楽家のお誕生日祝いに使われたことがあります。その主賓が、ちょっと不便ですから、正直言って。「どうしてここまで来るのって思ったんですが、中に入ってみてすぐわかった。こんな温かい建物はない」と、おっしゃっていただいて。そういった思いが奇をてらわない良さですよね。高級な材質を使っていますけども、そういうことだけじゃなくて温かさがあるとおっしゃっていただいたので。
司会:そこに住まわれた、おそらく、松本さんのその温かさというのも残っているんじゃないのかな、そういう長い年月をかけて作られたものなんじゃないかなというような気も致しますが、お二人はいろんな意味で、木についてもそうですけれども、環境保全についても共通するところがたくさんおありですね。
伊佐:私も今年の「森の田んぼ」はお邪魔したいですね。
司会:はい、「みどりの講座」。2月にだいたいスケジュールが決まるということだったんですが、春夏冬と3回。もしかしたら、どうでしょう?今年は多くなるかもしれませんねぇ。
横田:伊佐ホームズさんバージョンでひとつ追加したらどうでしょう?
伊佐:是非是非、やりましょう。お願い致します。
司会:いいですね~。そしたら、伊佐ホームズから木のプロを連れて行っていただいて、また講座が一つできるかもしれませんね。
横田:これ、いいんじゃないですかね。
司会:あぁ、いいですね。素敵ですね。これ決まったらまた「わたし歳時記」でご案内をいれさせていただきたいと思います。さて、2018年・新しい年、最初の月のゲストとして横田さんにお越しいただきました。今年どんな年にしようか、館長、それから社長、どんな思いでいらっしゃるかお聞かせいただいてもいいですか?
横田:また館長を続けさせてもらうという前提で、ですね。創業者・松本望がこういうことをしただろうということをもっともっと実現していきたいと思っています。その思いを引き継ぐべき館長としましてはですね、どんな方にも喜んでいただけるということを運営の柱にしていきたいと思っています。それが私の若いころの体験から出来た自分の生きていく意味でもありますので、偉そうなことを言うんじゃなくて、本当に一人一人と接して、館を訪れる方が門を出ていかれる時には「あぁ音楽って本当に素晴らしいな」と思っていただける、あるいは自然の良さを味わっていただける、そういう運営の方針でやっていきたいと思っております。
伊佐:私は来月、2月17日に東急田園都市線のあざみ野で「田園都市の家」というのを新しくオープンします。これは木の美しさを存分に使った新しい形態の住宅です。これによって消費者が改めて木の文化に親しんでもらって。で、そういう需要拡大が、森の再生につながるような仕事をますますやっていきたいと思います。
司会:今年もお二人にとって良い年でありますように。私も楽しみが増えましたので、また館にも是非お邪魔させていただきたいと思います。
横田:是非。今度は門の外まで待っておりますので、是非お越し下さい(笑)
司会:ありがとうございます(笑)ちょっと足を踏み入れるのにドキドキしていたので、思い切っていきたいと思います。
伊佐:私は下の崖から登っていきましょうか(笑)
司会:じゃあご一緒します、よろしくお願いします(笑)今月のゲスト、松本記念音楽迎賓館 館長の横田尭さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。伊佐社長ありがとうございました。
伊佐:ありがとうございました。
杉本龍之さん
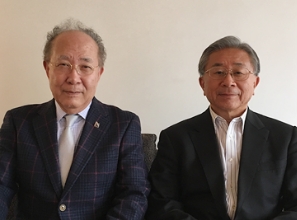
司会:わたし歳時記。今月のゲストは作曲家・杉本龍之さんです。どうぞよろしくお願い致します。そして、今月3週目、この方にもご一緒いただきます。伊佐ホームズ・伊佐裕社長です。どうぞよろしくお願い致します。
お二人は今日初対面でいらっしゃいますけれど、伊佐社長は先週・先々週と、番組をお聞き頂いたと思いますが、どんなイメージで…?
伊佐:えぇ、私ね。音楽の世界は遠いところの分野なんで、今日の対談は非常に苦手に思っていました。ただし1回目・2回目と、杉本先生のご幼少の頃の姿を浮かべながら、ご両親の姿とかあったりして。私は先生より5年遅れてこの世に生を受けているんですけれど、私の家も同じような商家で、うちは建材問屋だったです。似たような世界の中で、たぶん先生の中に、鋸を引く音とかですね、人間同士の声がしているご家庭だったと思うんですよ。私もまったくそうで。だから先生の中には木やりがあったと思うし。
杉本:そうですね。
伊佐:それがまぁ西洋の憧れでも、我々あの時代あったわけですから、近代音楽とか作曲とかに行かれたのかなと、勝手に推測したんです。
杉本:はい、そうですね。木遣りはもう小さいころから聞いていましたし。辰巳芸者の三味線の音とか、それから洲崎っていう遊郭があったんですけれども、まぁそういうところのお姉さんの…、私はその頃よくわかりませんから、でもお姉さんの香水のにおいとか、窓から手を振っているとか…そういうところで育ちましたから。
伊佐:そのやっぱり経験というのは、後できいてくるなと私思うんですよ。今の子供たちは、どうしてもマンションの場合、四角の空間。こう直角ですよね?全部。我々、昔の家屋とかまわりの風景とかは、非常に雑ぜんとしているか、いろんなものが不統一にあるというか。今の子供たちは、角々としたなかで生きてくるので、ましてやパソコンとかで、白か黒という決着つけているわけでしょ?○か×とかで。やっぱりデジタルの怖さというのを感じるわけでですね。それゆえに能力を発揮する子どももいるとは思うんですけどね。私どものね、あの頃の少年時代のことを思うと、景色が浮かびますよね。
杉本:そうですね。私もマンション住まいですけども、まず木がないですよね。マンションの中って。もうサッシもね、アルミだとか鉄だとか。その中にこう、障子なんかがあればいいんでしょうけど。
伊佐:木というのは、木目というのは全部違うんですよね、一枚一枚が。それが僕は凄いなと思いましてね、デザイン的に。
杉本:そうですね。生きているんですよね。木は切った後も生きているし、柔軟性もとてもいいし。鉄だとかなんかには敵わないようなものが。
司会:今、伊佐社長がお話になったような、小さい頃の環境が杉本さんの音楽活動に何か活きていると感じられることっておありですか?
杉本:日本の音楽の原点みたいな木遣りだとか、小唄だとか、長唄だとか。そういうものっていうのは私たちの中に染み込んでいるんですね。で、私たちが外国に行って音楽をやっても、もう私の作ったものは、西洋音階で作っているんだけど、「オー!ジャパニーズソング!」って。だから染み込んでいるんでしょうね、日本が。
伊佐:そうでしょうねぇ。私はもう幼少のころから音楽が遠くて。ピアノとかヴァイオリンをかじったことはあるんですよ。
杉本:おぉ~、すごいじゃないですか。
伊佐:いやいや、もうそれで逃げ出して、絵に行きましてね。私は、音楽は怖い学問なんですよ。ただしですね、こんな本を読みましたね。ベートベンの曲は、深い、深いベートベンの苦悩があって、それが20数年経ってこの曲になったとかですね。その音楽の深さというのはですね、心の様子を表現していく力というのは、人生の痛切な体験が必要だろうなと思って。で、前回ですか、先生。作曲家じゃなくて、「作直家」、真っすぐに表現するという教えがあったとおっしゃっていたんですが、誠にそうだなと思って。建築も研ぎ澄ましてくというか。複雑に考えたことを、整理して整理して整理して素直にしていく。非常に人間って複雑に考えるんです、初めは。それをどれほど整理するかという。素直に替えるというか。それがやっぱり非常に美しい、非常に整理された空間になっていくわけで。その苦心の跡が、住む人に感動を与え、住んだ方がまた家からなにか影響を受けると思いましてね。それは音楽もやっぱりそういうことだと思うんですけど。
杉本:そうですね。作詞家の先生なんかに言わすと、どのくらい言葉を捨てられるかと。いっぱい言葉を出して、どのくらい言葉を捨てられるかと。で、捨てて、捨てて、捨てて、捨てて、最後に残ったのが行間を、喋らなくても行間で心を伝えられるんだと。で、まぁ私たち、私はへなちょこな作曲家だけど、やっぱり心のなかにぎゅーっと凝縮されたものが、ある意味はストレスの部分もあるだろうし、世の中に対する不満もあるし、いろんなものがあるけども、それがこう、ぶわっと爆発した時に曲が出来るみたいなことがありますね。
司会:あの、伊佐社長。音楽に遠いなんでおっしゃっていましたけれども、実はこの「わたし歳時記」のテーマ曲「ふるさと」というのは伊佐社長の選曲なんですね。そういう心に残る歌…
伊佐:この曲はね、思い入れがありますよ、私は。当社の忘年会は職人さんと110名位で昔ながらの宴会をやるんですよ。最後のしめは「ふるさと」をみんなで肩を組んで歌うんですよ。この時になりますとね、私ものの日は1升近く飲みます、酒を。で、最後肩組んで。これを歌いだすとね、胸が熱くなってね、1年の感謝、職人さんたちへの感謝が生まれてくるんですよ。
また私、家内が4年前他界したんですけれども。家内がいよいよ息を引き取るときもですね、「ふるさと」と「夏の思い出」、尾瀬の歌でした。これを繰り返し、繰り返し歌って送ったんです。私はずーっと根底にふるさとといいますか、両親に恥ずかしくない仕事をしよう、あるいはこうしようというのは、いつも原型としてありました。まぁ、メロディと詞もいいんでしょうね。これが当然いいんでしょうねと思って。
司会:音楽の力というのを感じますね。
杉本:そうですね。音楽は言葉で、いや、文章で伝えられないものを伝える力があると、いうことをベートベンやなんかは言ってますよね。
伊佐:そうでしょうね。
司会:伊佐社長の建築も、ものすごく日本の心というのを追求されている部分があって。で、杉本先生の音楽の中にも、日本人の心というか、私たちの中にあるメロディがあるんじゃないかなというのが凄く感じたんですが。
杉本:そうですね。海外に私ずっと10年間ぐらい演奏活動で行ってましたけど。日本人が日本の曲をやるのが一番うまいんですよね。それはもうね、外国で、ドイツ人だ、アメリカ人だからね、ソーラン節歌ったら日本人のがうまいに決まっているんでね。だから私は堂々と日本の歌をね、日本人が日本の歌をやらないでどうするんだと、日本の音楽をやらないでどうするんだという気持ちが強く湧いたんでね。もうずーっと日本の音楽をやっています。
ただ、家なんかも私そうなんですけど、西洋の音楽というのは、家が響くように家の中が作ってあったんですよね。
司会:音楽というか、音が響くように?
杉本:音が響くように。例えば、床だとか、天井だとか、壁だとか、土で出来たり、石で出来たりしてるから、だからそこで音をうわーんと鳴らすと、ハーモニーが出来るんですよね。で、日本の家屋は…昔の話ね、畳に障子に天井で響かないから。響かないから、細やかな旋律が発達したんですよね。だから逆に、今度は、日本の細やかな音楽は向こうで響きすぎちゃってダメなんですね。
司会:凄い。音楽と建築のこの関係性って深いんですね~。
杉本:でももう今は、西洋の住宅になっちゃって、どこもかしこも。で、ピアノを置いたり、歌を歌ったりもするんで。まぁよく響くからいいんだろうけど、近所の音にね、迷惑かけちゃいけないとか。マンションだと、壁に伝わってこう回りますから、音が。集合住宅もそうでしょうし。だからそういうものを考えると、音があまり鳴らないようにしちゃう。あまり鳴らないようにしちゃうと、今度はそこで練習している人は、本当にちっちゃい音楽しかできなくなると。響かないから。だから、社長にちょっとお聞きしたいんだけど、小学校の音楽室なんていうのは吸音板を貼っちゃって、音が響かないようにしちゃうんですね。あれは、外に漏れてうるさいからって。でも中は響くようにしといて、外に漏れないようにするのは…。
伊佐:そうですねぇ。じゃあもうちょっと…木部がもうちょっと襞のようにあったほうがいいんでしょうね。反響がいいんでしょうね。
杉本:そうですね。で、反響が良くないとね、歌っててね、あるいは楽器演奏しててもね…
伊佐:心が喚起されませんよね、それはやっているほうは…。
杉本:うまく聞こえないから嫌になっちゃうんですよね。
伊佐:そうでしょうね。
司会:なんかお二人の専門的なところで話が盛り上がろうというところなんですけれども、実はお時間になってしまいまして。また是非これからもお二人、いろんなところで一緒の世界を広げていただければ、そういう機会になったんじゃないかなと思いながらお話聞きました。
「わたし歳時記」今月のゲスト、作曲家・杉本龍之さん、そして今週は伊佐ホームズ代表取締役社長・伊佐裕さんにもご一緒いただきました。お二人ありがとうございました。
杉本・伊佐:ありがとうございました。
山中敬久さん

司会:わたし歳時記。今月のゲストは秩父で林業を営んでいらっしゃいます、角仲林業・代表取締役社長 山中敬久さんです。よろしくお願い致します。そして、この方にもご一緒していただいています。伊佐ホームズ・伊佐裕社長です。今週もよろしくお願い致します。
さて、今月、角仲林業・山中敬久社長をお迎えしまして、林業の問題点・秩父の森づくりなど、お話をお聞きしているのですが。今週最終回ということで、もう一度その問題点も少しお聞きしたいと思うのですが、これからの林業を考える…何が一番大事だと思っていらっしゃいますか?
山中:問題点はいくつもあるんですけど、やはり、長期にですね、150年、200年の木を作るというのを一番基本にすべきことかなと思っています。で、その中で、しっかりと間伐しながら、後から生えてくる木を大事に育てていくと。そういう、端的に言ってしまえば生態系を重視すると…そういうことですね。
伊佐:そうですね、(生態系を)守りながらね。経済効率との関係ですよね。両方ですね。
司会:経済も切り離せない問題ですよね。
伊佐:両立することが存続できることですからね。
山中:そうですね。
司会:そのために新たに考えていらっしゃるようなことっておありですか?
伊佐:我々からすると、需要を安定的にうちが作っていくということで、山にそれをお願いする…。山も計画的に計画が出来るという。来年これを切ろうとか、計画が出来るわけですよね。
山中:で、前も出ましたように、3Dでそれが本当に使えるようになれば、伊佐ホームズさんと我々とが、じかに、ここんところはこういうふうにしましょう、ああしましょうと、そういう話まで出来てくるんで…
伊佐:まぁ、だいぶ出来てきていますけどね、それがね。精度あげながら。
普通、木は、3メートルとかで、玉切りっていって、出すわけですね、市場にね。3メートル、4メートルですかね、山では。でも我々から見ると、2.7でもいいんですよ。市場に応えて切ったほうが、30cmも無駄が出ないんですよ。だから、市場と直結することがいかに大事かということですよ。まぁ、いろんな業界、みなさんそうですね。ユニクロの柳井さんは、情報製造小売り業を目指すといっているんですよね。我々は情報なんですよ。情報でもって、製造する。そして小売りというか、一体化する、そこはもう隙間がない、それを目指したいですよね。
山中:そうですね、だから有名な大工の棟梁の田中文男さんという方が、なにしろ先に情報を流せと。で、この木ならこの木はこういうふうにして切ってほしかったと、いうようなことのないように、情報を是非流してくれと。そういう、もう30年近く前に言っているんですよね。
伊佐:それと山中さんね、これからしたいことはね、今我々のこの仕事は、秩父市の市長も大変理解があって期待してくれていましてですね、修理のことも今市長もお話になっているんですが。大径木があるんですよ。100何年とかの。こういう時、切るときはね、やっぱりお祭りをしながら、子供たちも集まってもらってですね、伐採式をやるようなことでね、木の命を頂くというような儀式をやりましょうよ、これから。
山中:そうですね、大事なことですね。
伊佐:そういうことをしながら、尊さを伝えていくというか。経済の効率とともに、そういう精神性を…そういうことも考えながら、山とつながりたいですね、都会が。
山中:いいですね、はい。
伊佐:あれも面白いですよね。秩父にイチローズモルトというウイスキーメーカーがあって。これの樽のですね、水楢の木が見つかったと聞きましたね、この前。大径木が。
山中:近いうちに、市と東大の演習林も関わって出すそうです。
伊佐:いいですね。これは世界的な評価の高いウイスキーですよ。で、秩父の木でウイスキーを作って、秩父の麦で生産すると。素晴らしいですよね。
司会:そういうものを、若い人たちが後継していくというか、育てていってくれるようになると、なおいいですよね。
山中:まぁ、それを期待しているんですけど。うちの場合は、今せがれに、なにしろうちの生計の元なんだから、キノコを徹底的によく覚えなさいと、そういう話はしているんですけど。せがれをまだ、山を全部見せたわけではないので、これからそのへんをどういうふうにしていくかというのが、まだ自分の課題でもあるんですけど。
伊佐:いや、いい息子さんですよ~。一晩民宿に泊まって飲んだんですよ。私は私のビジョンを語って…ご子息にわかるように話をしましたね。美味しいお酒でしたね(笑)
司会:地元の中学生の方ですとか、それから東京大学の学生さんも勉強に行かれているんですか?
山中:えぇ、あのー地元の中学生というのは、一番最初に植樹祭をした時に関わったのですが。もう中学校も廃校になっちゃって。東大の学生さんはですね、仁多見先生の関係で。木材整理とか、そういうのを研究している教室の学生さんたちが、もう7、8年来てますかね。で、山のほうは演習林のほうで見るので、きのこの栽培の状況なんかを見るんですけど、もうキノコが出てるところを見ると、皆さん必ず歓声あげますね。
伊佐:あのー、今、廃校になった小学校の校舎を使ってですね、東京芸大の名誉教授の坂口先生とかがですね、そこで絵を描くアトリエ村を作ろうということで、これも今もう実施に入りました。だんだんいろんな方が山に入ってきて、交流して。なんらかの文化を作りながら、新しい時代を開きたいですよね。
司会:そして、秩父に来られる方の反応というのはどうですか?
山中:今、だいぶね、三峯神社が1日に特殊なお守りが出るので、それでもう本当に大渋滞になったりするんですよ。まぁ、それが大きな目立ったことなんですけど。まぁ、秩父も何気ない場所でね、これぞ自分を取り戻せるいい場所だなというところがいろいろあると思うので…。
伊佐:今いいことをおっしゃいましたね、自分を取り戻せる場所。私がその創業の折りにですよ、ずっと子供を連れて歩いたのが秩父だったわけですよ。まだ会社が生まれる前、34か所、100何キロ歩いたわけでありまして。そういう場所なんですね、秩父というのは。僕はやはり、残った場所、昔から残った場所というのはこれから強みだと思うんですよ。都会がなくしたものがあるわけですから。だから僕は三峯神社もすごいと思うし、あのやっぱり神さびたというか、神秘性っていうのは素晴らしいと思うんでですね。都会には神秘性ってないでしょう。
山中:そうですよねぇ。
司会:最近テレビコマーシャルも、秩父、よく私拝見するんですが…なんかね、行きたいなと思わせる魅力がたくさんありますよね。
山中:是非…ぶらりと来てください。
伊佐:おいでください。
司会:おいでください…伊佐社長、もうおいでくださいになっている!(笑)もう秩父はふるさと…?
伊佐:そう、僕は迎えるほうですから(笑)
司会:伊佐社長が、その感じる一番の秩父の魅力、どこでしょう?
伊佐:そうね、特別これがかっこいいとかじゃなくて、穏やかで何度行っても飽きないところ。やっぱり、かっこいいというのは飽きるんですよね。何度行っても、こう進んでくれるというのかなぁ。あと、僕は山中さんの家に上がるときはなんとも言えないなぁ。あの、縁側に入ってたときとか。その縁側からね、何とも言えないね、山並みを見るといいんですよ。
司会:贅沢ですね~。
伊佐:贅沢。でね、山というのはずっと見ていても飽きないんですよ。雲の動きとかあるわけですからね。飽きないところというのはいいですね。
司会:そうですね。まぁ、山中さんはずっといらっしゃるわけですから、もう普通のことなのかもしれないですけれど、改めてリスナーの方に、何かそういった魅力とかメッセージというようなものをお伝え頂けるといえば、どんな言葉で…?
山中:そうですね、やっぱし…自然のリズムを感じられるところかな。まぁ、生活していると、自然となんとなく感ずるんでしょうけど、あんまり意識しないでぶらっと来れば、そういうのを感じられるところがあるんじゃないですか。秩父は非常に田舎なんですけど。
伊佐:まぁ、今もね、養蚕農家が残っているし、秩父の糸は大変強いと言われていますよね。これもまた活用して、世界に誇れるようなファッション産業に対抗できるようにしたいですよね。名声も…。
山中:あんまり秩父は格好ばかり追求すると、秩父らしさがない…(笑)そのへんを…。
伊佐:そうですな(笑)
司会:なんか秩父の山の中でいろんなパワーがもらえそうな…そんな感じがいたします。
伊佐:そうですね、神々しいですよね。絵描きさんがここに来るとなんかインスピレーションが湧くと言ってますよね。
司会:やっぱり。そうですか。是非ラジオをお聞きの皆さんにも、ご自分の足で秩父にお出かけいただいて、またその魅力をも感じていただきたいと思います。
山中:是非是非ぶらりと…。
伊佐:お越し下さい!(笑)
司会:「わたし歳時記」今月のゲスト、その秩父で林業をずっと営まれていらっしゃいます、角仲林業の代表取締役社長・山中敬久さん、そして5週に渡って、伊佐ホームズの伊佐裕代表取締役社長にもお付き合いいただきました。本当にたくさんの魅力を語っていただきました。ありがとうございました。
山中:どうかよろしくお願いいたします。
伊佐:ありがとうございました。お疲れ様でした。
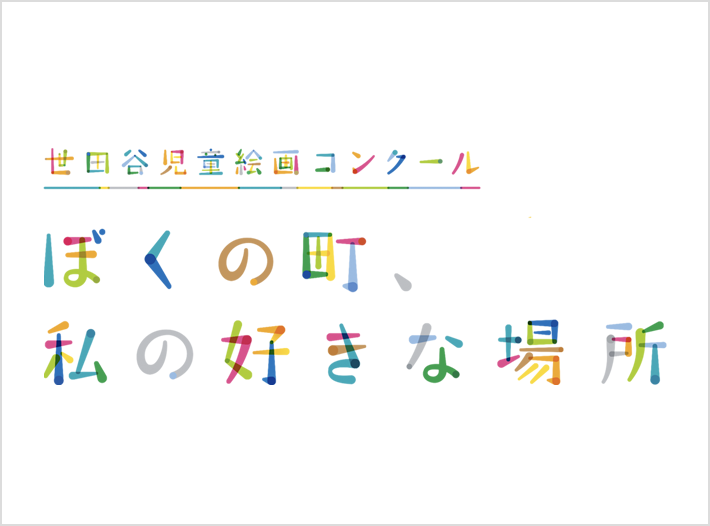
藤森隆郎さん
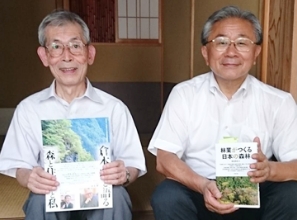
司会:わたし歳時記。今月のゲストは農学博士、藤森隆郎さんです。どうぞよろしくお願い致します。藤森さんは1963年に農林省林業試験場(現在の森林総合研究所)に入省されました。これまで半世紀に渡って、森林の生態系と造林に関する研究に従事なさっていらっしゃいます。そして藤森さんと一緒に今週もこの方にお話して頂きます。伊佐ホームズ・伊佐裕社長です。よろしくお願い致します。
今週は海外のお話などもお聞きしながらと、思っておりまして、藤森さんは日本の森林づくりを考えるうえで、海外の例を参考にされたというふうにお聞きしました。どんな点が海外では優れているというふうに考えていらっしゃいますか?
藤森:日本の林業とかあるいは森づくりに関しては「技術者」というのが育成されていない、これは非常に大きな問題だと思っております。例えば、ヨーロッパの国々では、森林所有者と一般市民の方々、この関係が非常によくできているということですね。一般市民の方々は、林業が大事だということを理解しています。一般市民の人たちは、税金から所得保障や補助金が使われるということはちゃんと理解しています。
司会:林業のほうにということですか。
藤森:そうですね。その一方で、市民の方々は森の中に自由に入って楽しめるということを求めています。権利も主張しています。で、そういう関係が出来ていることによって、一般市民というのは、木材の消費者でもある。その人たちは、やはり地域の木材を使うという、そういう意識が働く。だけどその中で非常に大事な役割を果たしているのは、森林・林業の専門家のフォレスターといっている方です。これは例えばドイツを例にとりますと、国の認定したフォレスターというのは凄い存在なんですね。大学を出て、それからフォレスターに必要な教育を改めて受ける。これは現場の実習・経験を1年・2年と積んで、そして非常に厳しい国家資格を受けてという…そういう技術者のリーダーがいます。で、その人たちが森の中で大きな役割を果たしている。例えば、先ほど一般市民がどんな所有者の森でも入っていくことが出来る、そして手につかめる範囲の山菜とかきのことかを採ってもいいというんですね。そういう時にとフォレスターがずっと巡回していて違法行為を取り締まる。しかし、それは取り締まるだけでなしに、そこでその教育というんですかね。普段からマナーをフォレスターがみんなに示している。国あるいは州の公務員のフォレスター・技術者のリーダーが市民と非常に近いところにあると。これが大事なことです。
もちろんフォレスターは、技術のリーダーですから、森づくりのリーダーです。山で生産された材の取引ですね、川下との取引の時にフォレスターがその調整役をします。で、フォレスターが材の等級区分もします。そして取引のアドバイスをして、山側の最低限の基準というのはこういうもんだと、だからこれぐらの価格が適正なんだろうという。本当に森のプロがそういうことをやっていると。これが日本にないところなんですね。で、そのフォレスターというのは、一般の人たちへの、先ほど言いましたような教育なんかもやっているということで、みんなの尊敬の的です。
で、そのフォレスターの資格がある人が、その州の、あるいは連邦政府の林野庁の最高幹部にまでなっていく、登用される。フォレスターで現場の技術者のリーダーでないと、上まで行けない。大学教授もフォレスターの資格を持ってないとなれない。全部公募制でですね、フォレスターで公募してきた人の中から大学教授やそれから、州や連邦政府の林野庁の幹部になるという。それぐらい技術者のリーダーであるフォレスターという人の存在の役割は大きい。で、国民の尊敬の的で、ドイツで若い人が一番なりたい職業は何かというと、一番はパイロットです。二番が医師です。三番がフォレスター。
司会:すごい…。
藤森:フォレスターはみんなの尊敬の的なんです。だから素晴らしい森が出来、そしてドイツが林業国家として名が轟いているというのも、やはりフォレスターという存在が大きいと思います。
司会:伊佐社長、日本で考えますと、どうしても現場の方とそれから机上の方というふうに…。
伊佐:遊離していますよね。
司会:その辺は学ぶところが…。
伊佐:そういう社会の仕組みを作りたいですね、先生。成り立つように…。
藤森:で、日本ではですね、大学で林学を学んできた人が官庁に入っても、2年か3年でポストが変わっていくんですね。組織のためにある。市民のためにあるというわけではないという話ですね。まぁ、そういう形で、だからせっかく能力のある人たちも、その現場の経験に基づいて力を蓄積していくというでなしに、昨日までやっていたことと全然違うポストに移ってしまう、まぁどんどん出世のために…
司会:そうですね、ある意味時間に流されてしまうようなところがありますよね。
藤森:そういうところを日本もですね、技術というものを大事にするという、こういうシステムをなんとしても作っていく必要があると思います。それはもう、さっきみたく、パイロットになるための訓練、医師になるための訓練、それともう同ベレベルのことなんですよね。それから、日本では、林業技術者に対する、そういった長い年月かけて育てられてきた経験豊かなそういう人だっていう、そういうものが日本にはない…
伊佐:定義づけがないですよね。
藤森:それをやっぱり、日本でもしっかりとした教育制度、あるいはフォレスターがしっかりと働けるようなシステムですね、これを作っていく必要があろうかと思いますね。
伊佐:そうですね。4回目にして、今後の林業の大事な課題を先生からお教えいただいたような気がしますね。
藤森:はい。で、またそういうフォレスターがいないとですね、私たちがせっかくやった研究が普及する、そういうパイプがないんですよ。全国には素晴らしい林業家の方々がいらっしゃいます。凄い技術を創意工夫して。でもそれはあちこちの点に過ぎない。
伊佐:繋がっていない。
藤森:で、フォレスターがそういう人たちのものをわかりやすく、他の人に説明して、それは、よほど学び・体験した、実力のあるフォレスターのような人でないと、それは出来ないんだと思います。あるいは一方で、フォレスターの人たちから、私たちの研究成果がフォレスターの人たちは現場でそれを応用して、問題があればそれを研究者のほうに返して頂けたら、また我々も動機づけがすごく出来ていく。そういうパイプ役の一番大事なところにいるフォレスターというのが、日本にいない。そういう状態で、森づくりや何やというのはですね、やはり日本もヨーロッパ諸国に学んでいければいいなと思っております。
司会:今月藤森さんのお話を聞いていて、森に行きたい、森林に出かけてみたいと思われた方、たくさんいらっしゃるのではないかと思います。できればプラスで、そういったフォレスターのいる森に行ってみたいなという感じがいたしましたけれども、例えば都会に住む人でも出来る、参加できる森づくりというのもありますか?
伊佐:我々は、今年は10月29日に秩父の森で、スギの木を切った跡にカエデの木を植えるという植樹祭を毎年やっています。そして混合樹林になっていくという仕組みを今作って、なるべく子供さんだとか、いろんな方に参加していただこうと思っています。
司会:その他にも何か大きな企画がおありになりますよね。
伊佐:脚本家の倉本聰さんが大変森への造詣の深いお言葉、森の尊さについて随分おっしゃっていますね。それで倉本さんをお呼びして、11月25日に、二子玉川ライズのイッツコムスタジオホールですね、「倉本聰と語る 森と住まいと私」というテーマで講演会をやります。都会の方々が森への関心を深めていただきたいなと思っています。
司会:ぜひ聞きたいという方は、まだ間に合いますか?
伊佐:あと数日ですが、当社のホームページで今受け付けておりますので、どうぞご応募ください。
司会:是非伊佐ホームズのホームページをご覧いただければと思います。
そして、実は私も読ませていただいたのですが、藤森先生の「林業がつくる日本の森林」というご本、築地書館から出ている本なんですけど、これには今月お話しいただいた問題点、課題、それからこれから私たちがどんなふうにしていけばいいのかというようなことがたくさん詰まっている、素晴らしい本なんですけれども、先生、この本をお書きになって、何か皆さんにこれこそ伝えたいというような思いはおありでしたか?
藤森:私たちは次世代以降の人たちのことを考えて、大地に根差した持続可能な生き方を考えていきたいと、そのように思っています。森との付き合いというのは、それの根幹になるものだろうと思います。で、私たちは、私たちの国はですね、私たちの生きざまのにじみ出た、誇りの持てる美しい国であってほしいと、そういう願いを込めてこの本を書きました。そういうメッセージを皆さん、受け取っていただければと思います。
司会:ぜひラジオをお聞きの皆さんも、今一度森について考えるきっかけになってくれればよいなと思っております。
「わたし歳時記」今月は、農学博士の藤森隆郎さんに4週にわたってお話いただきました。ありがとうございました。そして4週間、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきました。どうもありがとうございました。
神保和彦さん

司会:わたし歳時記。今月のゲストは昭和信用金庫 理事長、神保和彦さんです。よろしくお願い致します。そして今週は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきます。よろしくお願い致します。
さて、お二人の出会いなんですが、いつ頃になりますか?
伊佐:昨年の2月に世田谷区の商工会議所の新年会がございまして、その席でご挨拶を申し上げました。多くのご参加者の中からですね、何かひときわですね、お話したくなる、ご様子だったんですよ。その出会いが、今日まだ日は浅うございますがね、こんな風に私も甘えて対談をさせていただくようになっております。
司会:お声をかけるときには、緊張はなさらなかったですか。
伊佐:私、あんまりそういう緊張はないんですよ…。
司会:あぁ。たぶん理事長を拝見しているとそういうのはないだろうなぁと…。
伊佐:ご立派な方ってね、そういうことを持たせない様子があります。
神保:そんなことないですから…(笑)
司会:そして、もう一つお二人のつながりとしては、今年の3月になりますでしょうか。一般社団法人東京都信用金庫協会、それからしんきん協議会連合会、東京都事業経営者会が主催する、平成29年の第30回優良企業表彰制度の賞を取られた、これが信用金庫の取引企業・およそ17,000社の中から特に優れた企業を選ぶというようなもので、56社表彰、その中の伊佐ホームズさんが優秀賞ということだったんですね。
伊佐:思いがけない賞を頂きました。
司会:すばらしいですね~。これは伊佐ホームズさんのどんなところを見て選ばれたんでしょうね。
神保:私どものこの企業表彰って30回目なんですけれども、やっぱり今いろいろと経営環境がどんどん変わってきます。で、私どもの取引先の中でも、非常にきらりと光ったり、それからいろいろなところと連携をしたり、それから今の時代にマッチした経営をしたりということで、その特色のあるそういう方々をですね、中小企業診断士の方が…だから伊佐社長のところにも何回か行ったと思うんですけれど、ヒアリングを必ずやっていますから。なかなかこの賞を取るっていうのはね、私から言うと難しい賞なんです。何か一つきらりと光って、やっぱり社長さんの経営理念がしっかりしていないとたぶん取れない。その中で優秀賞というんで、私どもとしても非常に誇りに思っております。
司会:社長はいかがでしたか?
伊佐:私はこの会社を始めましてね、30年なんですね、ちょうど。そういう年にこういう賞を頂きましたが、建築業っていうのは非常に遅れている業界だと思いますし、また取引先である林業のほうも大変衰退している状態で。そういった意味で大変な業界だと思います。で、私も30年やってきた中で、美しい住宅を作ろうと思いましたけれども、今は美しい取り組みで美しいものを作ろうというふうに。美しい取り組みというのは、やはり同志なんですね。お互いが、同志助け合っていいものを作ろうという。単なる安く仕入れたからいいのではなくて。サプライチェーンと申しますが、お互いが納得する形で、共に発展するような取引をして作っていきたいというふうに思って、この5年間くらいサプライチェーンの研究をして参りました。特に林業問題って、大変な問題でして、国家的な問題だと思いましてね。私は工務店が直接木を、原木を買うという新しい取り組みを始めたわけです。そうやって無駄を省く。で、流通の無駄を省いて、セールスをするということで。これによって非常に山が成り立つ。お互いが成り立つ仕組みを作りました。これに伴って、今後の品質だとか、環境負荷問題とかいろんなことが始まりましてね。困った問題に取り組むことが、意外と新しいノウハウを蓄積していくかなと。それから新しい領域を開くかなという。考えたら、ヤマト運輸もしかりですよね。あるいは地図のゼンリン。みんな大変な労働力のいる業界を非常に転換して、新しい業界を作っていった…。我々も林業はですね、3Dで計測をしてですね、木の1本1本の数量がわかるんです。で、我々が設計を起こしたやつを山に送ればですね、この木を何本切って柱をとるなんて出てくるわけです。無駄がないわけですね。これによって、あと必要なことどうしでお互いが成り立つという仕組み、まぁそんなことの姿が理事長の目に留まったのかなと思っていまして。日本の林業を変えていきたいと思っております。
司会:あの、理事長は、建築に興味がおありだったということを、前の週でもお聞かせいただいているので、特に今のお話は興味深くお聞きいただけたのでは…?
神保:まー、興味深いというより、やっぱり日本人の和というのは心だと思いますのでね。それを大切にして、そしてサプライチェーンを合理化したと。これを今、なかなかできないことだと思うのですけど。それを取り組んだということは、私は素晴らしいことだと思っていますね。何しろ私は、和が大好きなんですね。日本人ですから。やっぱり住まいというのは心のよりどころですね。ホッとするところだと思うんです。だからそれが一番必要だと思いますね。なんでもいいってことではないと思います。
伊佐:嬉しいことをおっしゃいましたね。私も家はね、家が私を作ったなあという非常に思いがあるんですよ。これは豪華な家とかそういういう意味じゃなくて、家という空間が、人の心を育てるなあという非常に実感がありますよ。で、先般ある方から、チャーチルが「人が家をつくるが、また建築が人をつくる」というふうにいっている名言があるそうですね。やっぱり我々は、触れるもの・空間がいかに影響を与えるかということを思いまして。やっぱりよりどころがあるということは大事なことかなと思いますね。
神保:そうですね。何しろ、安らぎどころと、それから、次の日ですね、翌日の活力の素ですね、私はそう思いますね。それも和の、やっぱり日本人ですから。
伊佐:やっぱり自分がそこに在るような思い。その場がですね。自分が投影されているというかな。
司会:あぁ、なるほど。ん?自分の家を今思い浮かべてちょっとドキッとしちゃいました(笑)
伊佐:いいものっていつまでも居たくなりますよね。何もなくても。
司会:そうですよね。伊佐ホームズさんのギャラリーにお邪魔すると、いつまでも居たいなと思うんですけど。
伊佐:ありがとうございます。あとご人物もそうですよね。理事長のような方の横にはずっと居たいし。なんでしょうね、発するものってありますね。
神保:私もこないだ、伊佐ホームズさんところの展示場とか、いろいろ見させてもらって。あぁ、いいなあと思いましたね。
伊佐:お茶室にもお越しいただきましたね。
神保:落ち着きますね。
司会:それとさっき社長がお話になられた「美しいつながり」というのが、信用金庫のつながりにも同じなのかなぁというふうに思って聞いたのですが…。
伊佐:そうですね。この番組を聞いておりましてね、理事長のお考えが非常に伝わってきましたね。
神保:やっぱり、そうですね。お互いにお客様を第一にして、お客様の喜びを実現するのが、で、満足していただくというのが最終な目的ですね。相通ずるものがあるんじゃないかと。
伊佐:まぁ、私は67になりますが、理事長のお元気な姿を見ましたんでですね。まだまだこの仕事を続けていきたいなと思ってます(笑)。
神保:伊佐先生に頑張ってもらわないと(笑)お願いします。
司会:お二人の力で世田谷をもっともっと活気あふれる街にと思うのですが、お二人が目指す世田谷というのはどういうところでしょうか。
伊佐:そうですね。私は今でも本当にいい街だなと思いますね。すべてのバランスがよろしいですよね。
神保:そうですね。本でですね「23区格差」という本が出ていたんですけど、世田谷というのは、すべて1番じゃないんですけど、必ずトップ10に全部入っている。だからバランスの取れた街ですね。住んでよし、それから働くところもそこそこに、楽しむところもあると。どこ行くにも便利で…。
伊佐:自然も多いし、美術館も多いし…。
神保:いいですね、文化都市ですね。
伊佐:あと私、特に下北沢はですね、今後のインバウンドも含めて、世界の食文化といいますかね、誇るべき料理が多いなと思いましたね。そこに特化して、大変な日本を代表選手になるかなと気がしますけれども。そこに日本の和風文化もあるとよろしいですよね。
神保:世田谷というのはやっぱり一つのブランドだと思っていますね。ですから、私も協会で全国やって、地方によく行っていたんですけどね、昭和信用金庫って言ってもわかりませんから。世田谷の下北沢に本店があるというと、みんな知っています、世田谷というのは。そのぐらい、やっぱりブランドですね。
伊佐:私も世田谷・伊佐ホームズと。世田谷の方に支持されてやってきた30年という思いでおりますね。
司会:その中に、さっき理事長がおっしゃった「和」というものを強く押し出した感じでいけると、もっともっと魅力的な街になるような気がするんですが…。
伊佐:ちょっと素材も生かしましてね。日本の伝統工芸とか、いろんなものがありますね。
神保:やっぱり木というのは息をしていますからね。だからそれが違いますよね。
司会:何かお二人で力を合わせて、新しい取り組みとか出てきそうな…。
伊佐:やりたいですね。
神保:そうですね、なにかひとつでもやりたいですよね。
司会:そのためには話し合いの場も必要ですかね?(笑)
伊佐:はい、夜もお付き合い願えたらと思います(笑)
伊佐:そうですね、そういう時ほど、いろいろいいアイディアが浮かぶんで…。
司会:ね、そういうふうに社長、お酒の場ではアイディアが出るって前にも教えて下さったので…(笑)でもお二人ともお忙しいので、さてそんなお時間どうでしょうか?
伊佐:いやいや、その時間何とか優先的に(笑)
神保:私も優先的に(笑)
司会:ますます結びつきが深くなりそうですね。
神保:伊佐社長、よろしくお願いします。
伊佐:ありがとうございます。
司会:ありがとうございました。「わたし歳時記」今月のゲストは、昭和信用金庫 理事長の 神保和彦さん、そして今週は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただいきました。お二人どうもありがとうございました。
神保・伊佐:ありがとうございました。
愛甲次郎さん

司会:わたし歳時記。この番組は伊佐ホームズのギャラリー櫟からお送りします。今月のゲストは元 クウェート大使、愛甲次郎さんです。どうぞよろしくお願い致します。そして今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきます。社長、よろしくお願い致します。
伊佐:よろしくお願いします。
司会:さて、愛甲さんは、昭和8年に長崎県の佐世保でお生まれになったということで、お二人とも九州ご出身という共通点がおありなんですよね?
伊佐:あとで存じ上げたわけでありまして…。
司会:出会いの時にはまだ?
伊佐:いや、もう全然それは…。
司会:出会いはどういうきっかけで…?
伊佐:気功の道場なんですよ。
愛甲:前回の時にお話がちょっと出ましたけれども、二子玉川の気功の道場で。
司会:そうでしたか。初めてお会いになった時になにかこう感じられることっておありでしたか?
伊佐:なんでしょう。ねぇ、政府のこれだけ高官をされておられながら、非常に身近で、堂々とされて。非常に近づきやすかった。なんか、お身体から愛情がこう降りかかってくるような感じでしたね、私は。あれ、女性群もみんなそう思っていたんじゃないでしょうか、あの道場で。(笑)
愛甲:いや、どうでしょうか~。(笑)
伊佐:みんな、愛甲さん、愛甲さんってよくとりまいていましたね。
司会:お名前もとってもこう、呼びやすい…
伊佐:いい名前ですよね。
司会:愛甲さんはどうでしたか?
愛甲:あのね、鹿児島にはよくある苗字なんですよ。でもね、そういうことから言うと、伊佐っていうのは、鹿児島にね、伊佐郡っていう地名がありましてね。なんか関係あるんですか?
伊佐:いや、私は福岡で。まぁルーツは、山口にも伊佐っていうのがありましてね。そっちだと思っておりますがね。焼酎で伊佐美とか伊佐錦というのがありますね。
司会:あの、社長、先週はラジオ聞いていただけましたでしょうか?
伊佐:はい、聞いておりました。
司会:社長はご本が大変お好きでいらっしゃるので、愛甲さんの朗読もお聴きいただいて、何か感じられたことがおありなんじゃないかなと思ったんですが…。
伊佐:私は現代の小説を読みますとね、ストーリーは面白いんですけどね、読む気がしないというか。リズム感が伝わってこないというか。やっぱり多少、明治のご本とかに触れたときにですね、今日いい時間を過ごしているなぁというのがあるんですよね。やっぱり、リズム感というのが、内容以上に大事かなという。命ですからね、リズムというのは。内容は創作ですよね。なんかそこが齟齬があるような気がするんですよね。それから文語体になると、非常にこう、人生の重みが伝わってきていいなと思っていますけれど。
愛甲:文語と口語っていうのは、文語は文章語、それから口語は会話語なんですよね。従って、読むという意味ではね、文語のほうがずっと読みやすくできているんです。
伊佐:あぁ、そうですよね。
愛甲:それで、私も最近気がついたんですけれども、文章を書くときも、文語で書き慣れてくるとね、口語よりもずっと書きやすいんですよ。特に手紙なんかはね、相手とのいろいろ、人間関係を上手に処理するためにはね、文語で、候文で書いた方が、ずっと書きやすい。それはね、千年かけて、読み・書きのために発達してきたスタイルですからね。それはね、ものすごく目的に合っているというふうに思いますよね。
伊佐:文法で骨格がしっかりしているということですよね。で、骨格の中に、こう思いをいれていけば、非常に形になりやすいということですよね。
愛甲:あのね、スタイルがきちっと出来上がっているから、キーワードの選択さえ間違わなければね、誰でもね、達人の文章が書けるっていうのはね、それは文語のいいところですよね。
伊佐:そうなんでしょうね。
司会:なにか、そこに、日本文化の美しさのようなものがあるような気がします。
愛甲:千年かけてね、そういうソフトウェアを日本民族は開発してきたわけですからね。それをそっくりね、捨ててしまうっていうのはね、いかにももったいないという、そう感じですよね。
伊佐:あと、やっぱり響きがいいですよね。響きこそ私は内容かなと思うところがあるんですよね。内容がよくあっても、響きがないというのは、やはり命を感じないんですよね。私が尊敬する歌人で、前登志夫さんという方がですね、吉野の山中の方なんですがね。若い時は自由詩に憧れたと。で、ある年齢から定型詩、俳句と短歌のほうにいったという。まあ、短歌なんですけどね。その中で自由を見出していくというか、意味をおっしゃっていましたけども。それは事項を全部そぎ落とした中で、残ったものを表現していくというふうにおっしゃっていましたね。で、我々は、自由自由といいながら、非常に自由から自由になれてないというか。形があるからこそ、自由があるなと私は思いがするんですけれど。
愛甲:いやー、私はねー。文語と同じくらいね、これはあまり外に出していませんけれども、ずっと関心を持ってきたのが仏教なんですよ。で、日本というものを理解するためにはね、さっき言った文語というのも、もちろん、文字に書かれたものも、もちろん大事なんだけれども、それと同時に仏教に残されている伝統といいますかね。精神伝統をね、これものすごく大事だと思うんですよ。で、その、さっきね、なんでそんなことを言い出したかというと、事項を削ぎ落していったそこに最後に残るもの。それはね、昔の日本人はね、仏教を通じてその操作をずっとやってきたと思うんですよ。
伊佐:あー、そうでしょうかね。
私は建築の仕事なんですがね。やはり無駄があるときれいじゃないんですよね。やっぱりそぎ落としていくことが仕事なんですよね。
愛甲:いやーしかし、私は伊佐さんの仕事っていうのは、前から知っていたんですけれども、このモデルルームに入って、さっきからこうお話していますとね。木の良さっていうのがね、こう伝わってくるような…そういう感じがしますね。
伊佐:ギャラリー櫟とこのモデルハウス、この中で、私はやはり日本はこの自然があったから、我々の感性が磨かれたなと思うんですよ。そして、木の文化だと思うんです。日本の木は、杉・ヒノキで、非常にやわらかいんですよ。ヨーロッパの大工道具と日本の大工道具を比べますとね、日本のが繊細なんですよ。それだけ、繊細な…、やわらかいから繊細なものが作れる。私はね、心が形を求めたのか、形が出来るから心が進化したのか…という。やっぱり、日本の自然とか木の文化が、非常に日本文化を支えているなと思いますね。障子もそうですよね。障子通しの灯りですよね、障子越しの。
愛甲:あのー。紙。紙をね、ペーパー。これを建築にもね、すごくうまく利用していますよね。伊佐さんのあれでもそうですか?紙っていうのは大事ですか?
伊佐:使いますね、和紙は。光がいいですよね。
愛甲:特に照明器具なんかでは使うでしょうねぇ。
伊佐:かつてはですね、住宅ではただ明るさが大事だったんですけれど、だんだんに今、明るさをもっと文化的に捉えようという。性能からもっと心の取り方のほうが大きくなってきた気がしますね。心のとらえ方といいますかね。やはり日本人の明るさに対する思いがあるんでしょうね。
愛甲:あのー、最近、私感心しているのは、伊佐さんが建築というだけじゃなくて、そのもっと根っこにある林業についてね、いろいろと努力していらっしゃるのを最近知りましてね、非常に関心しているんですけれども。
伊佐:これはですね、私、やはり仕事を取り組む中で、相手が困っている問題というのは、よくないですよね。相手が困らない取引をしたいなと。林業家が我々にモノを売ってちゃんといいのか。今のままじゃ、山が植林できないんですよ。安すぎて。50年の杉の木1本切って7000円なんですよ。これ、高級なお菓子1箱ですよね。それでは植林も出来ないんでですね。私も取引をする以上は、皆さんが成り立つ仕組みを作りたいなと思って。新しい林業との取組みを…。
愛甲:で、先が見えてきているわけですか?
伊佐:ええ。いよいよ新会社が発足しましたし。(秩父百年の森)森林パートナーズという会社を作りました。日本で最初の取組みです。工務店が山の木を刈って、無駄がない流通を経てお客様に届けるという。
愛甲:お役所とか、政治は理解してくれていますか?
伊佐:よくわかる、心ある方はすごく理解されて期待されております。素晴らしい方いらっしゃいます。支援いただいています。
司会:なんか、お二人とこの空間でお話していると、とくに私は日本に生まれてよかったなというか、日本文化の良さを改めて感じるような気が致しましたけれども、これからますますお互いにいろんな刺激を受け合って、交流を深めていかれるんじゃないかなと思いますが。
伊佐:ありがとうございます、本当に。
愛甲:ありがとうございます。
司会:愛甲さんにはまた来週もお話をお聞かせいただきたいと思っております。さて、来週どんなお話になるか、社長もぜひ、来週もお聴きいただければと思います。
伊佐:聞かせていただきます。
司会:ありがとうございます。「わたし歳時記」今月のゲストは、元・クウェート大使の 愛甲次郎さん、そして今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただいきました。ありがとうございました。
伊佐:ありがとうございました。
畑中一彦さん
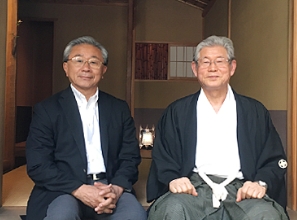
司会:わたし歳時記。この番組は伊佐ホームズのギャラリー櫟からお送りします。今月のゲストは太子堂八幡神社 宮司、畑中一彦さんです。よろしくお願い致します。そして今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきます。社長、よろしくお願い致します。
あの、伊佐社長は普段、神社に行かれることっておありなんですか?
伊佐:いやあ、私はね、多いんですよ。多いどころじゃなくてですね、私、毎朝、榊のお水替から始まります。朝は。
司会:お家に祀っていらして?
伊佐:はい。もちろん、仏壇もありますし。で、そのあと会社に来ても、会社でまた、社員みんなでお参りするという。やはり、一日を清らかに送りたいという思いを重ねていこうという…、重ねていくことしかないかなと思ってですね。まぁ、誠を尽くすという気持ちで行きたいという。で、ちょっと私話しますと、地鎮祭があるわけで。私ども、世田谷を中心に今までで約800棟の住宅を作ってきて。私も出来る限り、地鎮祭に参加するのですが、あの時間はですね、夏の暑い日もありますし、冬の寒い時もありますがね、約20分から30分かかるわけですよ。本当に尊いんですよ。で、静かに式に入っておりますと、その環境が変わってくるんですよ。遠いところから電車の声が聞こえてきたりですね。あるいは、道路がうるさいなとかですね。そうしているうちに、風がそよっと吹いてきますとね、本当に暑い日でも気持ちがいい。なんなんでしょう、環境になじんでくるんですなあ。で、懐かしいんですよ。たぶん、千年前も同じようにこうやって人は祈りを捧げてモノが始まったのかなあと思うとですね、そういう思いで仕事に向かいたいと思いましてですね。あの懐かしさというのはどういうことなんでしょうねぇ?
畑中:うーん、おそらく血の中にそういったものがあるからなんだと思うんです。神道というのは、考える宗教ではなくて、感じる宗教と言われますけれども、感覚なんですね。で、日本人はあまり深く考えないので、一神教のように、あれも考える宗教というふうに言われるわけですけれども、そこになかなか我々がいかないというのは、民族性だと思うんですよね。
伊佐:だから、西洋からいうと、日本人は宗教がないなんていいますけれど、我々は体の中にあるということですよね。それは体得しているということで…。
畑中:一番ありますね。
あのー、人類はおそらくね、私が思うには。まぁ、よく言われるのは、人間は火を使う動物だというふうに言われますけども、祈る動物でもあるという。どんな無宗教の人でも、信心のない人でも、無神論者でも、有物論者でも、祈るということは必ずあり得ますよね。自分が窮地になった時、それから家族が苦しい時に、誰かに祈るわけですよね。その誰かというのが、日本では神ということになるわけですね。
伊佐:私、建築なんで、林業の山に行くわけですよ。この前言ったときにですね。ちょっと曇りで、霧がこう谷間からわきあがっていくわけですね。じーっと見ておりましたらね、いつまでも居りたくなるんですよ。我々やっぱり、山をご神体と思って、魂が還って天に昇るという感覚があるなという感じがしましてね。山の力といいますかね。尊さというのを先般感じたばかりでしたですね。
畑中:我々、亡くなった人の魂はどこに行くのか、それは山の頂に行くというのがある。それは仏教でいうとこの、十万億土っていうところで、遠い、遠いところでなくて、身近なところにいらっしゃるという。それは極端なことをいえば、草葉の陰っていうところに来るわけですけど、身近なところで見守っていただくということが、我々の霊魂観にはありますよね。
伊佐:私も、家の力といいますか、美しいものというのは力があると思っていましてですね。そこでいうと、人間が立たされたり、力が出てくるという…。まぁ、私は創業していよいよもう30年になりますけど、まだまだの会社ではありますがね、祈りをもって美しいものを作っていきたいし、今の時代に合う性能も持ちたいなと思っておりましてですね。そういった意味では、私は建築を通して、人生の自分の実現といいますか、思っております。
畑中:家というものは不思議なもので、例えば新しい家でも、そこに住む人がいなくなると、家は急激に衰えるんですね。100年、200年の家でも、そこに人が住んでいるうちは、もうすごく輝いている。それは、家そのものにやっぱり魂が宿る、神が宿る。そこに住人がいなくなると、神様も行ってしまうので衰えるという、そういう感覚だと思いますよね。
伊佐:私、それを都市空間に考えますとね。東京は、東京の都心部に皇居があって、天皇陛下がお住まいだと。残念ながら、大阪は、大阪城公園って広さがありますけれども、あそこには人がいらしていない。もし、東京に皇居の場がなかったならば、たぶん雑然とした街だと思うんですよ。やっぱり中心軸が僕は必要だと思うんですね。家庭の中にもそうだし、あるいは都市としてもそうだし、あるいは国家としてもそうでしょうし。そこに、宮司さんがおっしゃった、魂・人がいるかどうかというのは大きな影響で。
畑中:おっしゃるとおりですね。神を信仰する国で、その中心になるのが、天皇という…。まぁ、天皇というものが中心にある、背骨があるということ。で、その背骨が、今はね、東京にありますけれども、かつては京都にあったと。そういうことで、背骨のあるところには、やはり栄えるということだと思うんですよね。
司会:あの、お家を建てるということに関しては、畑中さんもいろいろご相談を受けることもあるかと思うんですけれども、そんな時にはどんなアドバイスをなさるんですか?
畑中:東京に来てからは、ほとんど相談はないんです。ていうのは、何故かというと、もう相談できる状況じゃないわけです、東京は。家相とか、地相ということは、考えられないんですよ。もう狭いところで、地価は高いし、そこでギリギリで、家を建てなきゃいけないという制約の中で、家相まで考えられない。まぁ、北海道にいたときにはね、割と土地も余裕がありますし、家相を考えることが出来る。そういう時にはね、いろいろアドバイスをさせていただきました。我々の仕事はやはり、そういったことに対するアドバイスも仕事のうちなので、そういう知識を身につけるということが重要なことだったんですけれども。それで、今言えることは、一番重要なことは、土地の歴史というものが非常に大事なんだと。家を建てていけない場所というのがあるわけです。そういうものがわからないで家を建てたときに、災害とか、天災なんか起きたときに、それが出てくる。例えば、地震の時に地盤の問題ですね。それから、水害が起きたときに、何故、その扇状地の地盤の弱いところに、川のそばに建てた…。それが、大きな水害の時に持っていかれる。建てていけないところってたくさんある、特に悪いのは、お墓だった場所。人がね、埋まっていた、祀られていた。それから神社とかね、そういう神聖な場所も人が住むべき場所じゃないので、そこに家を建てるということは、その場所を汚すということになりますので、これもいけない。それから病院とかね、その跡地。これ、死者が出ますので、その土地がなかなか清められないということがあるんですね。その土地の因縁というものが影響してくるということがあるので、いくつか建ててはいけない場所というのがある。でもそれは、長い歴史の間でわからなくなってきてしまうということがありますね。ですから、地相が非常に大事であるということですね。それから家相は、風だとか太陽だとかですね、そういったものも、非常に住むためには重要なことなので、風通しのいいか悪いか。それから、よく、車が飛び込んでくる家というのがあるんですけども、それは道路の関係とかね。それは地相になってきますけれども。それから、家で緑が欲しいと、木を植えるんだけれども、これも考えないで植えると大変なことになる。家が壊れるということもあります。植える場所、それからどういう木を植えていいのかというのもあるし、植える場所も、ここに植えてはいけない。夏、例えばですね、日差しを避けるためということであれば、南側に落葉樹を植える、ただそれが家に近いと、屋根が傷むと。いろいろありますね。
司会:そういうことは、実際に畑中さんのところにご相談に行くのは構わないんですか?
畑中:それはもう、受けますので。
司会:そうですか。社長、今日はどうでしたか?宮司さんのお話…。
伊佐:私は、こうやって…今日が4度目ですか、ご一緒させていただきまして、ますますご人物に惚れていきますね。
畑中:ありがとうございます(笑)
司会:今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただいてのお話、本当に楽しいお話でした。ありがとうございました。「わたし歳時記」今月のゲスト、太子堂八幡宮神社 宮司 畑中一彦さん、もちろん、来週もお話して頂きますので、どうぞよろしくお願いします。おふたり、ありがとうございました。
ICSカレッジオブアーツ学長
丸谷博男さん
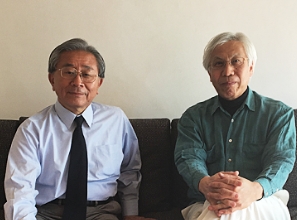
司会:わたし歳時記。この番組は伊佐ホームズのギャラリー櫟よりお送りします。今月のゲストはICSカレッジオブアーツ 学長でいらっしゃいます、丸谷博男さんです。よろしくお願い致します。そして今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきます。社長よろしくお願い致します。
まずはじめに、おふたりの出会いについて教えていただいてもよろしいですか?
伊佐:じゃあ、私から。小田原さんといいましてね、家具デザイナーがいらっしゃいましてね。私にとっては32年前からのお付き合いでしょうかね。で、丸谷さんが今度学校を開いたということでお会いしました近ごろですが、ただ遠い昔からお名前は聞いておりましてね。今回お会いしてみて、まだ日は浅いんですがね、前から私の師匠のような気がしております。とくに、前回、前々回と対談を聞いてましてね。素晴らしい方だなというふうに思います。なんでしょうね、自らのご体験からずっと人生を構築して、自分の仕事をなされ。なんでしょうね、こう、名を成そうとか、いろんな野心がある建築家も多いと思うんですけど、非常に身の丈をずっと作ってこられて。たぶんそれは、ご性格もあるでしょうし、吉村順三先生のご影響もあられると思います。ますますファンになりました。今日は楽しみですよ。
丸谷:ありがとうございます。こちらこそ。
司会:丸谷さんは、伊佐社長、第一印象とかいかがでしたか?
丸谷:いや、第一印象の前に、向こうの、(瀬田本社の)瀬田の建物。あれを見ていて。「あ、凄いデザインだな。これ、芸大の匂いがするな」と思っていました。で、うちの実家が等々力七丁目なので、ここもしょっちゅう通っていたんですよ。で、これが出来る時も見ていて。これが伊佐ホームズだっていうのは気がつかなかったんですけど。「あぁ、誰だろうな」って思っていて。建物からの出会いです。で、実際にお会いしたのは、つい最近なんですけど。それこそ、さきほどの小田原さんのご縁でお会い出来て。で、「どうしてこんなデザインが出来るの?」って、いきなり聞いてしまいました(笑)
司会:そうなんですかー。
伊佐:丸谷さん、私ね。いつも人間もそうなんですけどね。何かあった時に懐かしさを感じることがあるかどうかって結構大事だと思っているんですよ。人間って新しいほうに目がいくんですけど、この方の奥に何があるかなって見るんです。で、やっぱり、懐かしさがあって新しさがある。奥があって新しいものがあるということが、私のいつも生き方であり、キーワードだと思っています。まぁ、ちょっとあれを作った時が、もう29年と半年経ちましたけれども、あの頃まだ輸入住宅の時代でね。僕はね、本当にああいう文化がとても体質に合わなかったんですよ。やっぱり、自分が信じれることをやって生きていきたいなということで、模索してあれを作ったんですよ。今でもあんまり古くないですよね?
丸谷:いやー、もう全然変わらないです。この、ジョージナカシマの椅子なんですね、これ。社長が座っていらっしゃる椅子。これも吉村順三の友人なんですよ。で、(日系)二世で、四国の工房で作らせてね。芸大の教官室にこれがあるんです。こういうのを選ぶところも、置いてあるということも、大事な「風土」なんですね。その風土がすごく共通したものがあるんで、本当に風と土ってよくといったもんですけど。
伊佐:私は絵を描いていましたんで、絵を描いたときに、構図を決めて…。構図を決めたときにはだいたい、その色彩とか、持ち得る質感もだいたい一緒なんですよね、もう考えているわけですよ。だから建築もですね、平面が出来た、さあ今からなんだ…ということじゃなくて、社員たちにも、平面を描きながら「ここだったらこういう材料だろうな」とかですね、同時にそれが成り立っていったらいいなと…違います?
丸谷:そうですね。あのね、若い時は、自分の先生、吉村順三の弟子の奥村昭雄なんですけど。とにかく基本設計を描いたら同時にパスというか、透視図を描くんです。で、そこには家具から絵から照明がもう全部あるんです。で、自分が最初勉強しているときは、「やっと平面ができた。さぁて、じゃあ今度家具をどう置こうか、じゃあ照明をどうしようか…」って、足し算なんです。ところがベテランというのは、もうすべてが見えて、あと、もっとベテランになると、この家のディテール。細かい寸法とか、組み合わせとか、材の。それまで決まるんですよ。やっぱり修練というのは凄いですよね。
伊佐:そうでしょうね。やっぱり自分というものから、モノの距離感とか、質感とか、美しさとかというのが測れないといかんと思うんですよね。外側からじゃなくて…。
丸谷:あと面白いのは、僕も独立して、最初にとてもいい仕事をいくつか頂いたんですけど。まぁ、吉祥寺で作った家なんかは、奥さんの雰囲気と旦那さんの雰囲気を見ながら、「ここの木材は、ちょっと艶のある明るめの樺にしよう」とかね。そうやって材料と出来上がる質感もその人に合うものをって、選ぶんですよ。
伊佐:木は深いですよね。木目は本当にもう…。
丸谷:で、実直で、こうしっかりとした、冒頓な雰囲気だと、楢のほうが合いますし。やっぱりそれぞれこう木が自然に出てくるんですね。
伊佐:話は飛びますがね、九州の大分に、湯布院に、亀の井別荘・玉の湯という現在の名旅館がありますよね。私が亀の井別荘を知ったのは、今から50年前なんですよ。感動しました。湯布院の風景もその時感動しました。それが今、日本の観光地になりました。だから、私が感動した時に、私の感動は、それはまた普遍的な感動になっていくんじゃないか、私はそういうのは奥にある懐かしいモノ、人間の共通の、個々じゃなくて、実は共通のとこに行く着くようなモノを作りたいなと思いますよね。まぁ、そうやって、なかなか進化しませんけど。なんとか毎日毎日やっている次第でして。
丸谷:いや、いい風土ですよ。絶対古くならないから、こういうものはね。それが大事だなと思いますね。
伊佐:でも、先生の、その木の文化に対する深い造詣を教えて下さい!
丸谷:いえいえ!
伊佐:さまざまな木目の美しさがありますんでね~。
丸谷:そうなんですね。
司会:本当にお二人ともに、世田谷で家づくり、それから街づくりもなさっていらっしゃるということで、目指しているところというのがだんだんこう見えてきた…?
伊佐:うれしいですね。先を行く先輩がいて私が後ろからついていくというのは、本当にうれしいですよ。
丸谷:私のほうも、学長になってすぐね、伊佐さんに声かけて。産学連携で音楽会・映画会やりませんかって。今回の取組みはこのふたりのペアで。
司会:え~。音楽会と映画会を?
丸谷:音楽会と映画会を連続して。
伊佐:そうですね。あるいはここで、学生さんの勉強会とか…。
丸谷:そうそう。学生がここにきて、メジャーもって、スケッチブックと。寸法を測って、空間の大きさと。皆、気が付くかどうか…。いろんなディテールがあるんで。
伊佐:私も建物に入った時に、つり合いというのがあると思うんですよ。たってね、売れるから、天井が高いのが随分文化だとか、値段が高いなんてあったと思うんです。気持ち悪くてですね。何かへそが落ち着かないんですよ。だいたい私はへそでモノを見るというかな…ありますね。
丸谷:おもしろいですね。
伊佐:違います?本当に気持ちが悪いんですよね。妙に高いと。水平と垂直というかな、空間の分量に対するバランスがありますよね。
司会:へそというか、丹田というか、やっぱりここが要ですもんね。
伊佐:だから、私よく酒を飲むわけですけどね。飲み屋探しもね、かなり自分で鍛えていくと。これは違いますよ!(笑) ガイドブックじゃなくて、自分の眼力でやっぱり…。
丸谷:僕も負けないかもしれないですね(笑)
伊佐:同じですよね。やっぱり奥を見つめるというかなぁ。
司会:あ、最初の話に今繋がりましたね。奥ですね。
丸谷:あと空気ね。鼻がいいかどうか、その空気を感じられるか。海外旅行に行ってても、だいたい僕がレストラン探しをするの。で、そんなに間違ってない(笑)
司会:なんかお二人の後ろをついていくと、いいことがありそうな気がしますね。
伊佐:あんまり、表に変な標語とかラベルがあるとダメですよね、お店でも。
司会:あ、そうですか?
丸谷:やっぱり表面で勝負しようというのは、ちょっと浅はかでしょ。奥が浅いんですよ。もうひとつ何か、ふくらみとか、しっとり感とかね。
丸谷:あ、そういえば昔ね、世田谷の梅ヶ丘で「暖簾フェスティバル」というのをやったんですよ。
伊佐:面白いですね~、それ。
丸谷:ちょうど山崎小学校に和漉工房があって、そこのお母さん方にお店に合う暖簾を作っていただいたの。で、それを同時にぶら下げたらね、街の風景が変わるし。アートプロジェクトだと、直島でもね、やっていて。僕はそれをヒントにして、梅ヶ丘でやって。面白かったですよ。
司会:あ、そうなんですね。あの梅ヶ丘というと、梅ヶ丘アートセンターも…
丸谷:そうなんです。15年ギャラリーをやったんですね。で、建築家というのは、あらゆる材料を扱っているんですけど、ひとつひとつの材料は素人なんですよ。で、作家というのは、人生をかけて一つの材料に取り組むでしょ。その人たちから教わるのが一番いいなぁと思って。それで、素材と造形をテーマにギャラリーを15年続けました。これが一番勉強になりましたね。
司会:そういったところからご覧になる世田谷の街ってどうでしょうか?
丸谷:いや、面白いですよ。僕もまちづくり広場というのを10年か15年やったんですけど。国分寺崖線を守る、成城学園を守る、あるいは小さなグリーンスポットを連続させるとか、奥沢でもいろんな動きがあるし、瀬田でも若い奥さん方がいろいろやっているところがあるんですよ。まぁ、そういう面白さが、世田谷全国でも街づくりの典型例になっていて、もうあちこちにまちづくり運動が広がっているんですね。
伊佐:いや、本当、最後はやはりいい街を作るお手伝いをしたいですよね。
司会:あ~、すばらしい!
今月のゲストは、ICSカレッジオブアーツ 学長 丸谷博男さん、そして、今日は伊佐ホームズ・伊佐裕社長にも加わって頂きました。ありがとうございました。
春日敏男さん

司会:わたし歳時記。この番組は伊佐ホームズのギャラリー櫟よりお送りします。今月のゲストは一般財団法人 世田谷トラスト街づくり 理事長 春日敏男さんです。どうぞよろしくお願いします。あ、もうお声が聞こえました。今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきます。どうぞよろしくお願い致します。
さて、伊佐社長と春日さん、出会いはいつ頃、どんな形で…?
伊佐:はい、私から申しましょう。私はかねがね、家を作りながら街並みが良くなればいいなあという思いがあったんですよ。それで世田谷(区産業)振興公社の高山さまにご相談しましたら、そういう団体があるということで、春日理事長を紹介いただいたと。
司会:そうなんですね、第一印象はいかがでしたか?
伊佐:いや、この仕事に本当に心を込めてやっておられる方だなと思いました。
司会:春日さんはいかがでしたでしょうか?伊佐社長の第一印象は…?
春日:燃え上がる思いがある方かなと、住まいづくりに対するそういうのを感じましたし。昔、瀬田中の校内に風見鶏のモニュメントを…私担当していまして。その時に伊佐ホームズさんの前を(通って)やっぱり外に対して思いがある、そういう建物だったなという印象が残っています。
伊佐:ちょうどうちの建物の前は、雑木林なんですよ。あれを見てですね、建築よりも雑木林を見て、家を注文に来られた方がいらっしゃる…。やっぱりあそこに、我々の思想が反映しているかなと。通りに対する思い、あるいはどうでしょう、日本の風景と繋がるようなデザインをしていきたいなと思っていまして。私かねがねですね、もともとこの会社を作る前は、大手企業で、どっちかというと宅地造成、街を作っていたんですね。これは時間をかけずに、早く作って早く売るという仕事なんですよ。そういった点では、春日理事長は、この今、世田谷というこの街を、時間をかけて、人のいろんな思いを伝えて、作っておられるなと。こういう継続することが、街を良くしていくなと思いますね。
春日:イベントとかやると、参加者●人という形の評価もあるんですけど、私どもは、出来るだけ、深い、お互い理解し合える、共有できる人を少しずつ増やしていこうということで。もちろん数も、参加者が多い方がいいんですけども、そういうスタンスでやってきました。そういう中で、いくつかですね、困った時に後押し、あるいは一緒にできる、そういう人が全区に増えてきているのかなというふうに思います。
伊佐:我々家を建てましてね、お客様のいろんな困った問題が起こるんですよ。例えば、学者さんでしたら、自分の蔵書がこれだけ不要になると。例えば1万冊とか。僕はね、これをね、図書館の村を作りたいなという思いがあるんですよ。統一されたカテゴリがあるわけですから、それを分散したら価値がないわけでね。これを僕は空き家に持っていて。公立じゃなくても、そういうのがあって、人が集まるような場所…いかがですか、理事長?
春日:いや実は、地域共生の家でですね、そういう「哲学カフェ」じゃないんですけど、普段は自宅で、インターネットで古本屋さんをやってまして、で、オープンカフェという形で、蔵書を積むところをですね、増築するときに、合わせて「地域共生の家」ということで、開放するする空間をやりたいという…。やっぱり同じ思いの方がいらっしゃるのかなという。
伊佐:こういう情報をつかんでつなげるといいですよね、これは。
春日:例えば、世田谷の、祖師谷のですね、21。温泉のですね。あそこもですね、ブックカフェじゃないですけど、(本の)寄付をして頂いて、それをこう脱衣所に展示して。で、休みの日に集まってもらって、その展示した人のオーナーの思いを、その本について、語りあうという、そういうことをやっていたり。
伊佐:いいですね。
司会:いろんな情報…!疎かったですね、私。今聞いて、そんなこともあったんだ…楽しいことがたくさんありますね~。
春日:だから、世田谷でいろんなことが起きているのかなと。どこかでおっしゃったように、つながっていくと、1+1が3になったりですね、そういう計算ができるのかなと。
伊佐:たまたま私の友人の建築家が、宮城県の多賀城市。駅前に図書館を依頼を受けて作ったんですね。見てきまして。これは街の出会いの場ですよね。多賀城もね、やっぱり人口減とかで、非常に駅前が淋しかったんですよ。もう年齢を超えて、そしてカフェがあるもんですから、いろんな人が集っていますね。で、これから、たぶんそういう、本の力っていうのは、僕は大きいなと思うし、で、世田谷でもこう、困った問題を解決しながら、活性化したいですよね。
春日:そうですね。世田谷にも、文学館がございますよね。で、区内にも作家の方がいっぱい住んでいらっしゃいますし、過去にも住んでいらっしったわけですから。
伊佐:例えば、こういう学問の系統だったものが、リストがあると余計動きやすいですよね。どういう本が多いとか。
春日:だから、個人的には図書館もですね、例えば奥沢にある図書館はこういう文献があるとか、玉川に近いところは、少し川についてとかですね、それぞれ特色があると公立の図書館もいいですよね。
司会:それに繋がって、また空き家もなにかこう…
伊佐:少し解消されてねー。
司会:空き家の活用については、社長は、かなりアイディアをお持ちなんじゃないですか?
伊佐:まぁ、空き家じゃなくても、うちは、蔵の移築だとかっていう仕事はずいぶんやってきて。それが蘇って、それがまたこう元気に今生きてる姿というのは嬉しいもんでしてね。例えば、慶応の幼稚舎の蔵、福沢家の蔵を移築して、ある会社の本店の美術館にしました。これがあるからこそ、その建物、他が生きてるんですよ。古いものが来るとね、いいんですよ。新しいものより、古いものが力がある。歴史に耐えてきた力があるんですよ。
春日:そうですね。やっぱり人工物の、コンクリートうちっぱなしもいいんですけども、木造ですとね、その年輪というか、エイジングといいますけども。そこに歴史がにじみ出てくるような、風格がこう出てくるという…
伊佐:だいたい50年したら、真価が問われるんじゃないですか、建物も。それに耐えてきたっていうことは、やはりただ「在った」んじゃないんですよね。耐えてきたんですよね。我々もそういうことを目指して仕事をやりたいなと思いますよ。たまたま凄い話がありましてね。この前、日本の有名な建築会社の副社長までやった設計家なんですがね、一緒に旅しまして。私の故郷の、九州の玄界灘に行きましてね。1泊2日ずっと海を見ておりましたらね、「自分の人生はいったい何だったかな」とおっしゃいましたね。建築を作ってきたことが、自然の美しさに敵わないというか。真価が問われるのは、自然とどうあるかなんですよ。だから私は、植栽があって建物がどのくらいかというのは、植栽のが勝っていますよね。建物よりは。植栽があるからいいように見えているだけであって、本来建物はそこまでいってないなと思うことが多いんで。当社もそのへんはしっかりといいものを作っていきたいなと思っておりますけどね。
春日:やっぱり、いい街って歴史があって、食文化があったり、歴史があったりしてまして。私どもはやはり街を歩くと、そのお祭りというか、ステージがあって、田舎の祭りというのは、企画からですね、演出から、踊る人から、すべてその地域の人がやっているんですね。で、そういう街が、いくつかこう、歩いているとどっかで感じられる。それが建物だったり、広場だったり、あるいは公共施設の使い方だったり、違うんですけれども。区民が主役のですね、そういう街があちこちに、いろんなテーマで広がっていくといいのかなと思っています。
伊佐:私の少年期の体験なんですがね、私の家の前面道路は明治の建物が、約50メートル並んでおりましてね。毎朝みなさん商家ですからね、夏は水を打つんですよ。皆さん、水を打つんでですね、通りのすがすがしさってありましたね。で、建物のデザインが統一されているんですよ。異文化が入ってくる前ですから。特に輸入住宅が入ってくる前といいますか。そういうのが痛烈にありましてね、やっぱりいい街を作りたいというのは、私思いますね、現代に通用する…。
春日:そうですね。そのためには、ひとりのその意志がある人を、一人から二人とこう増やしていくところがですね…。
伊佐:そうですね。いや、理事長のこれだけの組織が、今まで、それぞれの場所において、皆さん団体があるわけですよね。これ全部が手を握ったら凄いですね。
春日:いや、凄い力になると思いますね。今地域の問題いろいろありますけれども、それぞれやっぱり地域には、一番知っているのが専門家ですから。そういうひとたちがそれぞれいらっしゃいますんで。私もお付き合いさせていただいているのは、子育ての問題やっている方もいらっしゃいますし、それから高齢者サービスをやる人もいれば、介護で疲れた人が集まって息抜きをする、そういう場を提供しようとかですね、さまざまな角度でやっている活動がありますので、ぜひとも一緒にですね、やっぱり世田谷は住宅都市ですから、住まいが原点だというふうに思っていますので、ぜひとも一緒に何か新しいことが出来たらと思います。
司会:今日はここまでのお話で、かなりお互いに刺激を受けられた部分がおありだったんじゃないかと思うんです。お二人がタッグを組むと、凄いことがまた起きそうな気がしておりますけれど。
伊佐:やりたいですね、嬉しいですね。
司会:今月のゲストは、一般財団法人 世田谷トラスト街づくり 理事長 春日敏男さん、そして、今週は伊佐ホームズ・伊佐裕代表取締役社長にも加わって、本当に楽しいお話をお聞かせ頂きました。ありがとうございました。
佐藤正一さん
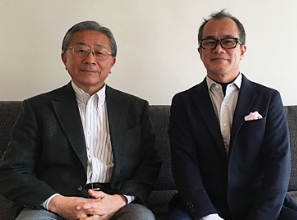
司会:わたし歳時記。この番組は伊佐ホームズのギャラリー櫟よりお送りします。今月のゲストはシナジーメディア株式会社代表取締役社長 佐藤正一さんです。そして今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきます。よろしくお願い致します。
実は、お二人とも福岡の出身という共通点がおありなんですよね。
伊佐:偶然ですね~。ましてや、佐藤さんが行かれた中学校は、私の家から歩いて5分くらいですよ。
佐藤:そうですか。
司会:そのお二人が、東京で出会われたのは何かこうきっかけっておありだったんですか?
伊佐:私はこの世田谷の二子玉川で創業して、29年経ちましたよ。あの頃まだ駅前が閑散としていました。髙島屋はありましたけどね。でもこれから伸び行く街だなという予感があって、ここに会社を作ったんですね。そのあと、ライズが出来たり…、近年ですね。で、いろんな街の分離したところを融合させようという動きを感じたわけでありましてですね。その活動を佐藤さんがされていると聞きまして、これはお会いしたいということで、去年お会いして。酒も飲みましたね(笑)
司会:お会いした時にどうでしたか?佐藤さんの社長のイメージというのは…?
佐藤:いまだに、博多弁の訛りが残っているから、なんかね、初めて会っても初めての感じがしないですよね。それに、あと明るいし、会って楽しくなるというか、こっちもわくわくするという感じでしたね。あと、瀬田の本社ですか?あそこに行かせていただいて。「あぁ、ここ、そうだったんだ~」ここのこれは、伊佐社長のところだったんだなぁって。なんか、あらためて。
司会:いい空間ですよね~。
伊佐:まぁ、私ずっと博多弁はね、私の福岡の近くは砂浜なんですよ。足の裏の砂の感触ってあるんですよ。人間ってふるさとの感覚をなくしちゃいかんなという気があります。それとやはり、一番大事な表現というのは、私は自分の方言のがしやすいなという。私は会社を作った時に、新しい人間が入ってくるときに、一番やはり言葉というのは大事だったんでね、そのためには迎合した表現は出来なかったですね。自分の大事なところで話そうという…そんな感じでしたね。
司会:また福岡弁っていいんですよね、響きが。
伊佐:どうですかね~、ちょっと押しが強くないかなと思ったりして。
佐藤:女の人のしゃべりがいいですよね?
伊佐:博多の?あぁ、そうですか(笑)
司会:そういうところがもう自然におふたりこう影響しあってという感じ…?
伊佐:私は尊敬していますよ。
佐藤:何を言っていらっしゃる!やめて下さい、とんでもない、僕のほうが逆に尊敬して…。
伊佐:放送をね、私も1回、2回、3回と聞かせていただいて、佐藤さんの生い立ちから、その情念というかな、ずっと持っておられるなと。人間やっぱり「志心」がないと、人生ダメだと思いますよね。私も知性があっても、「志」がないと人生は道が開けないなというふうに思いますよね。まさに佐藤さんは、その情念「志」と、頭脳とが相まって仕事をされているなと。
司会:そのバランスがとてもいい方だと。
伊佐:思いますね。特に、シナジーメディアさん、それから、サンカクカンパニー、エリアマネジメンツ。これは見事に三位一体だなと。例えて言いますと、サンカクカンパニーが気体、それからシナジーメディアが液体。二子玉川エリアマネジメンツが、具体的なことなんで固体。この3つが循環しているなという。やったことが次にまた気体化されたり、次は液体化されたりしていく…。そんな感じがして、ますます佐藤さんはこの大事な街で、誰も出来ないことをやってあるかなと思いますね。
佐藤:いやー、とんでもない。そんなほめていただいてありがたいんですけど、まだまだ僕なんか、決して全部が安泰とか安定しているわけでもなくて、日々実はもがいておりまして。それこそ、田舎が福岡に、九州にあるって、まぁわざわざそこから出てきて、流れ着いて今ここでやっている中で。先に、それこそ伊佐社長のようにですね、東京でしっかり事業をやられてですね、こうやってもう足もしっかり地についた形でやってらっしゃる方がいらっしゃると逆に心強いし。だし、僕もやっぱりどこかで、いずれは田舎に錦を飾る的なことをやらなきゃと思いながらも、なかなかそこまで行けずにですね、もう本当にぐるぐるぐるぐると走り回っている感じがあって…。
伊佐:その気持ちわかりますね~。田舎を出てきたわけですから、田舎に何をもって返せるかというか…自分の人生の。今仕事はこちらですけど、昔の仲間とか、両親とか、祖父母、地域の人に、自分はこうしたんだよということを持って帰りたいですよね。
佐藤:そうですね。ですし、今があるのも、たぶんベースはそこで生まれ育った感覚とか、その時の環境とかが、今いろいろな形で僕を作ってくれていると思うし…。
伊佐:初めね、行政の限界、企業の限界、ボランティアの限界をおっしゃったですよね。私本当それ思うんですよ。みんな限界なんですね。私はたまたま今住宅作りから、埼玉県秩父の林業と取り組んでいましてね。やっぱり、ボランティアはボランティアの限界があるんですよ。やっぱり経済的なことが機能しないとダメ、経済に理念がないとダメ、それを一緒にやっていく人間・同志が必要だということで。我々は今、日本で最初の林業の取組みをやってましてですね。林業家、製材所、プレカット工場、私共、そして消費者、これが同志になればですね、新しい夢が開けるんですよ。特に今、私の場合は、林業というのは大変な今危機にありましてね。やはり森林というのは100年かかるんですよ。今、一年間に1億立米という木が生産されるんですが、使っているのは2千万立米。8割がムダになっている…で、このままでは森が成長しない。それを改善するのも、ボランティアではなくて、やはりひとつの企業化、志の連動ですよね、連携ですよね。今日は街のことで連携ですが、私は林業と。一つの縦軸といいますかね、そんなことをやっていますね。
司会:今のお話を聞くと、また何かこうアイディアが湧いてくるのじゃないかなという気がしたのですが…。
佐藤:そうですね、社長が捉えられている時間軸というのが、100年とかね、そういう流れの中で何が出来るかというところでみられているというので。僕なんかも今、街の取組みということで、再開発がひと段落して、ここから3年、5年、10年、途中でオリンピックがあったりするでしょうけど、その先。もっと100年後とかっていうことを、見据えて何が出来るのみたいなことは、地元の方たちはけっこう、町会の皆さんとかは100年先を考え…みたいなことは結構考えていらっしゃいていて。僕なんかはそこまで見れていなくて、目の前のことをやっていますけどね。でも林業とかというのも、可能性、もったいない感じがしますよね。確かに。僕ら二子玉川って、川なんですけども。川は、やっぱりその山から…。
伊佐:…(山)あってこそですね。
佐藤:だから、この川と、上流の森林・森との関係性みたいなやつは、いずれちょっと面白い仕掛けを作っていきたいなぁって気がしますよね、何かね。
伊佐:佐藤さん、私の山の仲間にいっぱいいますよ、その辺の観察者が。ある人は、川尻から始まって、山の疲労を知って、林業の再生に向かっていますよ。魚が変わってしまった。それから味が美味しくない、で、いなくなったことから、いかに山が疲労したかということ。特に水際の木は必要なんですよ。これが全部針葉樹になりますとね、生物が生息できなくなるんですよね、卵を産み付けないとか。非常に水際が大事なんですね。
佐藤:なんか(東京)都市大の涌井先生が言われていたのは、確か「森林は肺だ」って言われてましたね。それで川は血液だとか言っていて。いかにいい空気をつくって、それをいかに下流まで流していくのかというようなことを言われていましたけど。
伊佐:やっぱり100年かかって山が育つ中で、いろんな生物が生息できるというかね。
司会:なんかお二人が一緒になると、新たにいろんなことが展開できそうな…そんな感じがいたしますね。
佐藤:いやー、是非、なにかできることがあったら是非お願いします!
伊佐:こちらこそ、お願い致します。
司会:どうでしょうか?一番これが影響を受けたなというようなことはおありですか?伊佐社長は、佐藤さんから…?
伊佐:いや、私はね、非常にITが弱いし、もう手で触ることしかわからない人間なんでね、ITが本当に見えてないんですよ。それを佐藤さんは楽々と両方されていると。私は右手だけで生きている、左手も欲しいなと思ってますんでね(笑)そういう点で、私の師匠になってほしいなと思いますよ。
司会:佐藤さんはいかがでしょう?
佐藤:伊佐社長は…まぁ僕の中では、やっぱり家とか、一人の人が1年2年で使い切るものではなくて、下手すると、というか、社長が作られているやつは、3世代とか考えて作られていると思うんですけど。あぁいう形に残るものを、人と向き合いながら、一つのものとして作っていくということは、僕には出来ないこと。そういうことに向き合っていらっしゃる事業っていうのは、僕はすごく感動するし、憧れますよね。もうできなから単純に。出来ないからこそ憧れますね、そういうところはね。
司会:それぞれの良さを感じて、これからまた、ますますお二人、私も楽しみにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。「わたし歳時記」今月のゲスト、シナジーメディア株式会社代表取締役佐藤正一さん、そして、伊佐ホームズ・代表取締役社長、伊佐裕さんにも加わって頂きました。ありがとうございました。
矢野弾さん
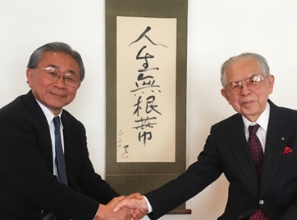
司会:わたし歳時記。この番組は伊佐ホームズのギャラリー櫟よりお送り致します。今月のゲストは月刊カレント 株式会社潮流社代表取締役 矢野弾さんです。そして今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきます。よろしくお願い致します。
さて、お二人はご出身が同じ福岡県でいらっしゃいます。矢野さんは3歳までということですが、実は福岡県人会の副会長。
矢野:そうですね、恐ろしいことですねぇ(笑)
司会:そして、伊佐社長も県人会に…。
伊佐:はい、入っておりましてね。5年になりましょうかねぇ、矢野さん。
矢野:そうですねぇ。
伊佐:矢野さんが県人会でご挨拶されたんですよ。で、私初めてお目にかかったんです。いや、お目にかかったというか、私は聴衆の一人ですよ。ただ、何人かのお話の中で格別のお話をされたんですよ。この方はただの方じゃないなと思いましてね。もちろんお名前は存じておりましたよ。で、是非、終わった後にですね「矢野副会長、今日一杯いかがですか?」というお願いをしたわけですよ。「そうか、行こうか!」ということで、ですね。渋谷の裏のほうのしみじみとした店に行ったわけでありまして。それ以来、こうやって師匠として私は崇めてお付き合いをさせて頂いてるという…。
司会:今、師匠というお言葉がありました。いろんなことを学んでいらっしゃる…?
伊佐:盛年らしい師匠といいますかね、ご年齢からいくと、相当のご年齢でおられるんですけれども、ますます盛年という感じですね。いかがでしょうか、矢野さん。
矢野:年は隠せないもので、85歳になりますね。で、その85歳ということを考えますとうちの父は66で旅立ちをしましたから、そういう意味においては、私は父をこれで大きく歩を踏み出すことができたんだなと思ってます。で、特に伊佐社長がもっている、このなんて言うのでしょうか、ちょっとこう寄ってこられる感じがですね、人の心をつかむのがお上手な方だなと思いました。それは話題の中で、その中から何かを自分がつかんだという形で提示なさるわけですね。そうすると、そのことに関しては共に考えたいという共感性を呼ぶわけですから、人の共感性を呼ぶこの人間学というのを持っていらっしゃるなあと。それが私の関心事になっていたと、言っていいんじゃないでしょうか。
伊佐:いや、非常にありがたい言葉を頂戴しましたけれども、私はまた、矢野さんという方は、心底胸のうちというのがいつも青年隊のことを思っておられるので、そこの部分に私は甘えられるといいますか。一流の方というのはだいたいその部分が私はおありになるような気がしますね。だから自分が考えていいと思ったことは、その方にぶつければ、今矢野さんからおっしゃっていただいたようなことで道が開けるというか、アドバイスを頂けるということだと思います。特にご縁が深まったのも、私どもがやっております「世田谷児童絵画展」ですね。これが、初め、私の発想であったのですが、なかなか実現できなかったのですが、矢野さんの大変なご援助でやれたと思っておりますので、会社にとって大変な恩人であります。
矢野:特に児童展というのは、子供ですよね。子どもは未来の王子様、王妃様ですから、そういう意味においては、子供のことというのは絶対に忽せにしてはいけないなと。特に教育の問題でこれは言葉が過ぎるのかもしれませんが、子が親を殺す、親が子を殺す、そういう近親憎悪という形のものが最近特に多いものですから、これはもう、絶対、子どもということに関しては大事にしなければいけない。それは、大事にするということは、知らしめること、よらしめることだと、こう思ってるものですから、それで、それに手掛けるという方はなかなかの人だなと。そう思いました。ですから躊躇なく手紙を書いて、教育長にお便りをしたんですね。そうしたらそれがトントンと開いたようでございまして、うれしいことです。
伊佐:もう3回絵画展があったのですが、これから将来の絵描きさんが生まれるかなと。それ以上に子供の絵の素晴らしさに我々が教えられるということが多いですね。
司会:矢野さんは、時代をバトンタッチしていかなければいけないんだということをおっしゃっていましたけれども、伊佐社長にも一つバトンタッチ、そして次の世代の子供たちにもという思いがおありですか?
矢野:伊佐さんは私、年の差を感じないんですよ(笑)。
伊佐:いや先ほど、前回(2回目)の放送を思い出しておりましてね、ただ私利私欲じゃなくて、世の中のためになることともに経営があるという、本来経営というのはそういうことだと思うんですよね。共に成り立つというかな。私ども、今、林業との取組み、ひいては、それは森が守れるということなんですね。環境問題とかやっておりまして。そういう生き方がまた、非常にお客様と共感できるものがつながるというふうに確信しておりまして、大きな視野で経営していきたいなと私も思っております。
矢野:ここ(ギャラリー櫟)の場所そのものが、そういう感性を充満させていますもんね。だからそういう意味においては、絵一つ、あるいは障子を見ても「あぁ、おぬし、やるな」という感じですよ(笑)。
司会:今、経営ということもお話が出ましたが、矢野さんは世田谷商人塾の顧問でもいらっしゃいます。やはりそういう意味では、世田谷も自分たちの手で温めてというようなこともお考えでいらっしゃるのでしょうか?
矢野:これはですね、実は、千歳烏山の商店街があります。そこに私が講演に行ったんですね。その時の青年部長が桑島俊彦さんという方でした。で、私の話を聞いて共感をして頂けたのですが、いずれまた出会いをする機会があるのかなというふうに思っておりましたら、この方が世田谷商店街の会長になると。そういうことの中で、望月先生という、照彦先生が登場するわけですが、その方のお話を聞く会があって、私も出たのですが「あぁ、いいお話されるなぁ」ということで。その時に、桑島さんと望月さんの中で商店街の中の勉強会を作ろうというような機運が出ましてね。それが世田谷商人塾、ざっと現在11期生ですか。私当初から接点を持ちたいというんで、私の持ち駒1コマあるんですけど、全部に出てフィードバックしようということで、全部出ているんですね。これは、自分の出番はペイがあるんですけど、他はペイないんですよ。ただそれは自ら知るということがフィードバックの最大の原点なんですね。それが無かったら語れません。
司会:こういうところも、伊佐社長、やはり学ばれるところですね。
伊佐:凄いですね。今のお話を聞いて、ますます、本当に矢野さんの…、なんでその…、矢野経済を作られた時のことと同じですよね。
司会:こういうふうなお話をしていると、1回目はお酒の席というふうにお聞きしましたが、話もお酒も尽きることはないような気がいたしますが…。
伊佐:そうですね、今2週間に一度はお会いさせていただいておりますでしょうかね。
司会:さぁ、このご縁、これからお二人はどんな風にしていこうとお考えでしょうか?
伊佐:私にとっては、経営のありよう、また、大変私も世田谷の街の発展に関係しているものですから、いろんなことで矢野さんのご指導を頂いていきたいなと思いますね。
司会:伊佐ホームズも、もう世田谷で30年でいらっしゃいますものね。
伊佐:そうですね。
矢野:やっぱり生きるということは、要するに生かされるんだなぁと。その生かされる縁の中で、未来を考えるということが大事だなと。で、私は、点線面球の思考方法というのを自らの中に作ったんですけれど、その中で、最終的に絞り込むと3つになるんです。原理原則に戻れ、2番目は、歴史に学び、人間に学べ、と。3番目が未来に対する志を持て、と。未来に対する志を持たないとですね、ロマンが生まれないんですよ。ロマンが生まれないと、仮説が生まれないんです。仮説が生まれると、プランが生まれます。
伊佐:おぉ。素晴らしい話ですね、矢野さんも。
司会:これからもお互いに刺激をし合い、影響を受け合ってということですね。今日は、お二人のお話、楽しいお話でした。「わたし歳時記」今週のゲスト、株式会社潮流社代表取締役 矢野弾さん、そして、伊佐ホームズ・伊佐裕社長もお話して頂きました。ありがとうございました。
株式会社三恵 代表取締役
飯島祥夫さん
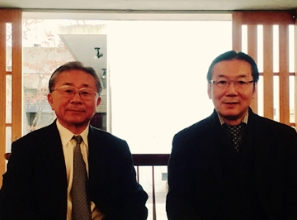
司会:わたし歳時記。この番組は伊佐ホームズのギャラリー櫟よりお送りします。今月のゲストは三軒茶屋銀座商店街振興組合理事長 飯島祥夫さんです。そして今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきます。どうぞよろしくお願い致します。
さて、お二人は今日が初対面でいらっしゃいます。第一印象はいかがですか?
飯島:いや、もう見るからにいい方だなという…。
伊佐:そうですか?九州の匂いをたっぷりとつけていませんか?(笑) 私から見るとね、三軒茶屋の方というのは、私は博多なんですけどね、生まれが。おしゃれだなと思っています。
飯島:いや~ありがとうございます。
伊佐:実際東京に来て三軒茶屋を知ってみますとね、おしゃれの奥に温かさがあるなという…、素朴さがあるなという…。まぁ東京の街でいえば、吉祥寺と三軒茶屋に非常にそれを感じますね。中野はもう少し雑然としているかな、三軒車屋と吉祥寺には、大変こう、山の手に近いところの温かさといいますかね、素朴さというか、感じますね。
司会:どうでしょうか?飯島社長、今のお話。
飯島:そうですね。ただ、私もう三軒茶屋生まれの三軒茶屋育ち、このまんまなもんですから、逆に素朴とか言われちゃうといかがなものかなというふうに思ってしまう部分もあるんですけど(笑) やっぱり渋谷だとか青山に憧れをもって育っておりますのでね、でもやっぱりそういうところが三軒茶屋の良さだなと…。
伊佐:なんか肩を触れ合うような商店街というのが大事じゃないでしょうかねぇ。
飯島:そうですね。
伊佐:実はね、私の生まれ故郷の、博多の私の家の前の通りも1.5キロ商店街が続いているんですよ。
飯島:あら、すごい長い商店街ですね。
伊佐:1.5というと、日本の中でもなかなか珍しいようで。今回「サザエさん通り商店街」とうのに全体がなりましてね。長谷川町子さんのご生家の近くなんですよ。それと私もこの街の魅力として、大きな箱の中の魅力もあるでしょうけど、やはりこう平面の中の回遊する街の魅力というのは、やはり根本はそこだなと思いますよね。それに温かいということ、そしておしゃれだということかな、両方を求めますよね?
飯島:そうですね。横道とか裏道に出ると新しい風景が広がって。で、次々とね、新しいシーンが生まれてくるというのは、やっぱり街歩きの魅力だというふうに思います。
伊佐:特に私は、街は路地が好きなんですよ。
飯島:あ、路地はいいですね~。
伊佐:私はよく歩くんでね。表通りじゃつまらないんでね、裏側をこういろんなふうに様子を伺いながら…。
司会:そうすると新たな発見があったり…?
伊佐:そうですね、屋号だとか、暖簾にですね、奥が見えるわけですよね。飲み屋でしたら今度来てみようとかですね。本当にそれが好きなんですよ。
飯島:本当にいいと思います。ただ路地もやっぱり整備されていかないと、歩きやすさがないんですよね。まぁ、三茶の三角地帯はああいう状況で、混沌とした中にも面白さがあるんですけども、もう少し整備されたら、もっといろんな人が歩けるのになあというふうには思うんですけど。
伊佐:私は、国木田独歩の「武蔵野」だったでしょうか。あの頃のいろいろな武蔵野の風景の描写を読んで、それを読むと三軒茶屋という由来といいますかね、それと今の栄を思ったりしてですね。なんでしょう、農村地帯からあそこに人が集まってきて都市部との接点だったんだろうなというふうに思うわけですよね。
飯島:そうですね。今でも三軒茶屋は、住んでいる方もいらっしゃるし、実際に働いている方もいらっしゃるということで、非常に不思議な感じの空間になっているかなと。もう働いている人だけ、遊びに来ている人だけというような、毛色の決まった街ではない…。
伊佐:そこが面白いところですよね。全国に茶屋とかつく地名ってどうなんでしょうね。大阪に天下茶屋というのがありますよね。これ、恵まれた地名ですよね、町名というか。
飯島:お花茶屋とかね、いろいろありますけども、やっぱり恵まれてると思います。
伊佐:大事なこう名前の由来を…大事にするとよろしいですよね。
飯島:そうですね。で、地方から来た人が「三軒茶屋はどこなんだ?」って言われるのが残念だなと。
伊佐:あぁ、そうか、ズバリね。そういう点ではないでしょうね。
飯島:そうですね。だから、三軒茶屋の観光にはやっぱり「三軒茶屋」を、3つのお茶屋さんを作るというのが、ひとつ一番いいのかなと。
伊佐:なんかルーツの復元のようなものがあるといいですね。それ欲しいですねぇ!
飯島:欲しいんですよ!是非伊佐社長のほうからもおっしゃっていただけたら(笑)
伊佐:いやいや。建築的にも面白いですね、それは。時代の中で。
司会:社長、なんか今アイディアがこう湧いてきているんじゃないですか?
伊佐:浮かびますね。面白いですねぇ。
飯島:そうですよね。幕末の頃から歴史の交差点ですから。吉田松陰さんのところがあったりとか、井伊直弼さんの菩提寺があったりとか。
伊佐:歴史散歩の出発点でもいいですよねぇ。
司会:ますます三軒茶屋が楽しくなっていくような…お二人のお話を聞いているとそんな感じがしますが…。
伊佐:いかんせん、私夜歩くことが多いので改めて昼歩こうと思います、これから(笑)
飯島:是非是非、よろしくお願いします。
司会:社長、三恵さんのお店の中は覗かれたことは、じゃあまだないですか?
伊佐:あります、あります。夜のお店はあります(笑)
ただ茶沢通りにつきましてはね、よくこれだけ下北に向かって、非常に信用できそうなお店が並んでいるなと、堅実なお店が並んでいるなという感じが、車で通る度にいつもありますね。1軒1軒違いますよね。様子が違う。いい店でしょうね。信用が多い店が並んであるなというのが不思議に感じますね。
飯島:ありがとうございます。本当にそういっていただけるとありがたい。昔からのお店が多いですね。ただ、今、やっぱり世代交代の時期に入っていまして、昔からの商売じゃなくなってきているところが多いのが残念かなあとは思っています。
伊佐:まぁ、でも景観というね、よく我々、街の景観、美しくて近代的にすればいいというふうに思われがちですが、その中にやっぱり温かさとか、それがあって初めて成り立つのでね、そういう両方を両立したいですよね、街というのは。
飯島:そうですね、やっぱり温かくなければね、一日過ごしていたいとは思わないですよね。
司会:それと合わせて「安心・安全」というのは、この前もお話の中にもありましたけど、そんな街でなければということですよね。
飯島:そうですね、やっぱり「安心・安全」は第一かなと。私どもでも防犯パトロールですとか、消防のカチカチみたいなこともやっておりますけれども、そういう日常的に顔見知りをたくさん作っていくというのが必要なのかなというふうに思います。それはイベントを通して、いろんな方と実際にお仕事を一緒にするとよくわかるので、そういうことをやって三軒茶屋の街を活性化していきたいかなというふうに思っています。
司会:なるほど。あの、三恵さんは創業もう60年近く…?
飯島:62、3年になると思います。
伊佐:当社が今年で30年です。
飯島:あぁ、おめでとうございます。
伊佐:半分ですね(笑)
飯島:いや、とんでもないです。でも初代でいらっしゃるんですね。
司会:どちらも長く地域に根差してということで、やはり何か目標にしてらっしゃることとか、心がけていらっしゃることがおありなんじゃないかと思うんですけど…?
伊佐:我々は建築をやるわけですけれども、その建築がそこに建ったので、街の景観とか変わったというようなきっかけになればなと思います。ただ美しいだけじゃなくて、お店でしたら流行る、繁盛する、そして何か変われるきっかけになればいいなと。実際、ある程度広い通りで、いい建物作ってきましてね、大変な高い評価を頂いていたりしているところもあります。
司会:よくゲストの方にも、街を通っているとホッとするというふうなお話も聞きますが、三恵さんはいかがでしょうかね?
飯島:やっぱりあの…そうですね、私どもとしてはお店が街の中の日常の中に入ってくれれば一番いい、そのままこう、ふ~っと入ってきて、あぁあそこにあるものを取って、で、レジ行って、ひゅーっと帰れるというような、もう日々の暮らしの中にうまくはまり込んでいけたら一番いいのかなというふうに思います。
司会:私もお店にお邪魔した時には、妙齢のおばさまと言っていいのでしょうか、ものすごい賑わいでした。だからおそらく三軒茶屋に来たら三恵さんに入って…というのがもう染みついているというか…そんな感じが致しました。
伊佐:定番のコースなんだ。
飯島:今、介護施設ですとか、ホームにも、ボランティア的に伺っているんですけども、「歩けたときは来たわよ。」というような方たちもいらっしゃるので、新入社員なんかはそういうところに行かせると感動して…結構疲れながら帰ってきます。いろんなお話を伺えるので…、またそれはそれでいいかなと、会社のためにもなるなぁというふうには思っています。
司会:本当に幅広く愛されているお店という感じですね~。
伊佐:客層がそうやって多世代に渡るということは、社員教育にはいいでしょうね。人生観が広がりますよね、それは。
司会:伊佐ホームズさんもやはりそういうところは意識されていらっしゃいますか?
伊佐:そうですね、うちはもう全面的にお客様とお付き合いしないと、住宅の設計というのは出来ませんので、作る前、作るとき、作った後、20年以上もお付き合いしているわけですから、それは本当に社員が鍛えられますよね。私、社員教育はお客様にやっていただいているぐらいだと思います。それはすごい変わりますね、社員たちが。
司会:それは、先ほどの飯島社長の話ともつながりますね。お客様とのつながりが、お店を、会社を大きくしていくということなんですね。
飯島:会社の社風が優しい感じがいいと思います、伊佐ホームズさんもねぇ。
伊佐:うちは8時の掃除から始まるんです、皆で。これは一日も欠かしたことが無くて。これはいいですね。
飯島:へぇ、やっぱりね、お掃除は重要なことだと思います。
伊佐:私、掃除の姿を見てね、本当に気持ちが入っているかどうかって見えますよ。これは他の会社さんの前を見てもわかります。腰が入っているかどうかっていうのがあります。それは何でも大事なことにこう、嫌なことでも入るかどうかっていうのが大事だと思いますね。いや、すべて嫌なことと思わないことが一番大事ですよね。受け入れるというかな。
飯島:そうですね、やっぱり日常になっていないといけないですよね。
司会:今日はどうでしょうか、お互い刺激を受けたところもありますか?
飯島:いやいや、本当に刺激を受けました。ありがとうございました。
伊佐:私は、先週、先々週とね、やっぱりイベントのこととか共感する方をいっぱい呼ぶというのは、大変勉強になりました。
飯島:ありがとうございます。
司会:これからまたますますつながりが出来てくるかと思いますが、今日はお二人ありがとうございました。
飯島・伊佐:ありがとうございました。
司会:今日は、三軒茶屋銀座商店街振興組合理事長 飯島祥夫さん、そして、今週は伊佐ホームズ・伊佐裕社長にお話して頂きました。ありがとうございました。

外山京太郎さん
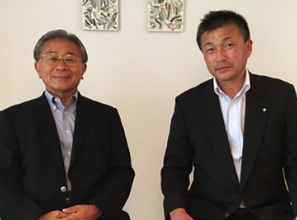
2016年11月 [第2週] 放送分
司会:わたし歳時記。この番組は伊佐ホームズのギャラリー櫟よりお送りしています。今月のゲストは、群馬県川場村 村長、外山京太郎さんです。よろしくお願い致します。そして今週・来週と2週に渡りまして、伊佐ホームズ・伊佐裕社長にも加わっていただきます。社長、よろしくお願い致します。まず、お二人はどんなふうに出会われたんですか?
伊佐:いやー、まだ村長とはね、今日まだ3回目なんですよ。しかしながらね、本当に尊敬する兄弟と会ったような…年齢はね、私のほうが上なんですがね、村一筋に生きてこられた村長のお姿が、なんでしょうね、旧来の友というか、旧知の友という思いがしますね。きっかけは、世田谷区からのご紹介で、オリンピックに備えて、アメリカの選手団のホームタウンに世田谷区がなるということで、ついては提携している川場村にも、選手団等ご案内したいということで、そこでいろいろな日本文化を表現したいということで、建築的な相談もしたいということで、世田谷区のほうから川場村さんを紹介頂いたと。そんなことでしたね。
外山:はい。
司会:村長はいかがでしたか?伊佐社長の第一印象は?
外山:本当に、まだ期間的には短いんですが、いままでやったことを考えるとですね、それぞれ、私が川場村の一本の木であって、社長が世田谷区の1本の木であったんですが、木と木が合わさって林になって、もうまもなくそれが森になるような話がですね、短いんですが、深くそういう話に盛り上がっているというとこだと思います。
伊佐:私はね、高校の入学、今から50年前、ちょうど今有名な大分県の湯布院。そのころ駅前はお土産屋さんは2件くらいでした。もう閑散とした田舎の温泉場でした。私は高校入学前に、春休みに行きましてね、なんと素晴らしいかと思ったんですよ。今から50年前に。なんでしょうね…、見た瞬間にそういうのがあるんですね。それはやっぱり日本人の心の中にある「風景」があったと思うんです。今回、私が川場に行って思い出すのは、湯布院での感覚に似ているんですね。そして、なんでしょう。人は少ないですよ、村に、川場さんも。しかし、生き生きとした村というのはわかりますよね。やっぱり田んぼの作り方ひとつとっても、心が入った田んぼというのは美しいなと思いますし。どこか投げやりなところは、田んぼの苗の並び方が荒れているんですよ。私ね、絵を描くものですから、山には田んぼがあると近景がいいんですよ。田んぼがあって初めてね、日本の風景だなというのがありましてね。四季折々、春先の早苗から始まって、あるいは、山の稜線が田んぼに映るのもいいし。そういうこともあって、直感的に、川場に行って大変なファンになりました。
外山:ありがとうございます。本当に嬉しい話でございまして、そういう中で、やはり社長が、昔見た、生まれ育ったところと川場が変わらないというとこなんだと思いますが、そういう中で、川場村はですね、関東圏内で52市町村が世田谷区との(縁組)協定に手を挙げて。で、川場村が選ばれたわけですが、その理由が「何もない川場」というとこですから、やはりそれを守っていかなければならないと思っております。
伊佐:しかし、今思いますと、理想的な「結婚」をされたなという気がしますね。
外山:はい、そうですね。
伊佐:そうですよね。いや、私はね、小さいころ母が忙しいので、夏休み・冬休みは、母の実家が農家なので、そこに行きますと楽しくてね。魚とりは出来るし、昆虫採集は出来るし、私にそれがなかったら、たぶん、なんでしょう…。自分の滋養分が育たなかったかなという気がしましてね。足りないことが出来たというか…そういう点で35年前に、世田谷区にとって足りない部分を川場に求められたというのは凄い発想ですよね。
外山:それが東京の中でもやはり世田谷区というのは違うのかなと思います。
伊佐:鈴木(忠義)先生ですよね、初めのこう…。
外山:そうです。もう鈴木先生がやはり川場村を見出していただいて、また、川場村のいいところをどんどんどんどん…ひっぱっていただいて、今日まで育てていただいたと思います。
伊佐:凄い仲人役というか、推進役がいらっしゃったわけですよね。私もこの前お会いしましたけれど、92歳で、お元気お元気で…。まだ現役の学者さんですね。
外山:もうあの先生が全国の中でですね、要するに都市工学等いろいろの中で、やっぱり川場の素晴らしさをずっと思っていただいたんだと思います。
伊佐:だから、鈴木先生のお元気さも、そういう良き仕事をされて、良き風景をお持ちだということなんですね。
外山:そうです。鈴木先生自体がもう30数年、川場(ふるさと公社)の社長をやっていられて、そういう中で、川場の、我々にですね、ないところを伝えていただいたんだと思います。
伊佐:でも、そのふるさと公社をお作りになったところで、やはり、結合したものがあったというのはまた大きいですね。
外山:そうですね、はい。
伊佐:気分的な友好関係ではなくて、やはり一つの形があるというのは、大きな魂が宿ってきますよね。
外山:今、全国の中で、いろいろな形で都市との交流はあるのですが、川場は世田谷と、要するに「結婚」をしたということですから、他よりも、より絆が強いということなんですね。
伊佐:本当にそう思いますね。皆さんのやりとりを聞いてもそう思いますね。心許した者どうしの…、行政の方どうしの話が非常にお互いを認め合ったご発言が多いですよね。
司会:そのさらなるバージョンアップを目指して、共同声明も発表されたと聞いておりますけれど…?
外山:はい、56年に縁組協定をしてですね、節目節目にいろいろな形で、また確認行為をやっているんですね。そういう中でちょうど今年は35年を経過しましたので、今度はエネルギーについて、川場村と世田谷がいろいろな形で協力をしようということで、また協定を結びました。今、世田谷区もですね、自然エネルギーのほうに移行しておりまして、そういう中で川場村も今度はバイオマス等を使ってですね、要するに木を使った形での新しいエネルギーを使おうという中で、世田谷と今後いろいろ検討しようというところであります。
伊佐:まさに、時代が必要としていることを前もってされているなと思いますね。
しかし私も、会社を創業して約30年になりますが、世田谷でしてよかったなと思いますね。本当に私も、仕事が世田谷で育てられたなという思いもしますし、こうやって、こんな同志とのご縁を頂戴した喜びでいっぱいですね。
司会:今、伊佐社長から世田谷に来てよかったというお話がでましたけれど、外山村長からご覧になった世田谷の魅力…どんなところでしょうか?
外山:はい、当時はですね、川場村が、人口が4千人、世田谷区が80万人だったんです。と、格差がちょうど200倍ございまして、よく言われたんですが、世田谷区の職員がちょうど4千人くらい。そういうなかで、川場の村民と世田谷区の職員が同じ規模だという中で、いろいろな人がおられたというところがひとつある、また、世田谷の公立の小学校5年生が必ず川場に来ていただいた…これがやはり大きいことだと思います。
伊佐:私もね、子供が5人いました。上のほうはもうだいぶ大きかったので行ってないですが、下二人は川場へ。私も非常に川場の名前は残っていますよね~。授業で行くというのは大きいですね。
外山:そうなんですね。ですから、お父さん、お母さんは川場を知らなくても、子供はですね、2泊3日で川場に来ていただいているものですから、川場で食べたあれが美味しかった、これが美味しかったと、そういうふうに言っていただけるので、それが大きな財産だと思います。
司会:外山村長ありがとうございました。今日は伊佐社長とお話を頂きましたが、お二人まだまだお話し足りないところがあるように思います。来週も引き続き、お二人の対談をお送りしたいと思います。わたし歳時記、ゲストは群馬県川場村・村長、外山京太郎さん、そして伊佐ホームズ・伊佐裕社長でした。おふたり、どうもありがとうございました。
外山・伊佐:ありがとうございました。
2016年11月 [第3週] 放送分
司会:わたし歳時記。この番組は伊佐ホームズのギャラリー櫟よりお送りします。今月のゲストは、群馬県川場村 村長、外山京太郎さんです。よろしくお願い致します。そして、先週に引き続き、今週も伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきます。よろしくお願い致します。さて先週、お二人の出会いからお聞きしました。原風景、いろいろなところでお二人の共通点があったように思いました。
伊佐:そうですねえ。村長、「雪ほたか」の苦労話を改めてお聞きしたいですね。
外山:はい。この川場の「雪ほたか」はですね、全国米食味コンクール(全国米・食味 分析鑑定コンクール)の8年連続金賞をとって。昨年は1年お休みしたんですが、必ず今年は9年目の金賞がとれると自負しているところでございますが。やはり少ない耕地の中で、川場村は一生懸命米作りを昔からやってたんです。そういう中で、ブランドを作りたいとうことで、前村長が心血を注ぎまして「雪ほたか」が誕生したというところだと思います。
司会:本当に米は原点ですよね、風景的にも田んぼが原点だと思いますし、うらやましい話ですよね。
外山:やはり農業にとっては米を作るというのが、原点の農業であり、美味しい米、これを追及するのが、農家の夢だと思います。
伊佐:あのー、水が大事でしょう、村長?だから素晴らしい環境の証明なんですよね、美味しいお米というのは。
外山:そうです。ただ、水があるということではなくて、やはり美味しい米を作る美味しい水を作るにはですね、きちっとした山があって、山から湧き出る美味しい水にならなければならないと思います。
伊佐:私も建築業からだんだん林業の問題に関わりましてね。山の方たちと会いますとね、非常に自然環境の問題に対して皆さん研究されていて。ある人は川の魚釣りから始まって、いかに森林が荒れたかを知って林業に取り組んでいる仲間がいますけれども、本当に森林と環境の問題って大きいですね。
外山:そうなんですね。やはり魚であり、また動物であり、いろいろな形の中で、生きうるものが、山と自然に携わりながら生きているというのがありますから、それがやっぱりバロメーターにもなるかなと。
伊佐:そうですね~。やはり羨ましい話ですね。あと、川場の木材、杉が中心だと思いますけど…。
外山:はい、もう世田谷と交流を始めて35年経ったということは、35年前に植えた木も、もう間伐の時期に入っているということなんだと思います。一度人間が苗を植えて手を携えたものは、その木を切るまで、いろいろな形で手を携えていかなければならない、と言われているんです。昔から「山の肥やしは人の足あと」だと言うんですね。木を育てるには、一回でも多く山の中に人が入ることがいい木を育てる、これが昔から言われたことなんですね。
伊佐:あーいい話ですね、肥しですか。でも、世田谷でも川場の木を使った家が建つとよろしいですよね。そのへんの今までの動きというのは…。
外山:はい、前ですね、世田谷区のほうは、公園ですとか、公共施設を作るときに、設計の段階で、川場の木を使用というのを設計書に入れていただいていたんです。そういう中で、公園のベンチがあったり、公共施設の中で、若干ですが、川場の木を使っていただいたというのが、かつてあったんですが、それをまた復活をしてですね、今後世田谷区でも、学校を建て替えたり、区の施設を作るというような話が非常に多くなってきましたので、そういう中でどんどん川場の木をつかっていただこうということで、今、一生懸命営業しているところでございます。
伊佐:じゃあ私もそれをお手伝いしたいですね。子どもたちにとって、木で育つということは大きなことで、大変精神的にも医学的にも落ち着くそうで、授業の内容も変わってくるというふうにデータも出ているようなんで、大事だと思いますねぇ。
村長、ちょっと私の話をいたしますがね。私の古き友人が家具のデザイナーなんですが、今回の東京オリンピックの件で、国から呼ばれてですね、いろんな椅子、家具を作ってくれということで。彼は、大変意気込んでいましてね、全国の木の産地に、プラス職人、その職人のオリンピックだと。それぞれの各県の木の良さ、そして職人に出てもらって、オリンピックをしたいと意気込んでいましてね。今回のイベントをきっかけに、そういうことが起こるかもしれませんねぇ、いろんなことが。
外山:まさしく、それは技能五輪につながることなんだと思うんです。やはり技術だとか、そういうものは、やっていることによって語り継ぎであったり、また技術を伝承するということがありますから。どんどん更新をしなければならないと思いますね。
伊佐:ちょうど世田谷区さんから、今回川場村さんをご紹介頂いたきっかけも、当社がお茶室をよくやっているということを、世田谷区の方が耳にされてのご紹介だったんです。お茶室というのも、本当に技能の伝承なんですね。現場がないと、なかなか伝えることが出来ない…幸いうちはそういうことが多いものですから、そのご縁なんですね。
外山:まぁ、なかなか最近の建築は、木を使わなくなったり、昔でいう床柱を使うところを使わなかったり…そういうのが増えてきたもんですから。それはまた原点に戻して、そういったものを使うような建築をしていくと、また林業がより活性化になるかなというところだと思います。
伊佐:私はやはり人が家を作りますがね、家がまた人を作ると思っておりましてね。私はそれを確信しておりますので、豪華な家じゃなくてもいいから、本物の材料で家を作るということが大事だと思います。
外山:そういう中で、世田谷区の中でも、子供さんが育つ教室に、川場の木材を床であったり、壁であったり、机であったり…そういうところで使っていただくと、より子供が安定してすくすくと育つ、そういう環境が整えられると思います。
伊佐:デザインが画一じゃないですよね、木の目は全部違いますよね。あそこに多様性があるんですね。一人一人違っていいんですよね。そこで落ち着きが出てくると思うんですよ。単なる真っ白だったら非常に不安定だと思いますね。心の折りようがないというかな。それが木目というのは不思議な安心感を持たせますね。
外山:木も一年を通じてですね、特に川場なんかは、冬には1メートルも雪が降るわけですから。春夏秋冬と四季の中で、それがちゃんと、木の年輪・木目に表れるわけですから、それを一つの板にしても、やはり社長が言うように、ひとつひとつ全部違うんですね。そいうものを、見ながら、使って、育つということが必要だと思いますね。
伊佐:ある大学の先生が、今度のオリンピックを機会に、木の文化を「KIAJI」、日本語の「木味」をローマ字で表記して、世界に広めたいという願いを持ってましたね。まったくそうでしょうね。いいチャンスですから、いろいろなことで、我々木の文化、日本人の心、デザインを表現したいですよね。それが地方の結びつきになると思いますね。
司会:あの、川場村では「ニュータウン川場」の宅地分譲にも乗り出していますけれど、そのへんも「木」ということを意識されていらっしゃるのでしょうか…?
外山:はい、区画は100坪がだいたい14区画なんですが、川場に家を建てていただく方はですね、まぁ出来れば、子供を育てる世代の人たちがですね、作っていただくと、いろいろな形で補助金を出す、要するに軽減措置をもってですね、で、また家にもですね、川場の木を使っていただければ、またそこに杉の柱を100本差し上げるとかですね、環境に配慮した色合いを使っていただくとか…いろいろな形で補助制度を作ってですね、家を作っていただければということで願っておるところです。
伊佐:また近いですよね、川場村は。インターから出て15分くらいですもんね。
司会:どうでしょう、伊佐社長でしたら、川場村にどんな家を建てられますか?
伊佐:やはりですね、山の稜線とか田園を見ながらすると、あまりデザインしなくても穏やかな形が出てきそうなので、どうでしょうね、人間があまり考えついたデザインではなくて、あそこの風景が生み出してくれると思いますね。
外山:そういう中で、川場村で育った杉であり、松であり、欅であり、桜であり、いろいろな形の木がありますので…。
伊佐:松もありました?それは、ジマツ?アカマツ?
外山:松もあります。アカマツですね。昔でいうと、アカマツも、梁材は弓なりに曲がった梁を川場のほうでは昔は使っていたんですね。そういうものをやはり使うような建物があればまたいいかなと思います。
伊佐:今、川場で現存している一番古い建物というのは、築年数でいうとどのくらい…?
外山:300年…。
伊佐:300年ですか?お住まいになっている、まだ?
外山:ええ、住んでおります。なかなか今、萱の家を継承するのが難しいのですが、そういう中でも、そういう家が1、2軒残っております。
伊佐:今度また見たいですね。
外山:けっこう夏は涼しく、冬は暖かいというところなんですね~。
司会:ありがとうございました。今週も伊佐社長と外山村長に熱く語っていただきました。ゲストは群馬県川場村・村長、外山京太郎さん、そして伊佐ホームズ・代表取締役社長、伊佐裕さんでした。おふたり、ありがとうございました。
外山・伊佐:ありがとうございました。
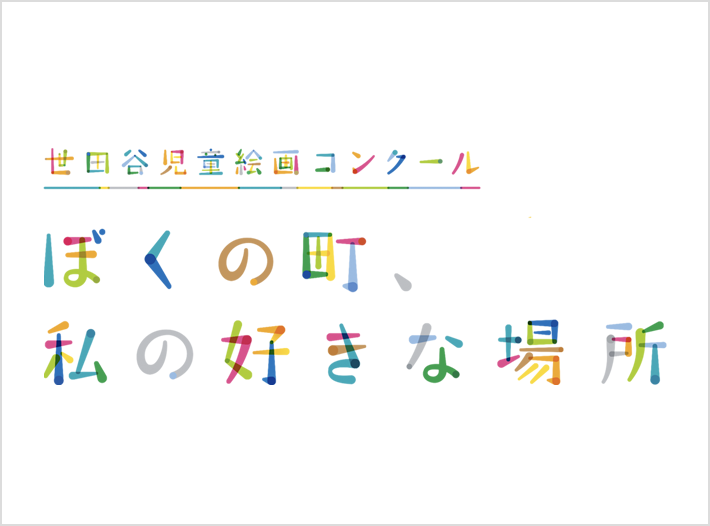
飯田永介さん
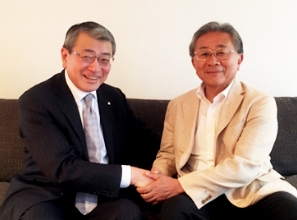
司会:わたし歳時記。この番組は伊佐ホームズのギャラリー櫟よりお送りしています。今月のゲストは株式会社岡永 代表取締役社長の飯田永介さんです。そして今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきます。よろしくお願い致します。
伊佐社長と飯田社長の出会いというのは、いつぐらいになるんですか?
伊佐:かれこれもう13年にはなると思いますね。あの、永介さん、社長のお父様、博さまとおっしゃるんですが、この方とのご縁が始まりでした。それで会長は去年の9月26日でしたか、他界されました。見事なご一生を送られましてね、私は人としても、経営者としても、誠に尊敬申し上げていました。わが父のようにですね、尊敬申し上げて、勝手ながら。そんな方のご長男で、こうやって亡くなられた後も交流を続けております。やはりお父様を介してですね、経営の思いといいますか、そして私も大変酒が好きなものですから、特に日本酒は。その中で折々杯を重ねてですね、今日まで来ていますね。
司会:日本酒について、いろいろ教えていただくようなこともおありなんでしょうか?
伊佐:そうですね、飲み方の始まりは温かいやつがいいよと。お腹を温めて冷酒に行ったほうがいいよと。今でも実践して…どこで私は燗酒から冷酒に切り替えるかが、分岐点が難しくてですね、結構燗酒のまま走ってしまっていましてね…(笑)
飯田:おぉぉ~。そうですか。
司会:覚えておいでですか?
飯田:いや~それはすばらしいですね。
伊佐:永介さんね、今までの3回のお話を聞きましてね、お父様が有名ブランドを辞めて、素晴らしい日本の地酒に目を持っていかれて、そして価値を共有する販売店を作って、事業をされてこられたというのはね、私も日本の木を使った良い建築をやろうということでやっております。その中で価値を共有するグループが連携してやっていったら、それだけ世の中に伝わるかなと思ってですね。常々そのやってこられた道が私にとって今の事業のお手本なんです。
飯田:ありがとうございます。
伊佐:今、林業が大変衰退していましてね、一年間に1億立米という成長をしているんですね。これエネルギーは0で成長しているんですよ。で、その木を日本で使っているのは2千万立米、8千万立米がまさに伸びっぱなしなんですね。自然界もやはり手入れが必要で、伐採していった方が循環するわけでありまして、もっと国産材を増やしたいと思って。そういうことでいくと、大変、日本の文化、地酒・日本酒を大事にしてこられたという経営思想はですね、私の本当に導きなんですね。去年のご他界は私にとっても大変痛烈な悲しみでありました。
司会:飯田社長、いかがですか?
飯田:いやー、あの、ありがとうございます。会長に対する伊佐社長の思いというのは、ずっとお聞きしいていましたけど、こういう形でいつもおっしゃっていただくのが何よりのありがたいことでございまして。私は私で伊佐社長のやっておられることを、とてもすごいなと思っておりましてね。経営者として尊敬申し上げていますし、親というか、兄貴ですかね。兄貴のような、そんな感じでいつもお慕い申し上げています。
伊佐:永介さんもラグビー好きですよね。私もラグビーやっていましたのでね、体型も似ていますね。まぁ、永介社長のが都会的ですが(笑)
飯田:いえいえ(笑)
伊佐:私、ラグビーも経営だなと思うんですよ。ひとりひとりがぎりぎりのプレイをしてチームに返していく。個人がどこまで吐出してそれがチームに返していくという…。単独で出すぎるとチームプレイにならないのでですね。本当、チームと個人の調和というのが経営だと思いますので、戦略も必要ですよね。
飯田:そうですね。
伊佐:まさに名門酒会さんには、その戦略があって、戦術があって、実践があるという…本当に私が目指したい会社の姿ですね。
伊佐:まさに名門酒会さんには、その戦略があって、戦術があって、実践があるという…本当に私が目指したい会社の姿ですね。
飯田:…ちょっと、過分なる言葉で(笑)
伊佐:いやいや。永介さんね、私は博多の生まれですよね。ちょうど博多も、なかなか商売を考える人間たちが多くて、食品業界では、ラーメンの一風堂の河原くん、それからふくやの明太子の川原さん、それから、今あごだしで有名な茅乃舎の河邉社長。大変身近にそういう仲間がいますのでね、やっぱり我が価値をどう伝えていくかということは同じなんですね。
司会:九州パワーを感じますね。飯田社長はずっとご出身から東京でいらっしゃいますか?
飯田:ずっと東京です。
司会:九州に負けられませんね。そのへんのところはどうですか、お酒を飲みながらでも、そういったパワーを感じられたりとか、そういう何か影響を受けられることっておありなんでしょうか?
飯田:そうですね。伊佐社長のさっきの木の話とかね、木材の話とか、山の話とかというのはとても重要な話で、何て言いますかね、地位経済をどう循環させていくかということか、それをどう都会とつなげていくか、というのは同じテーマなんですよね、僕ら。それが出来ない限り、もう日本はだめだと思いますから。地方創生ってね、今言っていますけど、言葉だけが踊るようでは話にならなくて。やっぱり現実的な地域経済をどう…、ローカル経済をどう循環させていくかという具体的なことがないと始まらないと思うんですよね。
伊佐:森がなくなったら水もないですからね。
飯田:その通りですね。
伊佐:まさに環境がダメになりますからね。
司会:お酒を飲みながら、お二人そんなことを実は考えていらっしゃったり…?
飯田:いやいや(笑)
伊佐:いや、ただ味に酔い、人の心に酔いで、そういうことは考えていません(笑)
司会:でも、お酒というのは「呑みニュケーション」という言葉もありますけれど、本当にいい効果を生み出してくれますよね。
伊佐:私もですね、自分の覚悟としてね、悪い酒は飲みたくないな、いい酒だけを飲みたいなって。自分の人生が悪い時もね、飲まずに自分で胸の中におさめたいな。酒を飲む以上はね、これをね、楽しくしなかったら申し訳ないなというのが、ある時からの信念としてありますね。いや、いつもいつもそうではないかもしれませんがね。やっぱり飲むと自分の可能性を広げますよね。あるいは人間のだらしなさも含めて。こんなに崇高なことを考えるかなっていうこともあるし、情が深くなるし、あるいはだらしないところもある。その幅を知った時にもう一回日常の中で少し是正されますね。飲まないとね、自分が見えてこない。飲むと自分の善し悪しがいっぱい見えてくる…それをまた自分で持ちながら生きていくというかな…。私は、本当に酒は凄いなと思いますね。
司会:飯田社長が応援していらっしゃるお酒の世界は凄いですね。
飯田:いやー、ありがとうございます。今の伊佐社長の話は深いですね。うーん。それに応えられるようなしっかりとしたお酒を提供しないといけませんね。
司会:お二人とも共通して考えていらっしゃるのは、やはり日本文化ということが大きいですね。
伊佐:結果としてそうでしょうね。私は仕事の話をしながら、人生の味わいを感じるのは、やっぱりお酒ですね。
飯田:そうですね、まぁ仕事がお酒なので、そこのところは途中でごっちゃになったりするんですけど(笑)
でも、本当にそのことはやはりありがたいなというふうに思います。そのことを生業とさせてもらっていることは、本当にありがたいことだなといつも思っています。
伊佐:それと私、酒の味でね、建築のこう、いろんな味わいを語るんです、社員に。濃いとか、薄いとか、薄くても奥が深いとか。薄いというのは、味が薄そうに感じますが、薄くて深いものがある。我々はやっぱりさっぱりしながら深いものを表現したいなって。濃いから建築がいいな、高価だな、じゃなくて。なんでしょうね~、食文化と美意識は近いところにあるなというのを感じますね。表現しやすいというかな、食を語ったほうが表現しやすい、その広さというのかな。
司会:わぁ、今日はとっても奥の深い話を聞かせていただきました。伊佐社長ありがとうございます。飯田社長には次週もまた語っていただくのですが、今日の話をふまえて、ますますいろんなお話聞けそうな気がしてきましたので、ぜひよろしくお願いします。
今月のゲストは株式会社岡永 代表取締役社長の飯田永介さん、そして、今週は伊佐ホームズ代表取締役社長・伊佐裕さんにもお話して頂きました。どうもありがとうございました。
飯田・伊佐:ありがとうございました。
清水健二さん

司会:わたし歳時記。この番組は伊佐ホームズのギャラリー櫟よりお送り致します。今月のゲストは合気道 天道流 天道館 管長 清水健二さんです。そして今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきます。よろしくお願い致します。あの、社長。天道流との出会いというか、清水管長との出会いというのは、いつ頃になるんですか?
伊佐:今から、どうでしょう。15、6年前でしょうか、先生? 私、会社の経営をして、約30年になりますが、ちょうどそのころ大変な自分の中の壁がありました。外的な壁があったこと、やはり内的に捉えるわけで、やはり自分を超える必要があったんですね。で、ちょうどその頃、福岡の両親も、特に父親が弱ってきましてね。片やそれを看病できないなんて、いくつかのいろんな自分の中の心の重しがありまして。で、私、ある時代から多少、座禅に縁があって、その頃ちょうど、山岡鉄舟の本だとか、江戸時代の白隠禅師の本だとか読んでおりました。それを頭で読んで、なかなか自分の中に入ってこない。で、ちょうどその頃、知った方から、天道館には、禅の研究家の鎌田茂雄先生が行かれているという…ああいう研究者がそこまでして体得されようとする道場というのはどういうものかなと思いましてね。私自体の苦悩といいますか、そういうことも、場所に行けば何か変わるかなということでお訪ねしたのが最初です。
司会:そうなんですね。門をたたかれてどんな感じを受けられましたか?
伊佐:いや、もう先生のお人柄がこんなふうなんで、私もすぐいい場所だなと思って。短かかったですが行かせていただきまして。その中で、やはりこう、形が美しいんですね、相手の力を生かすという…。我々は自分が、自分が…っていう思いが強いんですが、相手の力を利用して、その力を削ぐという…。だから我々は生きるために、自分がっていう思いがありますけれども、すべて来たものを受けながら返していくっていうことの大切さっていうかな、私は先生のお姿を見て、自分の人生の生き方を改めて確認したというのが、大変大きいと思っています。
司会:清水管長、どうですか? 今の伊佐社長のお話。
清水:いや、本当ありがたいお言葉ですけど、随分オーバーに言ってくださったと思っていますけど(笑)
伊佐:いや、とんでもない! 足りないくらいだと思っています。
司会:私も道場にお邪魔したんですが、空気がものすごく澄んでいるというか、落ち着く場所というような気がしました。
清水:あの、道場の内装は伊佐社長にやってもらったんです。
伊佐:ええ、うちの大工さんが喜んでお手伝いさせていただきました。
清水:手抜き、何もない! 安くやって下さったんですよ、ですからね、少しガタが来ても当然だと思っていましたが、なにひとつガタが来ない!
司会:すごくしっかりして、そして木の香りもするような…。
清水:いまだにそう感じますね。来た人がみんな「いい道場ですね。」って…その道場を見ただけで。作りがそのようにうまくやってもらっていますから。
伊佐:先生、あと皆さん、礼儀と掃除がすごいですよね。
司会:あー、きれいですよね。
伊佐:掃除の姿がいいなって思いますね。
清水:門弟勢がやってくれるんですよ。今ね、160、70人使っていて、電気関係の二代目の社長さんが見えているんですよね。どこからああいうエネルギーが出るんだろうと思います。53歳、一回今度お会いされたらいいと思うんですけど、紹介したいですけど。これ、変わりませんね。もう2年半来ていますけどね、それは私のほうが見習います。
司会:また、あの道場にあるあの“天道”という文字。揮毫された方が立花大亀老師。
清水:そうです、京都の大徳寺の。
司会:あの字も素晴らしいですが、あの故郷の話にちょっとなりますけれど、九州の天道からお取りになられた… 伊佐社長も九州のご出身ということでご縁がありますよね。
伊佐:管長と山を越えた反対側の博多の街でございまして。
清水:私は伊佐社長にお会いして、誠実な人だなあと思ったんですね。本当にね、いつ会っても気持ちがいい。今、ちょっと道場を遠ざかられていますけど、本当に感じのいい人ですからね。そして同じ九州でしょ。不思議なもんですね、故郷は福岡ですよね? なんか通じるものが…。
司会:縁というのはやっぱりあるんですね~。
清水:ええ。道場に時々顔を出してもらえるんですけど、なんかもう全然遠慮なく話せるし、本当にありがたい方が近くにいらっしゃるから嬉しいですよね。
司会:あ、伊佐社長、時々行かれるんですか?
伊佐:いや、今はなかなか仕事があって行けてませんけれども、でも管長への思いはいつも抱いていますね。管長ね、本当に損得抜きで、裸で武道で一生を終えようなんてという方の尊さといいますか、みんなこう損得というのは出ますよね。やはりそれ以上のものをして、人生生きたいなと思いますよね。あとで損得はついてくればいいと思うんですが。今の子供たちもみんな損得が先に立つと思うんですけど、やっぱ無心で行く人生を歩きたいなと思いますよね。
司会:それを体現されているのが清水管長…。
伊佐:そうですね、本当にこの道でしゃべっている…。
清水:やっぱり能力が…、いい成績でね、学校を出てましたらいいところに就職してたと思うんですけど、そういうこともありますね。それが、まあなんとかいい方向に進んだという…(笑)うちは天道って言いますでしょう? なんかおてんとうさまがこう助けてくれているのかなと…。
司会:あの、ちょっとだけ話戻っていいですか? 伊佐社長、道場をお作りになった、その時になにか込めた思いというようなものがおありだったのではないですか?
伊佐:そうですね、やっぱり木材はね、厚みがあって、命がありますよね。それがやっぱり大きいなと思いましたね。貼ったものと違いますよね、空間の空気が違ってきますよね。やっぱり僕は、高い安いじゃなくて、本物の中で生きるべきだと思います、人間というものは。どうしてもプリントもんでいきますとね、人間が軽くなってくると思いますね。安くてもいいから本物が大事だと思いますね。もう本当に、模造品というか、そういうものばかりですよね。やっぱり本物に出会うことが大事だと思いますね。
司会:本物の中で稽古される方というのは、じゃあ違いますでしょうね。
清水:違いますよね。昔はね、道場というのは立派だったんですよ。今はもう全然逆になりましたけど、ほとんど体育館借りてやってますから。
伊佐:先生、あの警視庁の剣道場なんて言うのは古風ですよね~。
清水:昔は町道場でもそういうのがありましたから。
伊佐:なにかぴんと、凛としたものがありますよね~。
清水:そういう威厳がありますよね。
司会:道場というのも、日本の美しさを一つ表すものだったのかもしれませんね。
伊佐:そうでしょうね、そこに行けば違うという…。
清水:やはり誇りがあったのでしょうね。
伊佐:やっぱり住宅でも玄関の大事さってあると思うんですよ。玄関というのは大変な場所に行く関所なんですよね、玄関という意味は。やっぱりあそこで心が変わるというか、そういうけじめが今はないですよね。
司会:ぜひその空間で、先生のお弟子さんたちにはますます磨いていただきたいですね。
清水:あの日本家屋は、磨いてきれいになる、柱なんかはね。ヨーロッパのは、いくらきれいでも塗っているのが多いですよね、塗る文化というか…。日本は磨く文化のような気がします。
司会:下から出てくる美しさというか…人間と一緒ですね。
清水:使えば使うほど重厚味が出てきてね…、さわやかというか、癒される感じですよね。
伊佐:極めていくというかな、極めていくことですよね。
清水:今、観音温泉今度一度お連れしたいんですけど、観音温泉ってあるんですよ。で、そこは30万坪くらい持っているんですよね。で、そこで合宿やるんです、外国から来た人を含めたときに。でそこがね、凄いんですよ、木が。で、今いい温泉が出ますから。で、そこでね、よくこちらが頼むと板をタダで分けてくれるんですよ。だから、ヒノキの板が、うち、こうすみっこに…、何か会があるときに板を台にして座るんですけど、そういうのは、やっぱり私が合気道をやってきて、そこの先代がやっぱり合気道をやってる人だったんです、昔。で、知り合っていまだにずーっと続いているのは、そういう…なんていいますかね、昔の、武道を、もう白紙でやってたときのことが、昔の私の姿を見てよく頑張っているよなと思うような、感じが今、生きてきているような気がしますね。温泉も十分いいお湯ですから、楽しめるんですよね。
司会:伊豆の温泉で世界セミナーを開かれているというお話は、次週また詳しくお聞きしたいと思います。今日は楽しいお話をありがとうございました。合気道 天道流 天道館 管長 清水健二さん、そして、伊佐ホームズ代表取締役社長・伊佐裕さんに伺いました。お二人ありがとうございました。
清水・伊佐:ありがとうございました。
池上幸保さん
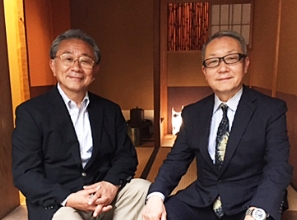
司会:わたし歳時記。この番組は伊佐ホームズのギャラリー櫟よりお送りします。今月のゲストは日蓮宗大本山池上本門寺檀家総代の池上幸保さんです。そして今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきます。よろしくお願い致します。
さて、今月第1週目で池上本門寺は、日蓮宗の宗祖である日蓮上人が亡くなられた場所ということをお聞きしました。そしてまさに日蓮上人が亡くなられた、池上宗仲公の館跡地としてあるのが、池上本門寺三内寺院のひとつである本山池上大坊本行寺。ここの客殿の建て替えが去年行われて、これを担当したのが伊佐ホームズさんということで…、その関わりがお二人のかかわりということでよろしいんでしょうか?
伊佐:いや、その前に大学の同窓ということもあったり、もっともっとその前の由縁がありまして…、私からちょっとその辺をお話ししましょう。
大学時代、私も同期で慶応大学を出たわけですがね、池上君のことは全く知りませんでした。卒業して15年ぐらい経って、同窓会で会いまして。実はその前に奥様のことを聞いておったんです。実は奥様のお父さんが、私の福岡の母校・修猷館高校の大先輩なんですよ。今97歳でご健在なんですが、この方のお宅にお邪魔していた時に「伊佐君、うちの娘が池上に行っとるとよ」って言われてましてね、その頃結びつかなかったんですよ。で、その後、卒業後、十何年経って会った時に、「あ、君が!」っていうことで。それからなんです。これだけのご縁が…だからもともと種があったのかなって、お会いできる。
司会:そうしましたら、その建て替えには、そういううご縁があって進んだということになるんですか?
池上:いや、あのね、もともとあった客殿が建築後40年位経ちましてね、鉄筋コンクリートで出来ていたんですが、経年劣化が激しくなって、建て替えなくてはいけないと。だいぶ手当をしながらやったんですが、もういよいよ建て替えなくてはいけないとなった時に、ご住職始め建設員の中でいろいろと協議をしましてね、やはり今度作るときには、寺院らしい、和風の建物にしたいねということになりまして。それで、数社お声がけをして、言ってみればコンペということになったわけですが、その中で私は伊佐さんのことを前から存じ上げてましたから、これはもう是非伊佐さんにも、プランの段階から入っていただこうということで、コンペに参加していただきまして。その出来上がってきたプランをみんなで検討した結果ですね、満場一致でこれはもう伊佐さんのところにお任せするのがベストであるということになったわけです。
司会:皆さん満場一致というのは、どこが一番…?
池上:いわゆる伊佐ホームズが従来からこだわって建てていらっしゃる木造建築の持っている良さっていうんですかね、そういったものが寺院建築に一番ふさわしいと、いうことですよね。それを現代風に、現代の技術を持ってですね、木造の良さを生かして、使いやすさ、あるいは、いろいろな意味で、日本建築のもっている良さが十分に表現されていたと、こういうことだと思いますね。
司会:伊佐社長は、そのお話が来たときはどんなふうに感じられたんですか?
伊佐:いやあ、本当に私にとっては驚きでした。また池上君が同窓会でお付き合いする中でね、私の仕事を見ててくれたんだなぁって思うことが嬉しかった。それとうちのような会社でこんな大きなね、お仕事のチャンスを頂いたと。で、戦後のある時期から、非常に社寺建築も鉄筋コンクリートになったんですね。それが、この30年40年経ってきますとね、大変、経年劣化っていう…今池上君言いましたがね、木造でしたらね、経年美化でね、年取ったことが美しいんですよ。残念ながら、新建材とか新しいものは、非常に醜くなるというのかな…。その辺をご住職、あるいは檀家総代の皆さんがよく認識されて。前提条件が木造ということと、伝統美ということをおっしゃってましたので、本当にこれは頑張って仕事をやらせていただきたいなと。またその頃、私の家内が重い病気に倒れておりましたのでね、そのためにもこれをやり抜きたいなという、私の個人的な思いも強かったです。その中で晴れて、皆さんからありがたいお言葉を頂いて、仕事が2年半かかってやって、去年の11月早々に竣工になったわけですが、私はこのような歴史的な木造建築、あるいは大田区、都内有数な場所でこういう仕事をやれたってことは、本当に人生のこれ以上の栄誉はないです。ありがとうございました。
司会:こんなふうなお話を聞くと、逆にまた、池上さんも嬉しく思われるんじゃないかなと思うんですが…
池上:そうですね。私はもう、伊佐さんにお願いするって決まった時に、もう絶対信頼してましたから。誰からもいいものが出来たねって言われるだろうというふうに確信しておりました。
伊佐:私自体、この会社を、信じる美しさのために作って、ずっと続けてまいったので、こんなような、私が思いの果たせた仕事はなかったですね〜。
木造建築はですね、やはり柱の大きさがある程度ありますので、無理が出来ないんですよ。それに従って設計していくので、そこに自我が出ずに…。あの、鉄筋コンクリートというのは非常に無理がきく、それは自我が出るんですね。私は、本当の個性というのは、自我を押さえながら、美しいものが湧き出るものだろうと思っているんです。木造はどうしても制約があるからこそ美しくなると私は思っているんですよ。今度の新国立競技場も含めて、木造の良さが非常に認識されているときだと思いますので、それに先駆けて、本行寺さんではこのような仕事に取り組まれて、そんなチャンスを頂いて、本当に私は嬉しゅうございます。
司会:また、居心地のよい空間ということで、以前この「わたし歳時記」のゲストに出ていただきました、日本画家の中村宗弘先生の絵も飾っている…そういう意味でもとてもいい空間になっているなと…私、写真でしか拝見していないのですが、そんなふうに思っておりましたが…。
池上:中村画伯もご縁がございましてね、寺院に日本画を残したいという強いご希望があって、そんなときにたまたま本行寺の栗客殿の建て替えというタイミングがちょうど合ったんです。本当にご縁だと思うのですね。で、中村画伯も全身全霊を傾けて、素晴らしい絵を書いていただいた。それが正面玄関入ってすぐのところに今も飾られているのですけれど、参詣していらっしゃった方の目を大いに楽しませてくれてるなと思っています。
司会:本当にいろんなご縁が結びついているということですよね。
伊佐:私は絵を見ましてね、絵が入って初めて完成したなと、建物が。本当にあれをもって完成だと。たぶん絵っていうのはそういうもんでしょうね。一体化しましたね。
私、人間というのは自分の道を生きながら、不思議な人と出会って、その志を成し遂げて人生を進んでいくのかなと思いまして。さまざまな方と出会う、そこで教えられて、道が開けること…いつも痛感しておりまして。池上君には本当にそれを深く感じる…。
池上:いや、なんかくすぐったいです。
伊佐:いやいや、本当に。飲むときはこんなんじゃないんですけどね(笑)
司会:そのお酒の場でもやはりいろんな刺激を受けたりとかされるんですか? どんなところが一番惹かれるところ…?
池上:やっぱりね、伊佐さんは仕事に打ち込んでいる姿がいいですよね。脱サラして徒手空拳で会社を興されて、奥様のご協力もあって打ち込んだ…結果、今の彼があるんですけれどね、それに至るまでは、本当に口に言えないような大きな苦労されたと思うんですけれど、そういったことは決して口に出しませんしね、俺が俺が…っていうところもないですし、きわめて謙虚に、だけれども熱いものを持ちながら仕事をしているという、非常に魅力的だなと思いますね。
伊佐:僕からみますとね、池上君は慶応の同級生の世話役であって、いつも私心なく物事を引っ張っておさめて…必ずそれをやってしまうんですね。本当に信頼の厚い、大変尊敬している同級生です。ましてや、私は九州から17時間の夜行列車で東京に着いた人間、で、大学はほとんど行ってないんでですね、慶応の卒業といっても、あまり慶応の意識なかったんですけど、今大いに人生で、慶応の同窓、先輩たちと会って、大いに慶応の卒業生だと今実感しております。
司会:なるほど、なんだか慶應義塾大学の魅力も今ここに感じられる気が致しますけれど…。お酒の場ではこんなまじめな話ではなくて、もっといろんな話をなさるんですよね?
池上:もちろん〜。同年代が集まれば、馬鹿話、若い者の悪口を言いですね、盛り上がるというのは、もうどこでも同じです。
司会:そしてまた次の活力に結びついていくということなんですね〜。今日ももしかしたらこの後飲まれますか?
池上:さぁ、どうしましょう。
伊佐:はい(笑)
司会:なんとなく行きそうな…、ちょっとお時間は早いのですが…(笑) ありがとうございました。今月のゲスト、日蓮宗大本山池上本門寺檀家総代の池上幸保さん、そして今日は、伊佐ホームズ代表取締役社長・伊佐裕さんにも加わっていただきました。ありがとうございました。
池上・伊佐:ありがとうございました。
梅崎浩さん

司会:わたし歳時記。今月のゲストは高齢者視覚障害者クラブつくし会 会長の梅崎浩さんです。そして今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきます。よろしくお願い致します。お二人は今日初めてお会いになるわけですが、それぞれに楽しみにされていらしたというふうに聞いておりますが、どんなところ楽しみにしていらっしゃいましたか?
伊佐:私はね、今日梅崎さんが視覚障害がおありになるいうことで、今までそういう方のお宅を作ったことがないものですから、そういう住宅についてもそうですし、お仕事についてもお聞きしたいですし、両方のいろんなお話をお聞きしたいと思います。
司会:今日もこの番組、伊佐ホームズのギャラリー櫟からお送りしているんですが、どうでしょうか、梅崎さん、入った時に何かこう感じるものとかおありでしたか?
梅崎:あの、一歩、あれ、手すりもそうですけどもあの階段も木じゃないですか?ね?なんか…すぐ感じましたね。うちは玄関から入ってもちろんコンクリで、中に入ってしまえば、靴を脱いでしまえば、板張りですけども、ああゆう外から入るのに手すりから何から全部木っていうのは、あれ?と思って…感じました。
伊佐:安心感か何かが強いですか?
梅崎:そうですね、そうですね。手すりもああゆう角ばった手すりでね、持ちやすいです、僕なんかにすると。つるつるしないで済むから、すべらないためには、あれのほうがいいですね。
伊佐:そうかもしれないですね。今日は、本当に目がご不自由ということで、我々うかがい知れないところがありましてね、たぶん音声とか、空間の把握力がお強いんだろうなというふうに勝手に思うんですが、いかがでしょうか? 空間に対しての感覚というのはどんなふうにつかんでおられますか?
梅崎:音声は確かに敏感になりました。それで、空間というのも音声で、例えば外に出てても、空間であっても空気を読んで、風から何から…そういう感じ方は敏感になりましたね。だからそれだけで、ここひょっとしたら交差点かな?とか、風の吹き方でね、そういうふうなあれはありますね。
伊佐:例えば、人間でも声の音質によって、人物がどうかっていう風にお考えになるでしょうし。
梅崎:あ、なります!
伊佐:そうでしょうねぇ。私はどうかな?という…(笑)
梅崎:いや、あの、ひとこと、二言話しますとね、なんとなく感じますね。
伊佐:私ね、1回目、2回目拝聴しましてね、大変なご苦労の中で常にいい形で運命を開いてこられている…高校もそうですし、大学もそうですし、また円谷プロに入られたのもそうですし。こうゆう障害になられても道を開いておられることに大変感銘を受けておりまして、まして今日我々設計上の問題でこうゆうケースがなかったものですから、余計我々は、今後の為にもですね、空間論、住宅論を我々も勉強してですね、さっき丸よりは角のほうが安定するとおっしゃったことも大事なことかなと思いますね。
司会:梅崎さん、住まいに対するこだわりっておありですか?
梅崎:今住んでいるところというのが建売で、その時は見える状態で。30年前ですけどね。でもそこから手直しをしたところ、どうゆうあれで、手直しをしたかというと、まず、だんだん僕が高齢者になってくるにつれて、すべりやすいっていうか、お風呂場なんかは全然手すりがついていなかったのを、手すりをまずつけ始めましたね。それでお風呂を改装して、浴槽にもすべらないようにしまして、すべらないようにということは気を遣いました。それで見えなくなってからというのは、今度は段差。うちの中で敷居とかね、跨ぐんじゃなくて、なければっていうことでなくして。たまたまその時床暖に階下だけ変えたんですよ。床暖に変える時に、下の敷居を全部外しましてね、ふすまとかそういうのも、ふすまがあっても、スライドしてても、段差がないようにということをしました。で、2階はそのまま、段差があるまんまで、日本間一つと子供部屋2つなんかはそのまんまなんですけれども、2階の畳の部屋だけ気をつけていればこけたり、つまずいたりすることがないもんですからね、その段差っていうのは非常に気を遣っていましたね。階段もやっと手すりをつけて…万が一のためにもつけました、やっと。
司会:段差がなくなってかなり快適になられましたか?
梅崎:そうですね、安心してます。
伊佐:中途半端な段差なんていうのは、一番悪いでしょうね、はっきりとした段差であれば、はっきりとした差異があるんで。中途半端というのは非常に見逃しやすい危なさがありますでしょうね。
梅崎:そうですね、本当に、年取った人が歩いていても、点字ブロックのぽこっとしたぶつぶつ、あれにでさえひっかかっちゃうんですよ。ですので、あの高さでも躓く人は躓いちゃう。ですので、やっぱり出来るだけ平らな方がいいですね。
伊佐:あと材料的なことで、足触りとかで安心だなって思われることって…、今日は上ってこられるときに、木材だってことを感じられたお話されていましたけど…。
梅崎:ええ。やっぱり、コンクリよりは…あの今みんな、うちもそうですけど、床暖にしたら木が全部失われてますよね、上にちゃんとつるつるのが貼ってありますんでね。で、それよりはやっぱり木のほうがいいですね~。
伊佐:今、床暖も木材でも十分大丈夫ですよ。
梅崎:あぁ、そうですか!へ~。
伊佐:お手伝い致しますよ(笑) どうしょうね、コンクリートよりやっぱり木のほうが安心感があるというのは、大事な問題かもしれませんね。
梅崎:感じ方全然違いますよね。長くそこに生活したりとか、しょっちゅう出入りするならなおさらそうですね。
伊佐:あとは家の中で、例えば、南の光が明るいとか、その辺の気配とかは梅崎さんの場合感じられることはありますか?
梅崎:そのへん、僕は光は全然見えないので、自分の頭、この頭が薄いので…
伊佐:そこに座られたら、もう光があるんだっていう感覚が戻ってくる…?
梅崎:いや、やっぱり温かさがないと…太陽光があると…朝…
伊佐:定位置にいらっしゃる…いい場所にいらっしゃる…じゃあ家庭の中での定位置が大事なんですね。テーブルの場所もそうだし。
梅崎:そうそう、動かないですよ(笑)
伊佐:でも笑顔がすばらしいし、お元気ですよね~。
梅崎:いやいや、まだ70ですから(笑)
伊佐:でもちょっと私、はじめ今日は緊張して参ったんですよ。こういう対談初めてですから。なんの壁もなく私もこうやってお付き合いをさせていただいている感じがします。
司会:実は梅崎さん、本当にアクティブでいらっしゃるんです。今お家の定位置っておっしゃいましたけど、おそらくそこにずっと長くいることは…ないですよね?
梅崎:まぁね、たぶんね(笑)
司会:意識して外にも出ていらっしゃるというふうにお話されていて、そういう意味では、お家そのものもそうなんですが、街についてもいろいろ感じるところがあるんじゃないかなと思うんですよね。
梅崎:たまたま、うち、路地になっていましてね、非常に子供の声がするんです。安心です。本当に安心で、うるさいというか、大変な通りから、70、80メートル入っているかな…で、全然その音がしないんですよ、通りの音が。で、子供が周りに幼稚園の子供とか小学校の子を入れると4人くらいいるんですけどね、やっぱり元気だからその声を聴くとね、本当に安心感。いいとこに住んでるなぁと思って。ちょっと駅には遠いけども(笑)
伊佐:だから今は老人ホームと小学校が近いほうがいいとかね、よくそういうことで計画されますよね。
梅崎:面倒見てもらえたりね、老人のことを理解したりとかね、老人の人も子供の声とかね、やっぱりお孫さんと離れ離れになったりしてる老人の人たち多いんで、そういうの安心感あるんじゃないですかね。
司会:じゃあ次週はその辺のところを少し膨らませて聞かせていただいてもいいですか?今月のゲスト、梅崎浩さんにお話を聞かせていただきました。そして今日は、伊佐裕社長にもご一緒していただきました。ありがとうございました。
梅崎・伊佐:ありがとうございました。
山谷えり子さん

司会:わたし歳時記。今月のゲストは、参議院議員の山谷えり子さんです。そして今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にもご一緒していただきます。よろしくお願いします。
今日は子供の日なんですけれども、お二人って子供の頃はどんなお子さん…、何か子供の日の思い出なんておありですか?
山谷:いや、もうやんちゃでねー。私福井で育ってましたけど、福井はまだ野っぱらが多くて、占領時代の生まれですけど、当時まだまだそのころ野っぱらが多くて、あっちゃこっちゃに秘密基地を作って、トムソーヤとハックルベリーフィンごっこばっかり(笑)
司会:楽しそう!社長は…?
伊佐:私は魚とりですね。橋を渡ってましてね、上から見たね、川にこう…いろんな小魚が泳いでるのを見てね、胸がときめきましたね。そうゆう自然の中でだんだん社会への勉強になったり…。
山谷:ねー、友達とじゃれまくって…自分というよりもなんか団子のように遊んでいたね、皆ねー。
司会:その頃はまさかお二人出会われるということは思ってもいなかったと思いますが、さてお二人はいつごろ、どんな形で出会われて…?
伊佐:20年前でしょうかね?
山谷:私、生活情報誌のサンケイリビングの編集長をやっていて、ありとあらゆる生活の情報誌で作っていたんですが、なんかそれで、たぶん住まい方とかで社長と出会って、お家まで呼んでいただいて…。素晴らしく落ち着いた、本当に品のある、こう日本の根っこから栄養を頂いている…みたいな感じの家で、奥様がお優しくて、卵焼きがとてつもなく美味しくて、色々ごちそう頂いて…。で、ファミリーがあったかくて、やっぱり、器とこのファミリーって本当に一つなんだなって。で、伊佐社長が、以前は大手の商社マンでいらして、住宅部門で、そのままこう大きな会社でやっていく方がもしかしたら楽だったのかもしれないのに、やっぱり自分自身の美意識と哲学と人を幸せにしたいっていうコンセプトで、やっぱり自分の思う住宅を皆さんにねーっていう思いで私の道だって決めて独立されて、会社立ち上げられて…。
伊佐:いやー、卵焼きのことは私忘れていました(笑)我が家はですね、大事な方は我が家でおもてなしをするっていうのが鉄則でして。浜美枝さんとか、のちにはペルーのフジモリ大統領も我が家で家庭料理でおもてなししましたね。
山谷:だからね、私も伊佐社長も世田谷住まいですけども、歩いているとウッと思う家があって、それは伊佐社長が建てられたね(家でね)、光とか風が通るとか、間があって、自然に邪魔しなくて溶け込んで、それでいて凄い存在感があるみたいな…。
伊佐:いやーありがたいお話を!ただお客様からはそんなふうなことは時々お聞きしますね。それとなく伊佐ホームズじゃないかなというふうに言われるのがとっても我々嬉しいんです、実は。
司会:それだけ街に、風景に溶け込んでいるということなんですかねー。
山谷:やっぱり日本文化研究会の理事もしてらっしゃるくらいだから、日本人としての自然体、それから長く皆が生活を積み重ねてきて、日本の国柄とか、日本人の感受性とかあるいは自然との交流とかね、そういうものを形にするとこうなるのかみたいなね。
司会:お二人とも日本というもの、文化を大事にしていらっしゃる、そのへんが共通するところでしょうか?
山谷:もう感謝でいっぱいなんですよね。やっぱり世界でいちばん長い歴史と統一国家としての文化・伝統を持つ国というのが、本当に大きな宝の中に私たちたまたま生まれ育っているなということと、日本人の思想って、おむすびじゃないけど、結びの思想でね、結ばれること繋がれることによって、素晴らしいものが生まれ、生み出されてゆくっていう、そうした考え方、感じ方というのは素晴らしいですね。今ほら、テロリズムとか対立とか、あるいはポピュリズムとか、なにかざわざわしていく世界の中でですね、本来の人間と人間のありかた、あるいは人間と自然の在り方、あるいは今生きている人間とご先祖様たちが積み重ねて下さったことやら、未来のひとたちがこれから作ってくれるだろうこととか、みんなつながっているっていう感覚がね、ありがたいし、それによって落ち着けるというか。
今度伊勢志摩サミットがありますけれども、私伊勢ご遷宮・平成25年度参列させていただいたんですが、41代持統天皇のころから1300年間、20年ごとに新しいお社を作って、祈りを込めて手抜きをせずに、その技術っていうのは神様に捧げる、そして捧げることによって一人一人も幸せになれるっていう、モノづくりの日本人、 あるいは謙虚な日本人、それから誰が見ていなくても真心を込める日本人の姿が象徴されているなと思いまして。で、もうさっと、奈良時代までさかのぼれる日本人って凄いなと、奈良平安鎌倉、なんかいろいろな時代のようだけど、でも脈々とそうしたものを大事にする心っていうのがずーっと時代を超えて伝わっているわけですから。
司会:本当にお二人共通するところがたくさん、そういう思いがおありだと思うんですが。
伊佐:年も!(笑)
山谷:そうそう3カ月違いの(笑)まぁ団塊の世代の一番右の方というか…。だからそのみんな希望に燃えて大人たち頑張っていたし、そんな中で子供なりにお役に立ちたいと思って素直に言い切れた時代かなーって。
伊佐:今日は子供の日ですから、山谷さんにとってご両親の姿こそ教育のすべてだったろうと思いますが…
山谷:それは本当に家庭教育というかねー、やっぱり愛情を注いでくれましたし、それから月に一回、うち普通のサラリーマンだったんですが、父が新聞記者で、月に一回食事、外食ねー、今なら外食当たり前かもしれないけど、当時めずらしくて。で、ハンバーグかなんか食べているときに「えりちゃん将来に何になりたい」って聞かれたんで、父と同じ職業を答えると喜ぶかなって思って「新聞記者」って答えたら、「そのナイフとフォークの使い方だったら、将来アメリカに行って、大統領に取材した後、ホワイトハウスでディナーを食べても、呼ばれても大丈夫だよ」って言って、もうねちっちゃいころにね、で「あ、いろんな可能性があるんだー」って。
で、福井から東京に引っ越してきた時に水泳部に入ったんですが、なかなか勝てなくてね。そしたら「人がやっていない種目ってなあに?」って。当時は女の子でバタフライの200メートルとか個人メドレーやる人いなかったんですよ。で、「それをやっているのはあんまりいないよ」って「じゃあそれやれよ」ってやってみたら世田谷で2位!(笑)素晴らしい銀メダルもらっちゃって。そういうふうにね、なんかこうちょっとした人生を渡るコツとか、それから世の中面白いんだよっていうふうに見せてくれる…それはなんか良かったなあって。
伊佐:私はですね、父親が事業をしていましたので家庭にいろんな人が出入りするんですね。私幼くして社会と触れてきたんですね。学校を出たから社会に行くんじゃなくて、非常に家庭の中に社会があって、あるいは酒を飲む姿があって、あんな男にはなりたくないなと思ったり。あるいは、母は70なんぼまで寝込んだ姿を見たことが無かった、何一つ愚痴がなかった。すべては物事は成り立つ、何があっても、私のことを「裕ちゃん大丈夫」って。かたやですね、親父は厳しかったですがね、いろんな私の話を聞いてくれました。私は小学校の時に、一日で180匹の昆虫、カブトとクワガタを取ったんですよ。
山谷:また自然も豊かで…凄い!でも集中力がありますね。エネルギーっていうか…。
伊佐:そういうこう成果はやっぱり親から認められて…このへんからですね、思いますね。
山谷:うちの父も麻雀が好きで、当時新聞記者たち麻雀よくして、いつも10人近くうちにどさどさっと来てはお酒も飲むから、もう給料前にお金がなくなっちゃうんですよ。それで母が質屋に着物を預けに行ったりとか、それでもうちの母も面白がって全然愚痴も言いませんでしたけど。で、麻雀は4人だから、のこった、あぶれた男性記者たちは私相手に、かっぽれとか都都逸教えたり、お座敷芸教えてもらって、楽しかった。
伊佐:社会への抵抗力はそのころから免疫がね…。
山谷:そうね、だから天下国家をなんか子守歌のように聞いて…。
司会:お二人とも素晴らしい家庭・環境の中で過ごされたんですね。いかがですか?こんなふうにしていてお二人とも同学年、3カ月違いということですが、とっても活力に満ちているというか…どこにその秘訣がおふたりおありですか?
山谷:運動は好きなんです。だから今でも水泳やっていますし、学生時代はずいぶん山登りもしましたし、今は合気道。週に一回通って今四段ですけれども、体を動かすことが好きで、うん。
伊佐:私も月に二回山登りしているんです。
山谷:あ、そうなんだ、やっぱり自然から力を頂く…。
司会:今日はお二人のお話の中からいろんなところが見えてきたんですけれども、次回もまたいろんなお話をお聞きしたいと思います。お二人ともありがとうございました。
山谷・伊佐:ありがとうございました。
橘益夫さん
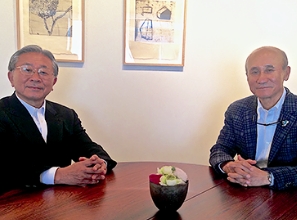
司会:わたし歳時記。今月のゲストは、橘益夫さん。そして今日は、伊佐ホームズの伊佐裕社長にも加わっていただきます。お二人、よろしくお願いします。
橘・伊佐:よろしくお願いします。
司会:といいますのは、この番組、伊佐ホームズのギャラリーで収録させていただいておりまして、本当に木の香りのするとても心地よい空間なんですが、お二人の共通点としては、慶應義塾大学の法学部のご出身、ただ学年はちょっと違いますよね? 学生時代には何か接点はおありだったのでしょうか?
伊佐:全くないですね。
橘:私が先輩でございます。
司会:ではいつ頃出会われて…?
伊佐:それは今から23年前、当社が橘邸という大建築をやらせていただいたときに遡りますね。それで、似ているようで、橘さんはまさに都会の典型的なスマートな方でいらっしゃった…私は九州から出てきた、田舎をしっかり背負って東京にきた人間でありまして、似ているようでまったく似ていないところがございました。
司会:似ているところはどんなところですかね?
橘:うーん、僕は正直言って、伊佐さんに似るってことはあり得ないなと思っております。伊佐さんって、さっき田舎からっておっしゃいましたけど、というより、自分の信念を持って、特に建築ってまさに大黒柱じゃないけど、そういうものがあって成り立つものじゃないですか。伊佐さんってまさに自分が大黒柱で家を作っていくっていうお気持ちを持って、新しい会社を建てられたのを知っていましたし、で、その木で作る家ということに僕共感して、家を建てさせていただいたんだけど、伊佐さんが持っている誠実さ、それからある意味では物事の本質を一生懸命見極めてモノを作っていく…。これ、僕は広告会社に、電通にいて、正直言ってちょっと表面的なとらえ方でずっとやってきたことと、モノづくりの基本が違うなと思っています。そういう意味では、伊佐社長の生き方・考え方とは、私は同じ学校出身なんですけど、違うなと実感しています。
伊佐:いやいや、そこは私ですね、橘さんのこと、こう思うんですよ。本当にソフトでいらっしゃるけれども、自分の道をきちんと通してこられた方だ…私なんて思いがあるとそこだけが出っぱって、非常に頑なになるんですけど、橘さんはすべてを受け入れられながら、前に来られた、あとは非常に人がお好きだと、そこは私と大変似ておられると思うんですけど、私だったらこうまっすぐ行ってしまうところ、橘さんは受けながら広げてこられたという…私は、こうやって長年のお付き合いになって学ぶところが多々あって、今またすばらしいことに一緒に取り組んでいるんですよ。
橘:今お話あったように、伊佐さんね、新しいことに挑戦されるのが好きだし、とても好奇心旺盛、そこは僕本当に一緒なんですね。だからついついね、伊佐さんから「こんなことやろうよ」って言われると、「じゃあちょっとやってみましょうか」っていうふうにご一緒するケースが多いんです。これはね、伊佐さんのいい意味での人を使ってくださる、得意技ですね。伊佐さんって人が好きな方じゃないですか。伊佐さんは特にですね、一度会ったら友達、二度会ったら親友、三度会ったら親戚同然ですよ。この付き合い方って類稀な方ですね。それはそれだけ、相手が心を許すってことをさせる方ですね。
伊佐:私福岡で生まれて、大変人の出入りが多かったんですね、私の家に。小さいころから挨拶することが多くて。で、人の前で歌うと…親父たちの宴会に入りますと「おい、裕、歌えよ」ということでみんなから拍手が出るんですよ。そういう家庭で育ったので、そういう点ではよかったなと思いますね。それだから、人への挨拶もね、川の向こうに友達が歩いていても、「おーい」っていう…川の向こうにいてもこう(挨拶をする)、だから近くにいても川の向こうまで語るような思いってあるんですね。
橘:それ本当に人がお好きなんです。人との結びつきをともかく大切にしたいって気持ちが強いよね。いやー、こんなね、純粋っていうかね、いい意味での、僕はそういう方にね…正直言って周りにはなかなかいらっしゃらないかな。
伊佐:でも家づくりって、お嬢さんたちが小さかったですよね、まだ幼稚園でしたかね、あの時は。それがもう皆さん一家を構えられて、お子さんがいらっしゃるという…。家づくりってやはり長いスパンですから楽しいですね。これほど長いスパンの商品をやっていくというのは…、商品という言葉はおかしいかもしれませんが、素晴らしいなと思いますね。
橘:そうですね、素晴らしいお仕事。伊佐さんは自分でそれをともかく立ち上げておやりになるって知って、瀬田にちょうどね、ショールームというか本社があって、よく犬の散歩で歩いてて、その家を見てて、「あーこんな家に住みたいな、こんな家に住めたらいいな」と思ってて、その当時正直伊佐ホームズって名前はそこに行ってしか知らなかったんです。で、門を叩いて伊佐さんにお会いして…
司会:また人柄にほれ込んで…?
橘:そうです。
伊佐:もうあのモデルハウスも28年過ぎましたね。今でも変わらないんですねー、建物が。いや今のほうがいいかな。経年美化ですよね、天然素材は。工業製品は出来たときは最高で、非常に放物線を描きますけど、自然素材はソフトランニングしていくし、それがますますよくなっていく。だから日本の文化の「わびさび」っていうのは、木はさびていくんですよね。ある面じゃ白っぽくなっていくようなカビがあるんですね。それでこう白くなっていく、それが美なんですよね。
橘:人間も経年美化したいですね。経年美化っていう言葉を我々のテーマにして生きていきたいな。
伊佐:私はずっと絵を書いていまして、絵が私を支えているなと思うんですね。やっぱり絵はつり合いですから、あるいは色彩のバランスとか質感とか。私らの家が、非常に質感のある、漆喰だとか漆だとか、素材感の非常にある家でしたので、そういう触る感覚というのが大事かなと思っていますね。
橘:そうですね。触感とか、におい、空気…。
伊佐:食物でもそうなってきてますよね、ジュースでも食感があるようなものずいぶん出していますよね。
司会:五感で感じるすべてを大事にというような感じですか…。
伊佐:五感は命ですよね。
司会:それは橘さんも共感なさって…?
橘:そうですね。よくシックスセンスっていいますよね。その五感だけじゃなくて、そこからその次にひらめくものというのは、そういうものが身についたり、その空気にいるから得られるものだと思いますね。
伊佐:そうでしょうね、触発されて。
司会:そして、先週のお話にもありましたが、「夢は見るだけじゃなくて、叶えるもの。見れば叶う」というようなお話もありました。そこに向かってまだまだお二人すすんでいくというところでしょうか。
伊佐:そうですね、楽しみですね。ますます我々青春です。本当に老いたらますます青春なんです。
橘:いいねー。経年美化という言葉をいただいちゃった〜。
伊佐:変わらない青春がありますでしょ?
橘:もちろんです。新しい青春です。青春の1ページって感じじゃないです。何ページ目かもしれませんけど(笑)。
伊佐:いやいや、新しい、新しい。今、ページがめくられますよ。
司会:私も負けられないなと思いました。
橘:当たり前ですよ。
司会:橘さんには来週もお話を聞かせていただきます。橘さん、伊佐社長、ありがとうございました。
橘・伊佐:ありがとうございました。
柴田美保子さん
橋本善八さん
中村宗弘さん
池井優さん
最高顧問
桑島俊彦さん
大須賀賴彦さん
日本を美しくする会相談役
鍵山秀三郎さん
政治経済評論家
徳川家広さん
望月照彦さん
江川家42代当主
江川洋さん
神野三鈴さん
坂口寛敏さん
代表理事
吉松正秀さん
松本純夫さん
徳澤貴美子さん
イイノナホさん
せたがや文化財団名誉顧問
熊本哲之さん
小川糸さん
武見敬三さん
後藤圭子さん
川口淳二さん