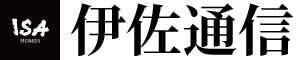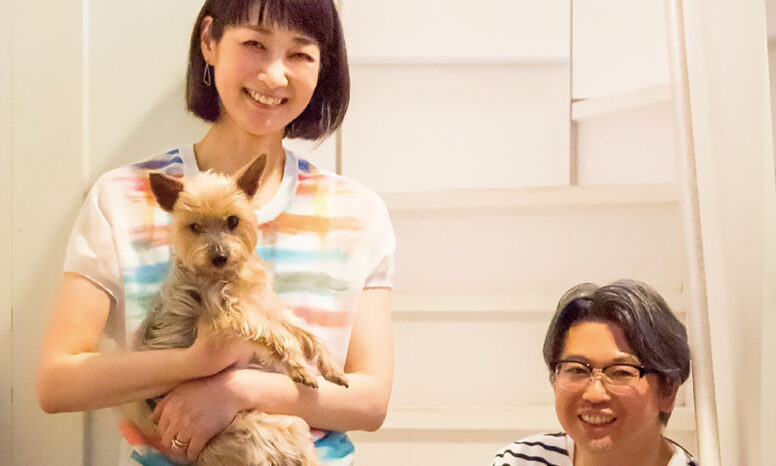而今禾オーナー 西川弘修さん

本来のお正月は春に向かう時期でした
そんな和暦に興味をもっています
伊佐ホームズ駒沢住宅からクルマで10分ほど。「而今禾」は、静かな住宅街の中にあります。桜の木と共に時代を経て、この場所になじんでいるコンクリートのモダニズム建築は、もとは住宅だったといいます。

骨董と現代作家のものも並列に。「箱書きで云々するのはぼくの仕事ではないので」と西川さん。

昭和初期のガラス。昔の職人たちの息づかいが感じられます。
玄関には季節の植物が生けられており、中へ入ると、ヨーロッパのアンティークから、李朝、中国、現代の作家まで、さまざまな時代の家具や器がしつらえられています。それらが醸し出す雰囲気がなんとも心地よく、気持ちがゆったりしていきます。

李朝のバンダチの上に中国の沈香壺を置いて。富士山の額は梅原龍三郎。
「而今禾」は、西川弘修さん、米田恭子さんご夫妻が1998年、三重県関宿で始めたお店。その後、栃木県益子、東京、台湾と拠点を増やしてきました。家具、器、道具、布、衣服、骨董など、扱うものは場所によって異なりますが、どれもときを纏って美しくなっていくような自然素材のものばかり。でも、選りすぐりの逸品を蒐集する、といった感覚とは違います。
「若いときはよくキャンプ生活もしていたんですよ」と、西川さん。
「僕はりんご箱にコップ酒でも満足できるし、ものはなくても暮らせる」なんて、さらりとおっしゃいます。「でもどうせなら、大量生産、大量消費品ではなく、誰かがていねいにつくったものがいいと思うんです」。

エチオピアのテーブルはコーヒーセレモニーに使われたもの。一本の木から削り出されており、なんともいえない力を感じます。

日本の古伊万里、李朝、中国、ベトナムなど少しずつ異なる白磁の湯呑みたち。

シンプルなウィンザーチェア。19世紀のものと思われます。
それは、ものに限らず、食べること、着ること、暮らし全般にいえることです。ともすれば、経済優先のシステムのなかで企画された商品に囲まれる現代生活。その中で西川さんたちが描く世界は、本来のあるべき姿を私たちに教えてくれるようです。
西川さんがいま、興味を持っているのは、和暦(旧暦)だといいます。
「先日、冨田貴史さんにお話を聞いたのですが、気付かされることがたくさんありました。たとえば、(和暦でいうと)今年のお正月は2月19日にあたるとか。本当に春に向かっていく頃だったんですね」

陶芸家、内田鋼一さん作の鉄膳。上に載っているのは高麗時代の匙。

茶室「未休庵」に椿を生けていただきました。花器は駒ヶ嶺三彩さん。
西川弘修(にしかわ・ひろのぶ)
沖縄、北海道、アメリカをまわり、アイヌ民族やネイティブアメリカンと共に過ごす。1999年、米田恭子と三重の関宿に日本家屋を改装した而今禾をオープン。畑や大工仕事などもこなす。
—『伊佐通信』4号(2015年)より転載—
※内容は掲載時のものです
「生活道具美展 仲春のしつらえ」を開催しました(2015年3月)。
初日には駒沢住宅のあちこちで西川さんが器を設定、花道家の上野雄次さんに季節の花を生けていただきました。
会期中には、「和暦ぐらし、旬を食する」と銘打って、冨田さんに和暦のお話を。そして料理研究家の植松良枝さんに滋味あふれるお料理をつくっていただきました。